介護付き有料老人ホームの費用の相場は?費用のシミュレーションをしてみよう
「介護付き有料老人ホーム」への入所を検討する際には、どのくらいの費用がかかるのか、おおまかな目安を把握しておく必要があります。長く利用する可能性がある高齢者施設だからこそ、家族と話し合った上で慎重に検討することが大切です。「介護付き有料老人ホームの費用の相場は?費用のシミュレーションをしてみよう」では、介護付き有料老人ホームの利用にかかる費用相場、費用の内訳、支払い方法、費用シミュレーション、支払いが難しい場合の対処方法などについて解説します。
介護付き有料老人ホームの費用相場
介護付き有料老人ホームは社会福祉法人、医療法人、民間企業が主体となり運営している介護施設です。設備、人員などの運営基準を満たした上で、都道府県の認可を受けた施設のみが該当します。また、介護付き有料老人ホームでは、24時間体制で介護スタッフが在籍し、日常の生活支援、食事、入浴、排せつなどの介助が提供されるため、手厚い介護が必要な場合に有力な候補となる施設。なお、介護付き有料老人ホームへの入所費用には、契約時に支払う「入所一時金」と、毎月支払う「月額利用料」の2つがあります。
入所一時金
入所一時金は契約時に支払う費用で、居住費の前払い金として扱われ、一定期間分の居住費を入所時に前払いすることによって、月々の費用を安く抑えることが可能。なお、入所一時金の相場は0~数百万円と大きな差がある点に注意が必要です。入所一時金に差があるのは、施設の規模、設備、立地などによって影響されるため。例えば、立地が良く土地の価格が高い、交通の便が良い、設備が最新式、介護体制が手厚いなどといった環境にある施設の場合、入所一時金が高くなる傾向にあります。
月額利用料
月額利用料は毎月払う費用で、相場は15~30万円程度です。月額利用料には様々な費用が含まれており、施設によって金額が異なるため、詳細は契約前に確認しましょう。また、入所一時金の制度がない施設では、月額利用料が高く設定される傾向があります。
介護付き老人ホームの費用の仕組み
介護付き有料老人ホームの利用における費用の仕組みとして、入所一時金、「初期償却」、「返還金」、「保全措置」、「月額利用料の内訳」が存在。費用の仕組みを把握しておくと、後々金銭トラブルを避けることができます。
入所一時金とは
入所一時金は、入所時に居住費を前払いする仕組み。前述の通り、介護付き有料老人ホームのなかには、入所一時金が不要な施設もあります。入所一時金を支払う施設の場合、入所後の居住費に割引が適用されるため、入所期間が長くなるほど費用負担を軽減。一方、入所一時金が不要の施設では、事前にまとまった費用を用意しなくても入所できる点がメリットです。
ただし、入所一時金の支払いには月払いを含め、複数の選択肢があるため、必ずしも入所前に数百万円もの費用を一括で用意する必要性がある訳ではありません。また、仮に早期退去した場合、初期償却分、利用期間分の費用を差し引き、残った分のお金が返還される場合もあります。
初期償却とは
初期償却とは、支払われた入所一時金のうち、一部を施設側が受け取る仕組み。入所一時金は、定められた償却期間(月数)で分割して居住費として充当され、入所者が負う月額利用料の負担を軽減します。初期償却に充てられる割合は、施設ごとに変動。
例として、入所一時金が500万円、初期償却が30%、償却期間が5年の場合、入所一時金500万円の30%となる150万円が入所時に償却され、施設側が受け取ります。残りの350万円を償却期間5年(60ヵ月)で割った約5万8,333円が、月々の居住費に充てられる仕組みなのです。
返還金とは
返還金とは、償却期間の途中で施設から退去した場合に限り、残った費用が戻されること。例えば、入所一時金として500万円を支払い、うち30%が初期償却され、償却期間が5年に設定されている施設を3年で退去した場合、初期償却分(150万円)と入所期間3年分(36ヵ月)の費用は戻りませんが、残った2年分(24ヵ月)の140万円が返還されるのです。
入所後すぐ退去する場合は、クーリングオフの適用
入所後、理由にかかわらず90日以内に退去した場合は、クーリングオフ(短期解約特例制度)が適用されます。介護付き有料老人ホームにおけるクーリングオフは、期間内に契約を解除した際に限り、支払った入所一時金のうち、利用日数分の家賃、食費、介護費用などを差し引いて残った金額が、全額返金される仕組みです。
保全措置とは
保全措置とは、老人ホームの経営が悪化し倒産に至った際、未償却分の入所一時金の返還を保証する制度。保全措置はすべての有料老人ホームで義務付けられており、500万円または未償却金額のうち、いずれか低い金額が保全範囲となります。そのため、未償却費用が500万円を超えた分は、保証対象外となる点に注意が必要です。
月額利用料の内訳
月額利用料には、居住費、食費、管理費、介護保険サービス費、その他の費用が含まれています。月額利用料は毎月支払う費用のため、内訳と各種金額をきちんと確認しておきましょう。
居住費

居住費は、施設に住むために必要な費用。一般的な賃貸住宅と同様に、居室の広さ、設備などによって費用に差が生じます。入所する施設の立地、アクセスが良い場合は居住費が高く、悪い場合は比較的安くなる傾向です。
駅に近い、個室、部屋が広い、利便性の良い場所にある、など施設の条件が良くなるほど、居住費は高額に設定されやすくなるため、施設へ入所したあとの日常の過ごし方と費用のバランスを考慮して施設を選びましょう。
食費
食費は、施設で提供される食事にかかる費用。食材を購入する費用の他、厨房の維持管理費、施設が食事を外部に委託している場合は、委託先へ支払う費用も含まれます。また、豪華な食事を提供する施設では、料金も高額になる傾向にあるのです。さらに、おやつを追加したい場合には、別途料金がかかる可能性があります。
管理費
管理費は、共有設備の維持メンテナンス費用、事務費用などが含まれる費用です。施設によっては「運営費」と呼ばれる場合もあります。管理費については施設の規模、設備の充実度、サービス内容によって料金が変動。食費と同様に、管理費としていくらの費用が請求されるのか、契約前に詳細を確認しておきましょう。
介護保険サービス費
介護保険サービス費は、生活支援など各種介護保険サービスにかかる費用のこと。具体的な費用は入所者の身体状況、経済的な状況によって変わります。介護保険サービスを利用した場合、費用の1~3割を自己負担しなければなりません。
その他の費用
その他費用には、医療費、歯ブラシや石鹼などの日用品費、おむつ、ティッシュペーパーなどの消耗品費、理美容費、嗜好品の購入費など様々な項目が含まれます。他にも、サークル活動にかかる費用、体操、ゲーム遊びなどのレクリエーションにかかる材料費なども該当。そのため、購入が必要になる物を事前に確認し、おおまかな費用を想定した上で備える必要があります。
費用の支払い方法
介護付き有料老人ホームへの費用の支払い方法として、「全額前払い」、「一部前払い」、「月払い」の3つが存在。経済状態に合わせて無理のない支払い方法を選択しましょう。
全額前払い
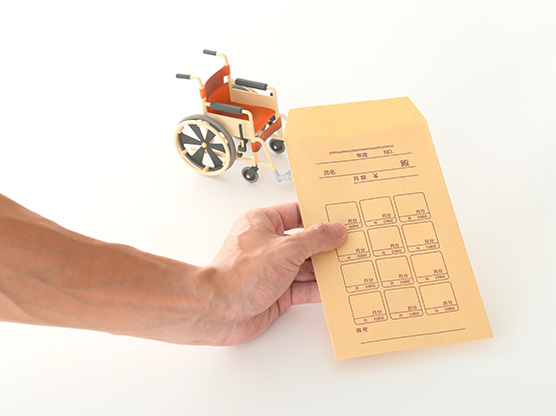
全額前払いは、入所するときに入所一時金をすべて支払う方法。全額前払いを採用している施設の場合、想定される入所期間にかかる総額を入所一時金としており、毎月の費用負担を大幅に減らせるメリットがあります。ただし、全額前払いをすると入所後の費用をやりくりしやすくなる一方、入所前に多額の費用を用意しなければならない点がデメリットです。
一部前払い
一部前払いは、居住費総額のうち一部を先に支払う方法。残りの費用は、入所期間中に分割して支払います。一部前払い方法では、全額前払い方法よりも前払いする金額が少ないため、入所時における費用負担の軽減が可能です。また、一部を前払いしておくことで、月額利用料の負担軽減にもなります。ただし全額前払い方法よりも、支払い総額が高く設定される点がデメリットです。
月払い
月払いは、費用を入所期間中に毎月支払っていく方法。入所時にまとまった費用を用意せずに済むため、長期的に入所する予定ではない方にとって大きなメリット。ただし、毎月の支払い金額が高くなる傾向にある点がデメリットになります。
介護付き有料老人ホームの費用をシミュレーション
介護付き有料老人ホームの費用を入所者の状態に合わせて、シミュレーションしてみましょう。
長期利用を想定している方の場合

介護付き有料老人ホームの長期利用を想定している方の費用をシミュレーションします。
- 要介護2
- 入所一時金:500万円
- 月額利用料:20万円
- 介護保険サービス費用は1割負担で、毎月2万円
毎月支払う費用は、月額利用料20万円に介護保険サービス費2万円を足した、合計22万円です。年間では合計264万円、5年入所すると合計1,320万円必要になります。入所一時金の500万円と合わせると、総額1,820万円かかる計算です。その他、諸費用として医療費、おむつ代、日用品代なども発生します。
短期間の利用の場合
別の施設へ移るまでの短期間だけ、介護付き有料老人ホームを利用したい方を想定し、費用シミュレーションした場合は下記の通りです。
- 要介護3
- 入所一時金:0円
- 月額利用料:30万円
- 介護保険サービス費用は1割負担で、毎月2万7,000円
毎月支払う費用は、月額利用料30万円に介護保険サービス費用の2万7,000円を足した、32万7,000円。1年間利用した場合は、合計392万4,000円の費用がかかります。他に諸費用として医療費、おむつ代、日用品代なども必要です。要介護3のため介護保険サービス費が少し高くなっています。加えて入所一時金を支払わない分、月額利用料も高めに設定。そのため、長期的に利用される方よりも月10万円以上も多く出費が生じるのです。
介護付き有料老人ホームの利用者のなかには、地方公共団体、社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホーム」へ移るまでの待機期間だけ入所する方、その他施設への待機期間のみ入所する方もいます。退去を前提として介護付き有料老人ホームへ入所するため、月々の利用料が割高でも入所一時金を支払わない選択が可能です。退去する前提で短期間の利用を希望する方は、月額利用料のみの支払い方法を選択肢に入れておきましょう。
費用が支払えない場合
介護付き有料老人ホームへ入所したのち、要介護度が上がったり、想定していた以上に医療費がかさんだりして、費用の支払いが苦しいと感じるようになる可能性もあります。その場合は施設スタッフ、ケアマネジャーへ相談してみましょう。施設にもよりますが、支払い期限の延長、分割払いへの対応などをしてもらえる可能性があります。しかし、今後長期的に支払いができない場合は、費用が安い施設へ移るか、公的制度の利用を検討しましょう。
費用が安い施設を検討する

有料老人ホームの入所にかかる費用を払えなくなっても、保証人へ請求されるため、すぐに退去を迫られることはありません。しかし、長期的に滞納が続く場合は、転居、退去を促される可能性もあります。退去を促されてから急いで次の施設を探す場合、じっくりと施設を検討できず、自身に合う入所先選びが難しくなるため、早めに次の施設選びをはじめましょう。
他の施設へ移る場合、有力な候補になる施設として「特別養護老人ホーム」(特養)が挙げられます。特別養護老人ホームは、地方公共団体、社会福祉法人が運営する公的介護施設。入所一時金がなく、かつ月額利用料が低く設定されているのが特徴です。さらに費用を抑えたい場合は、多床室を検討。
特別養護老人ホームの入所の注意点としては、費用の安さから待機期間が長い傾向にあることです。そのため、特別養護老人ホームに入れなかった場合には、下記の選択肢も入れてみましょう。
- より安価な介護付き有料老人ホームへの転居
- 認知症グループホームへの転居
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への転居
同じ介護付き有料老人ホームでも主要な駅、市街地から離れていたり、地方にあったりすると、費用負担が軽い傾向にあります。その場合、月額利用料が大幅に下がる可能性があるため、地域を限定せずに探してみましょう。また、「認知症グループホーム」は、要支援2以上の認定を受けた認知症の方を対象とする施設で、有料老人ホームと比べると費用が低く設定されている傾向にあります。特に認知症を発症している方の場合は、転居に適した施設です。さらに、「サービス付き高齢者向け住宅」にも、介護付き有料老人ホームより低料金で入所できる施設があるため、こちらも選択肢として探してみましょう。
公的制度を活用する
公的制度を活用することで、介護付き有料老人ホームにおける費用負担を軽減できる可能性があります。
- 1高額介護サービス費
-
「高額介護サービス費」とは、介護保険サービスの利用時に、自己負担額(1~3割)が限度額を超えた場合に超過分が還付される制度です。限度額の基準は個人、世帯の所得に応じて規定されています。自己負担額の上限を超えて介護保険サービスを利用した場合、自治体より申請書を送付。介護保険サービスを利用した、翌月1日~2年以内が申請期限のため、忘れず申請しましょう。
- 2高額医療・高額介護合算療養費
-
「高額医療・高額介護合算療養費」とは、介護保険サービス費と医療費における自己負担額の年間合計額が限度額を超えた場合に、超過分が還付される制度です。高額介護サービス費制度と同じく、自己負担額限度額は所得に応じて決められています。同一世帯で同じ医療保険に加入している場合、家族の分も合算が可能。介護保険サービス費、医療費として支払った金額を把握しておき、限度額を超えたときは市区町村の役所まで申請しましょう。
- 3扶養控除
-
「扶養控除」とは、納税者に控除対象の扶養親族がいる場合に、一定金額の所得控除を受けられる制度です。家族が介護付き有料老人ホームに入所している場合も、控除の対象になる場合があります。例えば、親の老人ホーム費用を負担している方、離れた場所で暮らしながら親の介護費用を仕送りしている方が該当。控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無によって変わります。
扶養親族が以下の項目に当てはまる場合、介護付き有料老人ホームに入所したあとでも扶養控除を受けることが可能です。
- 納税者と同一生計
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 介護施設への入所前から納税者の扶養に入っている
納税者と同一生計にある状態は、必ずしも同居している必要はありません。入所者の老人ホーム費用を納税者が負担している場合、同一生計とみなされます。一般的な控除額は1人当たり38万円になりますが、扶養している入所者の年齢が70歳以上の場合は老人扶養親族に当てはまるため、48万円の控除が該当。扶養控除を受けるには、確定申告で扶養控除申請書を提出する必要があります。
まとめ
介護付き有料老人ホームにおける費用は施設の立地、設備、サービス内容、人員配置などによって様々です。希望する施設で余裕を持って生活するには、費用がいくら必要かを整理し、自身の経済状況を考慮して施設を選ぶ必要があります。また、入所後すぐに退去するのを避けるためには、実際に施設を見学したり、市区町村の相談窓口を積極的に活用したりするのも大切です。支払い方法、契約内容、支払いが難しくなった場合の対処法などを把握したうえで、適した施設を選びましょう。


