ケアプランとは?目的や内容、作成の流れを分かりやすく解説
ケアプランは、要介護または要支援認定を受けた高齢者が、介護サービスを受けるために必要な計画書です。プランを作るにあたっては、被介護者と家族の意向に沿って介護目標を設定し、それに必要となるサービスを決定。ケアプランの目的や種類、作成の流れ、セルフケアプランの概要、確認するポイントを解説します。
ケアプラン(介護サービス計画書)とは
ケアプランとは、被介護者や家族の意向に基づいて、被介護者がどのような介護サービスを受けるべきか定めた計画書です。ケアプランがなければ、介護サービスは利用できません。
ケアプランの目的

介護保険を利用して解決したい課題は、被介護者によって異なります。「日中は家族が不在でひとりは不安」、「入浴や食事をひとりではできないので、できないところを手伝ってほしい」など、置かれた状況や、抱える問題が、人によって異なるためです。
それぞれの課題を解決できるよう短期・長期の目標を定めて、計画的に介護サービスを利用できるようにするのが、ケアプランの目的になります。
ケアプランはケアマネジャーが作成
居宅介護支援事業所などに依頼すれば、在籍しているケアマネジャーがケアプランを無料で作成してくれます。ケアマネジャーは介護の専門家で、ケアプランの作成や、自治体・介護サービス事業者・施設などとの連絡・調整を行うことで、利用者を援助。介護職員、医療従事者や福祉用具専門相談員など、様々な職種がチームになって行う介護のなかで、リーダー的な役割を果たします。
ケアプランの種類
ケアプランは、「居宅サービス計画」、「施設サービス計画」、「介護予防サービス計画書」の3種類です。要介護認定の介護度によって、利用できるプランが異なります。
居宅サービス計画
居宅サービス計画とは、在宅で介護サービスを受けるためのプラン。要介護1~5の人が対象で、サービスの種類と内容は以下の表の通りです。
| サービスの種類 | サービス内容 |
|---|---|
| 訪問 サービス |
|
| 通所 サービス |
|
| 短期入所サービス |
|
| その他のサービス |
|
施設サービス計画
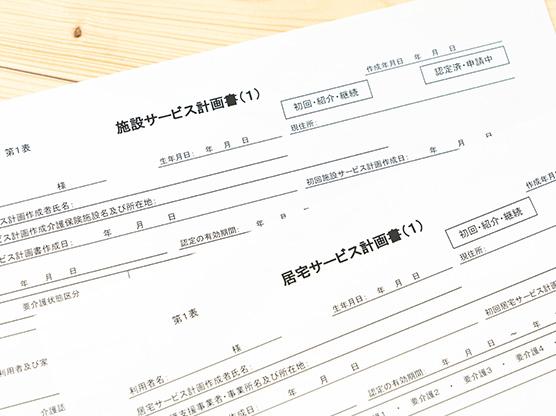
施設サービス計画は、介護施設でのサービスを受ける要介護1~5に認定された人が対象で、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の3つの施設を利用する際に必要です。施設によって入居基準や入居できる期間が定められ、サービス内容も異なります。
施設に在籍するケアマネジャーが、入居者様ひとりひとりの希望に合わせたプランを作成しますが、施設ごとに特徴が異なるため、プランの内容も異なるのです。
| 施設の 種類 |
サービス 内容 |
入居基準・その他 |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
|
|
| 介護老人保健施設 |
|
|
| 介護医療院 (介護療養型医療施設) |
|
|
介護予防サービス計画
介護予防サービス計画は、要支援1または2に認定された方が、介護予防サービスを利用する際に必要なケアプランです。まだ介護を必要としない人が、今後介護を必要とする状態にならないようにサポートを受ける際に必要となります。介護予防サービス計画は、地域包括支援センターのケアマネジャーや保健師などによって作成されるのです。
| サービスの種類 | サービス内容 |
|---|---|
| 介護予防サービス |
|
ケアプラン作成の流れ

- 1現状把握(インテーク)
-
現状把握は、被介護者が置かれている状況を把握するための重要なファーストステップです。
直接面談や電話などで、サービスを利用したい本人や家族の希望、困りごと、体調、家庭環境などを把握します。
- 2情報収集(アセスメント)
-
次に、被介護者の家を訪問して、健康状態、自宅の環境、介護の状況、本人や家族の要望、どんな生活をしたいのかを確認し、情報収集。詳細な聞き取りをすることで、必要なサービスは何か、課題は何かを分析可能です。このとき、聞き取った情報を客観的に判断するために、厚生労働省が示している「課題分析標準項目」を用いて評価をします。
(参考:厚生労働省、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正等について) - 3ケアプランの原案作成
- 情報収集の結果をもとに、ケアプランの原案が作成されます。被介護者や家族の要望に合わせた必要なサービスの検討、長期・短期目標の設定、プランの組み立てなどを実行。原案をもとに、利用が可能なサービス事業者との連絡調整を行います。完成後は、被介護者の希望と間違っていないか、本人や家族に見せて確認するのです。
- 4サービス担当者会議
- ケアマネジャーを中心として、被介護者と家族、サービス事業者の担当者、主治医などの関係者とプラン原案をもとに会議を実施。生活の状況や課題の認識を参加者間ですり合わせ、目標や方針、計画を共有します。会議のなかでは、再度本人や家族、関係者からの考えを聞き、計画したケアプランに問題がないかを確認するのです。
- 5ケアプランの完成・交付
- 会議で出た意見をもとに、変更すべき点があれば原案を修正。そして、改善案が被介護者や家族に再提案され、同意が得られればケアプランは完成です。被介護者や家族がケアプランに同意したのち、同意書に自署・押印をすることで、交付は完了となります。完成したプランは、サービス提供事業者にも交付される仕組みです。
- 6モニタリング
-
サービス開始後、最低でも月に1回以上、ケアマネジャーが被介護者の自宅を訪問し、サービスがプラン通りに提供されているかを確認します。定期的なモニタリングを行って、サービスの変更が必要と判断した場合には、ケアプランを修正し、再交付。
モニタリングをすることで、ケアプランを適正に保てるだけでなく、被介護者・家族とケアマネジャーとの良好な関係を築くことができ、被介護者と家族の安全・安心につながります。また、約6ヵ月に1回は、被介護者や環境の変化に応じてプランを見直し、修正していくのです。
ケアプランの例
ケアプランは、第1~7表の7枚で構成され、第1、2、3、6、7表の5枚を被介護者、家族、事業所へ交付。ここでは、第2表居宅サービス計画書(2)の項目の記入例を紹介します。
| 生活全般の 解決すべき課題 (ニーズ) |
長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| ベッドからの起き上がり、立ち上がりをひとりでできるようになりたい | 就寝時に起居動作ができるようになる | バランスを崩すことなく、起き上がりや立ち上がりができるようになる |
| 自分で排泄ができるようになりたい | 規則的な排泄の習慣を身に付ける | 規則的な時間にトイレに行けるようになる |
| 転倒することなく、安全に入浴したい | 安全にひとりで入浴できる | 入浴を習慣付ける |
| 栄養バランスの取れた食事を摂りたい | バランスの良い食生活をする | 規則正しく、食べられる |
| 介護者の負担を軽減させたい | 介護者の病状悪化を防ぎ、夫婦での生活を継続する | 本人と介護者の負担軽減を実施する |
| 生活のなかで楽しみを見つけたい | 楽しみを持って生活する | 外出の機会を設け、刺激のある生活をする |
被介護者や家族が作成するセルフケアプランも
「セルフケアプラン」とは、被介護者や家族が作るケアプランのことです。自分で作成する場合には、市区町村の介護保険課にケアプラン作成を申し出て、必要な書類をもらいます。サービス事業者について調べて、自分でケアプランを作成。サービス担当者会議を開いてケアプランを完成させ、サービス提供事業者にケアプランを交付して、利用を開始します。
介護サービス利用中は、自分で事業者と連絡を取り、毎月サービス利用実績を自治体に提出。介護サービスに慣れていないと、ケアプランを作るのは難しいと感じる方も多いかもしれません。
セルフケアプランのメリット
一番のメリットは、自分や家族が納得のいくケアプランを作れる点。利用する事業者は、本人や家族の希望で選べるため、利用する際の不安や不満も減らせます。
また、ケアプランをケアマネジャーに作成してもらった場合には定期的なモニタリングが必要ですが、自分で作った場合にはケアマネジャーとのやり取りは不要で、かかる時間を短縮させることが可能。やり取りを負担に感じる人は、セルフケアプランはおすすめです。
セルフケアプランのデメリット
利用する事業者についての情報収集や、事務的な手続きをすべて自分で行わなければいけません。介護について不慣れな人や、十分な知識があるか不安な人は、ケアプランの作成を難しく感じることが多いです。
また、被介護者や家族は介護のプロではないため、専門性に欠けたプランになるケースもあります。どうしても自分でケアプランを作成したい場合は、自治体の介護保険課で相談し、専門家の意見を聞きながら作ることが重要です。
ケアプラン作成時に確認すべきポイント
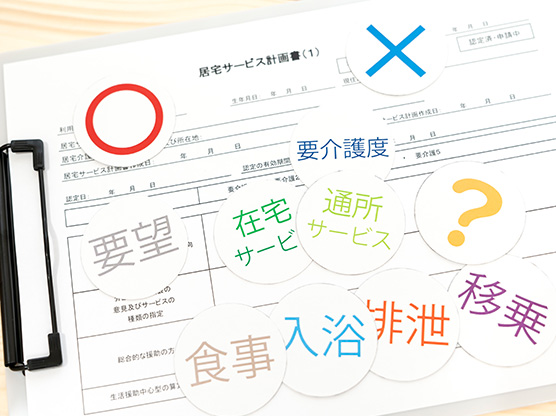
作成時に確認すべきポイントについて、被介護者側とケアマネジャー側とで解説します。
被介護者が確認すべきポイント
ひとつ目は、作成をケアマネジャーにすべて任せないで、自分の意向を伝えることです。
ケアマネジャーは介護の専門家ですが、利用者側の希望や意向を完全に推察できるわけではありません。自分や家族の希望を具体的に伝えていないと、家族の要望を十分に満たせないケアプランができあがる場合があります。被介護者は、自分が利用するサービスなので、遠慮しないで自分の意向を伝えておくことが重要です。
2つ目は、サービスを利用する費用が高すぎないか確認することです。ケアマネジャーが作成したケアプランにあるサービスについて、自己負担額が高額になっていたり、利用者の経済状況に合わなかったりする場合は、計画的な利用が難しくなるおそれがあります。経済的に無理のないケアプランか、事前にしっかり試算しておきましょう。
ケアマネジャーが確認すべきポイント
ひとつ目は、家庭の経済状況は最初に確認することです。経済状況が分からなければ、サービスを受ける際の費用負担の限度額が分かりません。ケアプラン完成後に、費用を負担できないということを避けるためにも、最初に経済状況を確認する必要があります。
2つ目は、被介護者や家族のニーズの優先順位を考慮できているかどうかです。被介護者と家族で、意向が異なる場合には、なるべく被介護者本人の意向を確認します。ただ、被介護者の意見ばかりを聞いていると、家族の希望は考慮できないため、本人と家族の意向が異なる場合には、両者と相談しながらお互いの妥協点を見つけ、優先順位を決めるのが重要です。
3つ目は、ケアプランの課題欄で後ろ向きな言葉を使用していないかどうか。課題欄には、現状の問題点ではなく、希望する生活を送るために何を達成したいかを記載します。例えば、「自分で食事ができない」ではなく、「自分で食事ができるようになりたい」とすることで、将来に向けた前向きな行動を促せるようになるのです。
まとめ
介護サービスを受ける際に必要な計画書であるケアプランは、高齢者にとって重要なものです。基本的にはケアマネジャーが作成しますが、状況によっては被介護者本人や家族も作成可能。ケアプランには種類や確認すべきポイントなど、抑えておくべき要素が数多く存在します。介護を受ける本人がしっかり課題を解決できるように、しっかり打ち合わせを重ねて作ることが大切です。


