地域密着型サービスとは?種類を一覧で簡単に解説
地域密着型サービスとは、普段の生活に介護が必要になっても、慣れ親しんだ地域で生活を送れるよう、サポートを目的として提供されるサービスのことです。今後の日本では、高齢者の増加と平均寿命の伸びに伴って、介護を必要とする人が増えることが予測されます。地域密着型サービスの概要、費用、サービス利用の条件などについて見てみましょう。
地域密着型サービスとは

地域密着型サービスは、生活に介助が必要な状態になっても、住み慣れた地域で過ごすことができるよう、市区町村が中心となって提供するサービス。
要介護度(介護の必要度)によって、受けられるサービスには違いがあり、要支援1~2(比較的生活への支障が少ないと判断される場合)には、利用できないサービスもあります。
地域密着型サービスの利用を検討するときは、利用条件に自分が当てはまっているか確認しましょう。
利用できるサービス
地域密着型サービスでは、非常に幅広い支援を行っているのが特徴。利用できるサービスは大きく4つに分けられます。
- 通いで支援を受けられる「通所型」
- 専門職員が自宅訪問をして行う「訪問型」
- 施設に入居しながら受けられる「施設型」
- 通所や訪問、宿泊を組み合わせた「複合型」
提供しているサービス内容は地域によっても異なるため、サービスの詳細が気になる場合は、自身の住む地域包括ケアセンターや担当のケアマネジャーに確認してみましょう。地域密着型サービスの施設は、事務所が地域住民同士の交流が行いやすい場所に設置されていることが多いため、地域での生活を大切にしている方にとっては特に便利です。
居宅サービスとの違い
介護保険には、地域密着型サービスの他にも、居宅サービス(自宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般)、施設サービスがあり、それぞれで支援内容や特徴が異なります。
居宅サービスは居宅で生活をしていながらも、受けることができるサービス。地域密着型サービスと同じように、訪問や通所での支援も行っているため、地域密着型サービスとどこが違うのか疑問を感じる方も少なくないでしょう。
居宅サービスと地域密着型サービスの違いは、大きく3つあります。
- どこが管轄しているか
- 利用者の範囲
- サービスの規模の大きさ
まず、居宅サービスの管轄は都道府県が担っているのに対し、地域密着型サービスの管轄は市区町村が行っています。また、地域密着型サービスを使うことができるのは、事業者のある地域に住んでいる人のみという点も特徴。同じような内容のサービスでも、地域密着型で提供されるサービスは比較的小規模となっているのです。
小規模のサービスでは、スタッフが利用者それぞれに寄り添い、個人を大切にした関係ができます。また、職員や利用者の顔を覚えやすく、仲の良い人ができたり、アットホームな空間を楽しめたりするのです。
地域密着型サービスの種類
地域密着型サービスのうち、代表的な10個の支援内容について見てみましょう。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、入浴や排泄など身の回りの介護をしてくれる訪問介護、看護師が自宅に出向き健康管理を実施してくれる訪問看護を利用することができます。また、定期的な巡回や、利用者の連絡に応じた対応も行います。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護とは、18~翌朝8時の夜間帯に対応した訪問介護です。介護が必要なのは日中だけではないため、日常生活の手伝いから安否確認等を夜・早朝に実施します。
地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、通いながら介護を受けられる、いわゆるデイサービスのこと。
居宅サービスでもデイサービスを利用することができますが、地域密着型サービスは定員19人以下という条件があります。
定員が少ないことで、スタッフが対象者一人ひとりを把握しやすいため、スタッフや利用者が仲良くなりやすいのがメリット。地域密着型通所介護では、通って来た人の食事や入浴などの日常生活の支援が実施されています。
療養通所介護
療養通所介護は、医療的措置が必要な方も受け入れているデイサービス。通常のデイサービスでは、医療的な措置を必要とする人が通所できない場合もありますが、療養通所介護では医療的措置を行う環境が備えられているのが特徴です。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、認知症患者を対象としたデイサービス。日常生活の支援やレクリエーション等も実施されていて、楽しみながら友好を深める機会もあります。定員は12人で、他の利用者やスタッフの顔を覚えやすいため、認知症患者にもやさしい環境となっています。
小規模多機能型居宅介護
通所・訪問・宿泊を、ひとつの事業所が行っているのが小規模多機能型居宅介護の特徴です。基本的には通所型のサービスを利用し、必要に応じて訪問や、短期での宿泊も受け入れています。サービスがひとつの事業所にまとまっていることにより、スタッフとの関係を作りやすく、何かあったときに相談がしやすい環境が大きな強みです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護は、認知症患者が入居できる施設で、グループホームとも呼ばれます。5~9人の少人数が、専門知識のあるスタッフと共同生活。入居者様の能力に応じて、スタッフと一緒に家事を行うのが特徴です。
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の有料老人ホームやケアハウス等のことです。施設に入居しながら、日常生活の支援や運動が実施されています。
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設は、定員数が29人未満の特別養護老人ホームのことです。日常生活の支援、健康管理などが実施されています。通常の特別養護老人ホームに比べて小規模で、地域住民しか入居できないといった点が特徴です。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)では、ひとつの事業所がデイサービス・ショートステイ・訪問介護・訪問看護をまとめて行っています。看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護は、365日24時間運営される施設。小規模多機能型居宅介護との大きな違いは、訪問看護も提供している点です。
地域密着型サービスを利用する条件

地域密着型サービスは、一定の条件を満たした人だけが利用できます。
条件は以下の通りです。
- 市区町村が指定した事業者がある地域に住んでいる
- 要介護認定者
通常の介護サービスを受けるためには要介護認定が必要ですが、地域密着型サービスでは、要介護認定に加えて、指定された市区町村に住んでいなければ利用できないという条件があります。
地域密着型サービスを利用するまでの流れ
地域密着型サービスを利用するためには、適切な手順を踏む必要があります。
- 1要介護認定の申請
-
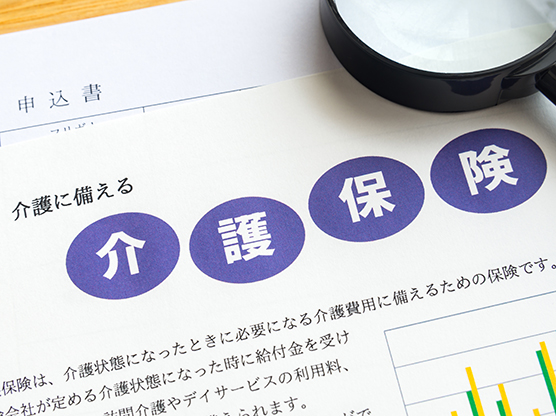
要介護認定は、各市区町村の窓口で申請することが可能です。申請には介護保険被保険者証が必要。
申請後は職員が自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。そのあと、かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらい、聞き取り調査や書類の情報をもとにして1次判定・2次判定が行われ、要介護度が決まるのです。
- 2担当のケアマネジャー・地域包括支援センター等に相談
- 要介護認定を受けたら、担当のケアマネジャーや地域包括ケアセンターに相談をしましょう。専門スタッフが生活状況や身体状況に合わせて、必要なサービスについて相談に乗ってくれます。
- 3利用したい事業所を探す
- 利用したいサービスが決まれば、次は事業所探しです。事業所が見付かっても空きがないと支援を受けられないこともあるため、空き状況の確認も必要。検索やケアマネジャー、地域包括ケアセンターに協力してもらい、空きのある事業所を探しましょう。
- 4ケアプラン作成
- 事業所が決まれば契約をし、支援の支柱となるケアプランの作成を依頼します。ケアプランは、介護が必要な人の生活上の問題点改善と軽減を目的とした計画書。事業所はケアプランに沿って、サービス提供を実施します。
- 5利用開始
- サービスが開始したあとも、ケアマネジャーや地域包括ケアセンターと相談し、支援内容の改善・調整を進めます。市区町村への申請や施設探し、空き状況の確認など時間がかかることもあるため、各手続きの準備は早めに始めましょう。
まとめ
介護が必要であっても、住み慣れた地域で生活をすることは、生きがいを保ち、生活の質を維持することに繋がります。地域密着型サービスでは、地域が主体となり、通所や訪問、宿泊など様々なメニューを提供。また、ケアマネジャーや地域包括ケアセンターに相談することで、一人ひとりに合ったサービスを検討できます。サービス利用までには時間がかかることもあるため、早めに準備することをおすすめします。


