老人ホームを契約するときに気を付けたい注意点5選!トラブルを未然に防ごう
「老人ホーム」を契約するときは、特に「重要事項説明書」、「入居契約書」などを読み込んで理解することが重要です。入居したあとにトラブルが発生しても、すぐには対応できない場合も少なくありません。入居後に後悔しないためにも、老人ホームを契約するときの注意点の把握は大切です。「老人ホームを契約するときに気を付けたい注意点5選!トラブルを未然に防ごう」では、5つの注意点、重要事項説明書の見方、必要な書類などについて詳しくご紹介します。
老人ホームの契約は「重要事項説明書」の確認が必須

老人ホームの契約をする際、重要事項説明書の確認は欠かせません。老人ホームでは「老人福祉法」により、入居希望者の求めに対してすぐ交付できるよう、重要事項説明書の作成が義務付けられています。重要事項説明書には老人ホームの「運営元」や提供している「サービス内容」、「費用」など老人ホームへ入居する場合に知っておくべき事項が掲載されています。
重要事項説明書のポイント
重要事項説明書の各項目のなかで、見ておきたいポイントを紹介します。
記入年月日
事業の概要
共用施設やその他
苦情・事故等に関する体制
入居希望者への事前の情報開示
その他
| 重要事項説明書の記載項目 | |
|---|---|
| 記載項目 | 内容 |
| 記入年月日 | 重要事項説明書が作成または更新された日 |
| 事業主体概要 | ・個人か法人か ・事業主の名称 ・事業主の所在地 ・事業主の連絡先 ・代表者名 ・設立年月日 ・主な事業 |
| 有料老人ホーム事業 の概要 |
・老人ホームの正式名称 ・主たる事務所の所在地 ・最寄り駅 ・交通手段と所要時間 ・連絡先 ・管理者氏名 ・管理者職名 ・建物の施行日 ・老人ホームの開始年月日 ・類型 |
| 建物概要 | ・土地の敷地面積 ・事業主が所有する土地 ・事業主が賃貸する土地 ・建物の延床面積 ・耐火構造 ・構造 ・事業主が所有する建物 ・事業主が賃貸する建物 ・居室区分 ・共用施設 ・消防用設備など ・その他 |
| サービスの内容 | ・老人ホームの運営方針 ・サービスの特色 ・入浴、排せつ、食事の介護 ・食事の提供 ・洗濯、掃除など家事の供与 ・健康管理の供与 ・安否確認または状況把握サービス ・生活相談サービス ・特定施設入居者生活介護の加算対象となるサービス体制の有無 ・人員配置が手厚い介護サービス実施の有無 ・医療支援 ・協力医療機関 ・協力歯科医医療機関 ・入居後に居室を住み替える場合の判断基準 ・居室住み替えの手続き内容 ・居室住み替えの追加費用の有無 ・居室住み替えの居室利用権の取扱い ・居室住み替えの前払い金償却調整の有無 ・居室住み替えした場合の居室の仕様変更 ・入居対象者 ・留意事項 ・契約解除の内容 ・事業主体から解約を求める場合 ・入居者様からの解約予告期間 ・体験入居の内容 ・入居定員 ・その他 |
| 職員体制 | ・職種別の職員数 ・資格を有する介護職員数 ・資格を有する機能訓練指導員数 ・夜勤を行う看護、介護職員数 ・特定施設入居者介護等の提供体制 ・職員の状況 |
| 利用料金 | ・居住の権利形態 ・利用料金の支払い方式 ・年齢に応じた料金設定 ・要介護状態に応じた料金設定 ・入院などでの不在時における利用料金の取扱い ・利用料金の改定条件、手続き ・利用料金の代表的なプラン2例 ・利用料金の算定根拠 ・特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠 ・前払い金の算定根拠 ・前払い金の償却年月数 ・償却開始日 ・初期償却額 ・初期償却率 ・返還金の算定方法 ・前払い金の保全先 |
| 入居者様の状況 | ・入居者様の内訳 ・平均年齢 ・合計 ・入居率 ・前年度の退去者状況 |
| 苦情・事故等に 関する体制 |
・窓口の名称 ・電話番号 ・対応している時間 ・定休日 ・損害賠償責任保険の加入状況 ・介護サービスの提供で賠償すべき事故が発生した場合の対応 ・事故対応、及び予防のための指針 ・利用者アンケート調査など、利用者の意見を把握する取り組みの状況 ・第三者による評価の実施状況 |
| 入居希望者への 事前の情報開示 |
・入居契約書の雛形 ・管理規定 ・事業収支計画書 ・財務諸表の要旨 ・財務諸表の原本 |
| その他 | ・運営懇親会の有無 ・提携ホームへの移行 ・有料老人ホーム設置時の老人福祉法第29条第1項に規定する届出 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録 ・有料老人ホーム設置運営指導指針「5.規模及び構造設備」に合致しない事項 ・有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項 |
出典:公益社団法人全国有料老人ホーム協会「重要事項説明書の見方」
重要事項説明書の別添え資料
重要事項説明書には、「別添え資料」が2種類付属。ひとつ目の資料は、「事業主体が当該都道府県、政令指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス」です。老人ホームのある地域で事業主がどのような介護サービスを行っているか確認できます。
2つ目の資料は、「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表」。老人ホームの契約ではありますが、介護保険で「特定施設入居者生活介護」の認定を受けている施設として、「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)が、それぞれどのようなサービスを提供しているかを提示することが義務付けられています。
老人ホームの契約時に注意すべき5つのポイント
老人ホームの入居契約をするとき、見ておきたい注意すべき5つのポイントを、重要事項説明書や入居契約書の内容も交えてご紹介します。
- 1入居一時金・月額利用料などの費用
-
「入居一時金」や「月額利用料」などの費用は、利用料金の項目で確認できます。特に、入居一時金などの前払い金は、費用の説明や残額を返還するときの計算方法などが書かれているため、熟読しましょう。また、月額利用料の内訳も家賃や食費、光熱費などが細かく記載されており、費用の算定基準も分かります。月額利用料に何を含むのかは、老人ホームによって異なるため注意が必要です。
さらに、スタッフの手厚い「人員配置」による「上乗せ介護費」や、入居者様が入院などで不在時にも利用料金が発生するかもチェックしましょう。基本的には入居者様が不在時でも利用料金は発生しますが、割引きされる場合もあるため確認が必要です。
- 2介護サービスの体制・内容
-

重要事項説明書の介護サービスの内容確認では、食事や入浴など生活にかかわるサービスを行っているか、また外部委託かどうかがチェックポイントです。生活にかかわるサービスを行っていない場合は、利用者自身で食事や入浴を行う必要があります。
また、類型欄には老人ホームが介護付きなのか、介護サービスなしなのかが記載。介護付きの場合は、「介護保険事業者」としての登録内容も確認できます。都道府県や市区町村から指定を受けた介護保険が適用される施設「特定施設入居者生活介護」に登録されている場合、「個別機能訓練加算」など、加算対象のサービスの有無も確認が必要です。
- 3医療体制
- 「医療体制」は、通院や入退院時にサポートがあるのか、救急車を手配するのかなどを確認できます。また、施設外の協力医療機関についても記載されており、医療面でどのような協力体制があるのかが確認可能です。さらに、亡くなるまでの過程を見守る「看取り」体制が整っているかなども確認が可能。最期まで過ごせる老人ホームを探している場合は、看取りの確認をしましょう。
- 4スタッフの体制
- スタッフの体制は「職員体制」の項目に記載されており、常勤換算人数や夜勤スタッフの人数を確認できます。常勤換算人数は、実際に働いているスタッフの実人数ではなく、常勤換算人数を算出する計算式の数字となるため、働いている人数と同じでない場合もあるので、注意しましょう。他にも、利用者に対して介護、看護スタッフが何人いるかの比率なども確認できます。スタッフの比率が多いほど、より手厚い介護が受けやすい施設です。
- 5契約解除・退去の条件
-
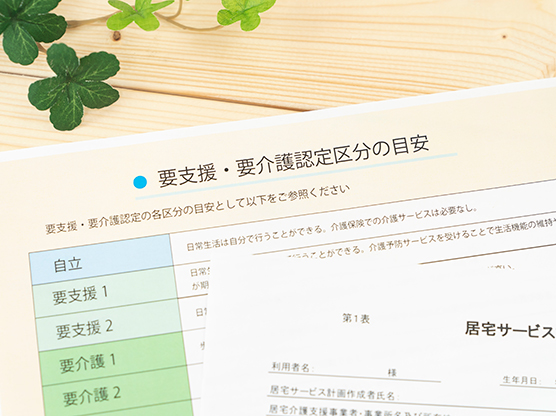
解約条件は入居契約書で確認できます。また、契約解除は利用者の契約違反により、退去を求められるケースもゼロではありません。意図せず契約違反をしないためにも、解約条項に書いてある内容を理解しておく必要があります。
また、利用者側から退去を求める場合は、退去する何ヵ月前までに施設へ伝えておくこと、なども決められているため注意しましょう。直前での退去予告などは、追加費用が発生する恐れもあります。さらに、長期入院をした場合に、施設から退去を求められるケースもあるため、記載されていない場合は、直接老人ホームに問合せてみましょう。
契約時の書類は退去するまできちんと保管
契約関係の書類は、もし契約後に施設側とトラブルになった場合の証拠になります。そのため重要事項説明書をはじめ、契約に際して使用した書類は、退去するまですべて保管しておきましょう。また、施設に提出するため、手元に残らない書類は、提出前にコピーを取っておくことがおすすめです。
老人ホーム・介護施設との契約時に必要な物
老人ホームや介護施設と契約する際には、様々な物が必要です。施設によって、金銭管理の必要性から通帳のコピーもしくは原本、また老人ホームが独自に発行する物品預り証など、必要な書類などが異なります。施設に何が必要か確認しましょう。
契約時には、「入居申込書」や入居契約書(利用契約書)にサインや押印、デジタル署名をします。入居申込書は、施設を利用したい意思を伝え、利用者の基本情報を記載する書類です。入居申込書の提出後、面談などを経て入居契約書を提出。入居契約書は、施設と利用者でお互いの権利や利用者の入居条件、注意事項などを確認し、問題がなければサインと押印、もしくはデジタル署名をします。
なお、契約後のトラブルを防ぐためにも、重要事項説明書や入居契約書での説明を受けるときに、疑問点は聞いておくのがおすすめです。記載されていない費用はないか、家族の宿泊が可能か、持ち込み禁止物はないかなど、書類だけでは分かりにくいことを確認しておきましょう。
老人ホーム・介護施設との契約時に必要な物
- 住民票や戸籍謄本
- 印鑑
- 印鑑証明
- 健康診断書
- 診断情報提供書
- 看護サマリー(病院から施設へ入居する場合)
- 身分証明書
- 所得証明書
- 身元引受人
- 連帯保証人
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者保険証
- マイナンバー
契約後・入居後にトラブルになったら
細かく契約書をチェックしても、意図しないトラブルに巻き込まれる可能性があります。トラブルになった場合の対処方法を知っておくと、もしものときも慌てずに対応が可能です。
第三者に相談する
当事者同士の話し合いで解決できそうにない場合は、第三者を頼ります。老人ホームでのトラブルについて相談できる機関と連絡方法は、以下の通りです。
- 入所者本人、もしくは家族から担当ケアマネジャーに相談
- 障がい認定されている高齢者の場合、相談支援事業所の相談支援専門員に相談
- 重要事項説明書に記載の苦情受付相談窓口へ電話
- 消費者ホットライン「188」に電話をすると、地方公共団体の消費者生活センターなどに案内してくれる
- 都道府県の国民健康保険団体連合会:住んでいる都道府県の問合せ窓口に連絡
- 自治体役所の介護保険課や高齢福祉課:役所窓口へ訪れるか、電話で問合せる
- 日本司法支援センター「0570-078374」に電話をすると、法の手続きや解決の相談窓口を教えてもらえる
- 全国老人ホーム協会「03-3548-1077」で有料老人ホームに関する苦情や相談を受け付けており、電話予約すれば面談もできる
クーリングオフ制度を活用すればお金が返還される
クーリングオフ制度とは、2012年(平成24年)に法律で義務付けられ、90日以内に退所した場合、月額費用など必要諸経費以外の一時入居金が全額返金される制度です。「短期解約特例」や「90日ルール」とも呼ばれます。
法律で定められる以前にも90日ルール自体は存在しましたが、義務ではなかったため、トラブルになった際に利用者側が諦めるしかないケースも多発。それに伴う相談や苦情が相次ぎ、法が整備されました。もしクーリングオフ制度に施設側が従わず、返金しなかった場合は施設に罰則が与えられる仕組みです。
なお、クーリングオフ制度は、利用者が自ら退去した場合だけでなく、亡くなった場合にも適用されます。
まとめ
老人ホームや福祉施設でのトラブルを未然に防ぐには、重要事項説明書、入居契約書(利用契約書)に記載している契約内容の確認が大切です。費用が何に対してかかっているのか、サービスはどこまで受けられるのか、そして要介護度がどこまで対応できるのかなどは、しっかりとチェックしておきましょう。契約後に意図しないトラブルが発生する可能性もあるため、もし分からないことがあれば、理解できるまで確認することをおすすめします。


