慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは?症状や原因、治療法などを分かりやすく解説
「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」は、長期間にわたってタバコや他の有害物質を吸い続けることで、肺が炎症を起こす疾患です。進行すると、日常の簡単な動作、例えば着替えるだけでも息切れを感じることがあります。特に40歳以上で、かつて喫煙していた人は慢性閉塞性肺疾患(COPD)のリスクが高め。また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、高齢者に多く見られる疾患のひとつでもあります。慢性閉塞性肺疾患(COPD)に関する症状や原因、診断方法、治療法、予防策について、詳しくまとめました。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、肺の気道が慢性的に炎症やけいれんによって閉塞(へいそく:閉じること)し、空気が吸い込めなくなる病気です。以前は、「慢性気管支炎」や「肺気腫」(はいきしゅ)と呼ばれていました。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、タバコの煙やその他の有害物質に長期間さらされることで、肺組織が継続的な炎症を起こすことが原因。特に、喫煙が主な要因であるため、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は生活習慣に関連した疾患と言えます。多くの場合、中高年以降、特に高齢者における発症が増えているのです。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、肺炎や肺がんといった重大な病気のリスクを高めてしまうため、早期に発見し、適切な治療を受けることが重要。なお、日本呼吸器学会の「COPD診断と治療のためのガイドライン」によれば、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の5年生存率は約60%と言われています。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の症状

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、その症状が表面化するまでに時間がかかることが多く、気付いたときには、肺に深刻なダメージが生じている場合があります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、進行すると労作時(ろうさじ:身体を動かしているとき)の息切れ、慢性の咳 、痰の増加といった症状が出現。さらに進行すると、栄養不足になり、体重が減少することもあるのです。
また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、多くの疾患と関連があると言われています。例えば、「高血圧」、「虚血性心疾患」、「慢性心不全」といった心臓の疾患、骨密度の低下と骨のもろさを引き起こす「骨粗鬆症」、脂質の代謝異常、消化器系の病気、精神的な問題である「うつ症状」など。特に、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者は、非喫煙者に比べて、肺がんを発症するリスクが約10倍も高い傾向にあります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)が進行するとどうなる?
慢性閉塞性肺疾患(COPD)はその進行に伴って、日常の動作さえも困難です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、呼吸困難だけでなく、さらなる進行によって命を脅かす「呼吸不全」や「心不全」を引き起こす可能性があります。そのため、症状が初期段階であっても早めに対応し、適切な治療を受けることが重要。また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、全身性の炎症を引き起こすことで、心臓、血管の疾患、骨の健康を害する骨粗鬆症、「糖尿病」といった他の病気を併発するリスクが高まります。
慢性閉塞性肺疾患の原因

空気は鼻や口を通って気管を経由し、最終的には肺に達します。そのとき、肺胞(肺の中にある微細な部位)では、酸素が血液中に取り込まれ、二酸化炭素を血液中から肺胞へ排出する「ガス交換」が行われているのです。
しかし、タバコの煙など、有害物質が長い期間にわたって気道に影響を及ぼすと、細い気管支は炎症を起こします。これらの有害物質が肺胞まで影響すると、肺胞の壁は破壊。肺胞の拡張性も失われ、息をうまく吐き出せなくなることもあります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、肺の障害が原因で肺から空気がうまく排出されず、酸素不足、息切れを引き起こす疾患。さらに病気が進行すると、酸素の低下、二酸化炭素の増加が引き起こされる傾向です。
このような症状の背後には、主に肺胞と気道の炎症が関与。日本において、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の約90%以上を占める原因が、喫煙に起因すると言われています。タバコを吸わない人でも、受動喫煙の影響で慢性閉塞性肺疾患(COPD)のリスクが上がる傾向。また、胎児、新生児がタバコの煙の影響を受けると、肺の発達は阻害され、将来的に慢性閉塞性肺疾患のリスクが上昇することも明らかです。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の検査方法

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の確定診断には、肺の機能を詳細に調査する「スパイロメトリー」が中心。スパイロメトリーは、患者が一気に息を吐き出す際の気流を計測することで、肺の気流が閉塞している程度を評価する呼吸機能検査です。
また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診断だけでなく、その重症度、合併症、原因となる他の疾患があるかどうかなどを詳しく調べるために、様々な検査も併用されます。例えば、画像診断では「胸部X線」や「CT検査」を用いて、肺の構造的な変化と他疾患の有無を確認。「動脈血ガス分析」や「血中酸素濃度」の測定は、肺のガス交換機能を評価するために行われます。「血液検査」では、全身の炎症反応、心不全を示唆するマーカー、肺の疾患にかかわる他の指標などを検査。「心電図検査」は、慢性閉塞性肺疾患の合併症、原因となる心疾患の有無を確認するために実施します。
これらの検査を総合的に評価することで、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診断を確定し、疾患の状態、合併症、治療の方針などを詳しく判断することが可能に。そして、他の疾患、特に「喘息」、「気管支拡張症」、「うっ血性心不全」などとの違いを明確にすることで、適切な治療を選択するための大切な手がかりとなります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療
慢性閉塞性肺疾患(COPD)には様々な治療法があります。順に見ていきましょう。
禁煙
禁煙は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療において効果的な手段。タバコの煙に含まれる有害物質は肺を直接攻撃し、慢性的な炎症を引き起こします。また、長時間喫煙をしていると、肺の炎症、気道の閉塞が進行し、その結果、肺機能の低下を招いてしまうのです。
禁煙をすることで、症状の進行を遅らせ、さらには症状の改善も期待。実際に、喫煙を止めたことで、咳や痰の量が減少し、息切れも軽減される方が多く見られます。長期的に見ても、禁煙を継続することで、肺機能の低下がゆるやかになることが多くの研究で示されているのです。
しかし、禁煙は簡単なことではありません。多くの人が何度も挑戦しては失敗を繰り返しています。そのため、医師や看護師、薬剤師などの専門家のサポートを受けながら、少しずつ禁煙を続けていくことがおすすめ。禁煙外来、禁煙治療薬の利用も効果的な手段として考えられます。
薬物療法

薬物療法は、症状の重さや病状に応じて選択され、患者の「生活の質」を向上させることを目的としています。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療は一人ひとりにカスタマイズされ、患者の症状や病状、合併症の有無などを考慮して、最適な治療薬を選択。患者と医師が密にコミュニケーションを取りながら、治療計画を立てていきます。
- 1気管支拡張薬
- 「気管支拡張薬」は、気道の筋肉をリラックスさせ、狭まった気道を拡げるのに効果的。これにより、息切れや呼吸困難が軽減され、日常生活が楽になります。
- 2去痰薬
- 「去痰薬」(きょたんやく)は、痰の粘度を下げ、喀痰(かくたん:痰が出ること)をしやすくする効果が期待。これにより、気道の清潔を保つことができ、感染のリスクを減少させます。
- 3抗生物質
- 「抗生物質」は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の増悪(ぞうあく:症状が悪化すること)の原因となる感染症の治療に使用。特に、気道に細菌が感染して炎症を引き起こす場合には、抗生物質の使用が必要となります。
- 4吸入ステロイド薬
- 「吸入ステロイド薬」は、気道の炎症を抑えるのに効果的です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)の増悪を繰り返す場合や、気道の炎症が強い場合には、この薬剤の使用が検討されます。ただし、長期間の使用には注意が必要であり、医師の指示に従い、定期的なフォローアップを受けることが大切です。
ワクチン
インフルエンザや肺炎は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者にとって、症状の増悪、合併症の原因となるため、これらの感染症を予防するワクチンの接種は非常に重要です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者がインフルエンザに感染すると、通常よりも重症化しやすく、その結果、入院や合併症のリスクが高まることが知られています。インフルエンザワクチンを受けることで、これらのリスクを大幅に減少させることが期待できるのです。
また、肺炎球菌は、肺炎の主な原因となる細菌のひとつ。慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の場合、肺炎にかかると病状が急激に悪化するリスクがあります。肺炎球菌ワクチンは、この細菌による肺炎を予防するためのワクチンであり、接種により慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の肺炎リスクが低減。慢性閉塞性肺疾患(COPD)の管理は、ワクチンの接種や薬の適切な使用だけでなく、禁煙、適切な運動、栄養の確保など、総合的なアプローチが必要とされます。
呼吸リハビリテーション
リハビリテーションの効果に関する研究は常に進められ、その有用性が多くの機関によって認識されています。特に、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者における効果は、国際的な研究やガイドラインによっても明確です。「米国呼吸循環リハビリテーション協会」のガイドラインでは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者へのリハビリテーションが強く推奨されており、これらの国際的な取り組みを受けて、日本でもリハビリテーションの重要性が認識され、関連する学会からもガイドラインが発表されています。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者は、日常生活での動きによる息切れを恐れ、運動や活動を控えがちです。しかし、長期的に活動を制限することは、筋肉の衰え、持久力の低下を招き、さらなる息切れの原因に。このような状態を「息切れの悪循環」と呼び、その予防がリハビリテーションの重要な目的です。リハビリテーションは、筋力を回復し、持久力を向上させることで、日常生活の動作を楽にし、息切れを減少させる効果が期待できます。
また、リハビリテーションによって、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の「生活の質」を向上することが実現。なお、リハビリテーションの取り組みは、患者一人ひとりの状態やニーズに合わせて、専門家に指導を受けて行われることが望ましいです。
在宅酸素療法
在宅酸素療法は、慢性的な低酸素血症(ていさんそけっしょう:体内にある酸素の量が少なくなってしまい、SPO2が低値を示している状態)を持つ呼吸不全の患者に対して、自宅で行われる長期的な治療法です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の入院日数を減らす効果があるだけでなく、運動能力の向上、日常生活での活動性の向上なども期待できます。
酸素供給の主な方法としては、酸素濃縮器を使用することが一般的です。外出時や歩行時には、携帯用の酸素ボンベを活用。そして、これらの酸素供給装置から、チューブや鼻カニュラ(鼻の下にあてがって酸素を供給するためのチューブ)を介して、酸素を直接吸入することができます。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)を予防するには

慢性閉塞性肺疾患(COPD)を予防するためには、まず、喫煙者は禁煙の重要性を理解し、積極的に禁煙を心掛けることが大切です。タバコの煙には200種類以上の有害物質が含まれているとされており、これらの物質によって肺へのダメージが継続的に与えられます。
禁煙を行うことで、肺機能の低下を予防し、咳や痰の症状も軽減。さらに、タバコの副流煙は、主流煙よりも多くの有害物質を含んでいると言われているため、喫煙する場合には、指定された場所でのみ喫煙し、非喫煙者はその煙を避けるように努力することが求められます。
また、日常生活において身体を動かす習慣を持つことが健康維持には欠かせません。適切な呼吸法を取り入れながらの運動は、深い呼吸ができるようになり、息苦しさを軽減する効果があります。特に、「口すぼめ呼吸」という呼吸法は息切れの緩和に有効。この方法は、鼻で息を吸い、ロウソクを消すように口をすぼめて時間をかけて息を吐き出すものです。これにより、肺にたまった古い空気を効率的に排出することができます。歩く際には、最初の2歩で鼻から息を吸い、次の4歩で口すぼめ呼吸をしながら息を吐き出すというリズムで歩きましょう。
介護保険の対象となる特定疾病のひとつ
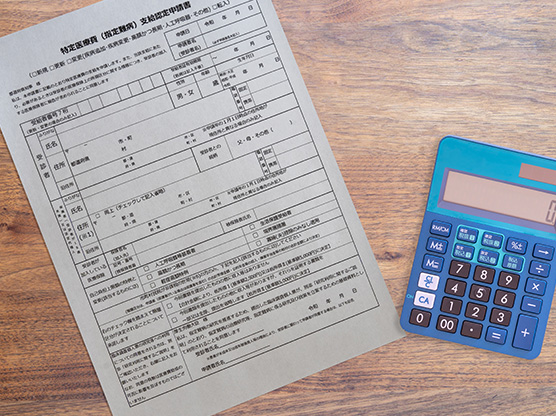
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、介護保険制度の対象となる特定疾病のひとつです。介護保険制度は、高齢者の健康や生活を支えるための制度として設けられています。
介護保険制度では、被保険者「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに分類。具体的には、第1号被保険者は65歳以上の高齢者を指し、第2号被保険者は40~64歳までの中高年層です。65歳以上の第1号被保険者になると、要介護や要支援の認定を受けることで、様々な介護サービスを利用することができるようになります。
一方で、第2号被保険者である40~64歳の間の方々は、介護が必要となったとしても、介護保険の適用を受けることはできません。ただし、例外として、介護保険制度が定める特定疾病を原因として要介護状態になった場合、この年齢層でも介護保険のサービスを受けることが可能です。
まとめ
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、主に喫煙などの刺激により肺胞や気管支が破壊され、空気の通り道である気道が徐々に狭くなったり、閉塞したりする病気です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)では、息切れ、慢性的な咳嗽(がいそう:咳)、痰の増加などの症状がゆるやかに進行します。そして、進行するにつれ、日常生活動作が制限されたり、急性増悪を繰り返したりするように。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は完治困難な進行性疾患ですが、禁煙や薬物治療によって進行を抑える対症療法が中心となっています。慢性閉塞性肺疾患(COPD)の症状を軽減するには、早期診断と生活指導が大切です。


