高額医療・高額介護合算療養費制度とは?申請方法やいくら戻るかの計算例を紹介
「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療保険サービス及び、介護保険サービスに関する年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)の支払い総額が一定額を超えた場合、その負担を軽減するための制度で、2008年(平成20年)4月から制度の運用が始まりました。高額医療・高額介護合算療養費制度がはじまったことで、それまでは夫婦とも75歳以上の高齢者でかつ住民税非課税世帯において、夫が医療保険サービス、妻が介護保険サービスを受けている場合、年間60万円払っていたものが半分程度の支払いで済むようになったのです。本記事では、高額介護合算療養費制度の解説、参考事例、申請の方法を解説します。
高額介護合算療養費制度とは
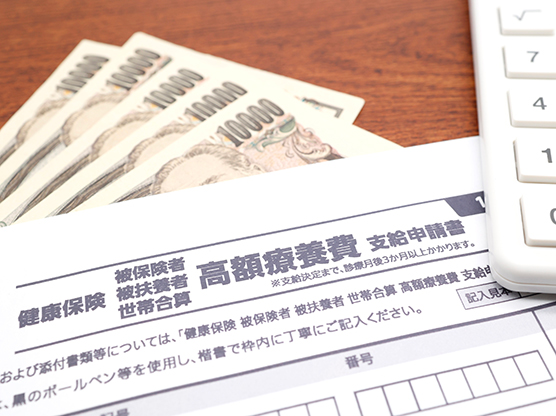
「高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯内で「医療保険」と「介護保険」の両方を使った場合に発生した費用のうち、一定の自己負担限度額を超えた部分がのちに返金される制度です。
具体的には、毎年8月1日~翌年7月31日までにかかった「医療費」と「介護(予防)サービス費」の自己負担総額を世帯内で合計し、それぞれの保険で定められた自己負担限度額を差し引いたのち、500円以上の超過分が発生した場合、その超過分を「高額医療・高額介護合算療養費」として申請することで還付。医療費にかかる部分は「高額介護合算療養費」、介護(予防)サービス費にかかる部分は「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。
特に、「後期高齢者医療制度」の対象である70歳以上の世帯に対しては、若い年齢層に比べて限度額をより低く設定。これにより、被保険者の経済的能力に合わせた給付が提供されることがこの制度の特徴です。
制度の対象者は?
制度の対象者
高額介護合算療養費制度の対象者は、以下の条件が当てはまる世帯となります。
- 国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
- 1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
制度の対象にならない負担額もある!
高額介護合算療養費制度は、基本的な医療費や介護サービス費をはじめとする自己負担額が軽減される制度ではありますが、下記のものは対象外です。
高額介護合算療養費
入院中の差額ベッド代、食事代、自由診療(美容整形等)
高額医療合算介護(予防)サービス費
限度額を超えたサービス利用、住宅改修費、特定福祉用具(ポータブルトイレなど)の購入費
高額介護合算療養費制度の限度額
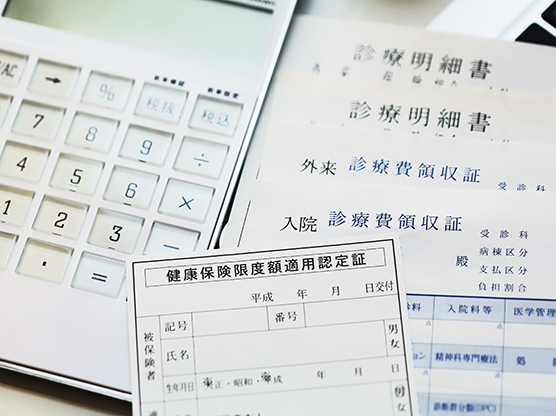
高額介護合算療養費制度の支給には、年齢・世帯及び収入ごとに年間自己負担限度額が設定されています。
特徴は、70歳を境に自己負担限度額が区分けされていることと、非課税世帯においては、70歳以上になると自己負担額が大きく変わってくることです。
| 自己負担限度額(年額) | ||
|---|---|---|
| 70歳以上 ※1 | 70歳未満 ※2 | |
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
| 年収770万~1,160万円 | 141万円 | 141万円 |
| 年収370万~770万円 | 67万円 | 67万円 |
| 年収156万~370万円 | 56万円 | 60万円 |
| 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |
※1 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合は、70~74歳の自己負担額を優先的に計算。上限に達していなければ、70歳未満の計算を行う。
※2 被保険者とその扶養家族のすべての収入から、必要経費、控除額を除いたあとの所得がない場合。
高額介護合算療養費制度の参考事例
ここでは、自己負担限度額をさらにイメージしやすくするために、参考事例を用いて計算例を示します。基本的な計算方法は、自己負担合算額-自己負担限度額となりますが、同一世帯内に様々な年代がいることで、計算が複雑になるのです。以下では、2つの例を交えて説明します。
例1)75歳以上の後期高齢者の夫と妻で構成された世帯の場合
- 世帯収入が年間200万円
- 夫77歳の年間自己負担額:医療50万円、介護保険利用なし
- 妻76歳の年間自己負担額:医療15万円、介護保険21万円
まず、世帯収入による負担限度額を確認します。世帯収入は年間合計200万円となりますので、負担上限限度額の年収は156~370万円の範囲に該当。よって、156~370万円の範囲における70歳以上での自己負担限度額は56万円となります。
では、支給額の計算を考えてみましょう。実質の年間医療費・介護サービス費の合計は、夫の医療費50万円+妻の医療費15万円+介護サービス費21万円=合計86万円となりますので、医療費・介護サービス費合算額86万円-自己負担上限額56万円=30万円が支給されるということになるのです。
例2)74歳未満の夫と妻+70歳未満の息子で構成された世帯の場合
- 世帯年収 360万
- 夫73歳の年間自己負担額:介護保険41万円
- 妻70歳の年間自己負担額:医療保険20万円
- 息子45歳の年間自己負担額:14万円
世帯年収は360万円ですので、70歳未満であれば60万円、70歳以上であれば56万円に。年間自己負担額は夫と妻を合わせると61万円になるため、医療・介護自己負担額61万円-70歳以上の自己負担上限額56万円=5万円が支給されるということになります。
また、45歳の年間自己負担額は14万円であり、両親である夫と妻の負担限度額を足すと70万円に。この70万円から、70歳未満の負担限度額60万円を引くと、10万円となります。よって、妻と夫の支給額と、息子の支給額を合わせると、この世帯に支給される高額介護合算療養費は年間で、15万円です。
高額介護合算療養費制度を利用する場合の申請
高額介護合算療養費制度を利用する場合の申請については、以下の順序で行われます。ただし、申請や支給の通知方法などはお住まいの場所によって違う場合もあるため詳しくは、各市区町村ホームページ、または、直接問合わせるなど確認が必要です。
- 1市区町村から介護被保険者への支給対象の通知が届く
-
介護保険制度の保険者である市区町村より、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象である旨の通知と申請書が送られてきます。
- 2市区町村へ支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書の提出
-
介護保険者への「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」の申請と、医療保険者に提出するための「自己負担額証明書」を交付してもらうための申請を行います。これらを提出することで、市区町村への申請は完了。次に必要な医療保険者への申請に必要な自己負担額証明書を受け取ることが可能です。
なお、計算期間中(毎年8月1日~翌年7月31日までのこと)に被保険者が加入する医療保険者、介護保険者に変更があった場合は、変更前のそれぞれの保険者に対して同様の申請を行う必要があります。
- 3医療保険者へ自己負担額証明書を提出
-
市区町村から取得した自己負担額証明書で、国民健康保険、被用者保険などの医療保険者へ申請を行います。
- 4医療保険者から市区町村へ支給額の連絡
-
医療保険者への申請が済んだら、市区町村と支給額等の情報が連携され「支給額計算・計算結果」が送付されてきます。なお計算期間の末日を含む1年の間に、医療保険者から計算結果が送られてこない場合は、申請が取り下げられたとされるため市区町村の窓口に確認しましょう。
- 5高額医療高額介護合算療養費が、市町村(介護保険者)と医療保険者それぞれから口座へ支給される
-
各保険者により支給決定されると、「支給決定通知」が対象者に届き現金支給及び、口座への金額振込が行われます。
まとめ
本記事では、高額介護合算療養費制度の解説、対象者、限度額を解説し、具体的な、支給費用の事例を紹介することで、具体的な支給額を算出しました。高額介護合算療養費制度は、医療保険、介護保険の双方で負担が発生し、1年間の合計が上限額を超えた場合に払い戻しが受けられる便利な制度です。申請先は、各市区町村の窓口になります。通知が届く前であっても分からないことがあれば、相談してみることがおすすめです。


