誤嚥をふせぐ薬の飲みかたは?誤嚥した場合の対処法も解説
錠剤や粉薬を服用するときに誤って気管に入って、むせた経験がある方も多いのではないでしょうか。こうした「誤嚥」(ごえん)は、飲み込みに問題がなくても起きることです。頻繁にむせる場合は、薬を飲むときの姿勢を見直したり、サポートグッズを使ったりすることで快適に薬を飲めるようになります。薬によっては、医師や薬剤師に相談して、飲みやすい物に変えてもらうことも可能です。近年注目されている「錠剤嚥下障害」(じょうざいえんげしょうがい)について説明し、飲みにくいときの工夫をお伝えします。
誤嚥を引き起こす錠剤嚥下障害とは
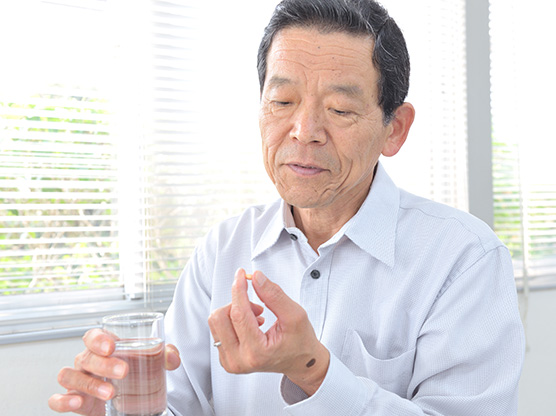
「錠剤嚥下障害」とは、錠剤をうまく飲み込めない状態のことです。嚥下障害(えんげしょうがい:食べ物や水分をうまく飲み込めない状態)の中でも、特に錠剤を飲み込むのが難しいという意味。
固形物である錠剤と、液体である水やぬるま湯を一緒に飲むのは、難しいことです。普段の食事やお茶は問題なく取れるけれど、錠剤を飲むのだけは苦手という方も少なくありません。錠剤をうまく飲み込めないことで、以下のような問題が起きています。
- 気管に水や薬が入ってしまう(誤嚥)
→むせる原因。ひどいと窒息や肺炎の原因に - 薬が口や喉、食道に残ってしまう
→くっついた箇所で違和感が起きたり、ただれたりする。
薬は腸まで運ばれないと吸収されないため、効果が遅れたり出なかったりする - 薬を飲むことに抵抗感が生まれる
→飲むのが怖くなったり、自己判断で薬を止めてしまったりすると治療に障る
錠剤嚥下障害が起こる原因
錠剤が飲み込みにくくなる原因 は、①加齢、②病気、③薬の副作用、④心理的な原因の大きく4つがあります。
- 1加齢
-
加齢によって舌や喉の筋肉が弱くなると、喉の奥へ薬を送り込みにくい、飲み込む際に、食道の入り口が十分に開かない、などのトラブルの発生が懸念されます。
- 2病気
-
脳卒中や認知症、パーキンソン病、がんなど。舌や喉の筋肉が動かしにくい、喉や食道が狭くなる、喉や消化管の手術などが飲み込みに影響する可能性があります。
- 3薬の副作用
-
持病の薬が口を乾燥させる、口の筋肉の働きが悪化する、などが原因となり飲み込みが難しくなります。
- 4心理的な原因
-
飲み込めなかったり、むせたりした記憶から、怖くて錠剤を飲めなくなることがあります。
誤嚥をふせぐための薬の飲み方
錠剤が飲み込みにくいとき、水を多めに飲む、数回に分けて飲むといった簡単な対策で解決すれば良いですが、工夫をしても、錠剤嚥下障害が高度になるほど危険も増えます。こういった場合に自己判断で錠剤を砕くことはおすすめしません。医師や薬剤師に相談して、飲みやすい薬への変更を依頼しましょう。以下に挙げる5つのポイントを押さえて、対策することが大切です。
姿勢を改善する
薬を飲む際、上を向く方が多いでしょう。錠剤が重力に引っ張られて喉の奥へ向かうため、飲みやすいと感じる一方で、上を向くと口や舌の筋肉が緊張し、喉の動きも制限されるため、飲み込みにくい面があるのです。薬を飲むときの正しい姿勢は、正面を向き、あごをやや引いて服用。こうすると筋肉は薬を飲み込むために自然に動きます。
椅子にまっすぐに座り、足を床に着けて安定した姿勢で飲むと安全。錠剤が喉の奥へ進みづらい場合は、リクライニングする椅子やベッドを利用し、上体を45度ほど傾けると、重力の力を借りやすくなります。あごを引いたり枕を入れたりして、首がのけぞらないように 気を付けましょう。
紙コップの一部をカットする
あごを引いて飲もうとすると、コップのふちが鼻に当たってうまく飲めないことも。紙コップを用意して邪魔な部分を切り取りましょう。鼻に当たらず飲みやすくなります。
ゼリーやオブラートに包む
滑りの良い物で錠剤を包むと、まとめて飲み込むことができます。飲み込みにくい場合に試してみましょう。
ゼリーの使い方
服薬補助ゼリーは、薬の効果に影響がないよう工夫された製品です。スプーンに適量を出したら、薬を埋め込んで包み、ゼリーごと飲み込みましょう。
オブラートの使い方
オブラートは、シート状やコップ状、カップ型などが市販されています。深めの小皿などに水を準備して、薬を包んだオブラート全体を素早くひたし、そのまま小皿に口を付けて飲んでみましょう。表面が、なめらかになって飲みやすくなります。
とろみ剤を用いる
とろみ剤を用いてとろみを付けると、飲み込みやすくなります。とろみがあることで、飲み込みの速度が遅くなり、喉の筋肉が飲み込む動作に適切に反応し、誤嚥のリスクが低減するためです。
飲みやすい薬に変更する
錠剤は自分で砕かない
飲みにくいからといって、錠剤を砕くことはおすすめできません。じわじわ溶け出して効果を持続させたり、腸まで運ばれてから溶けるように錠剤が作られたりしている場合があり、砕くと効果が変わります。飲みやすい形状の薬に変更できないか、薬剤師に相談することをおすすめします。
錠剤の大きさを薬剤師に相談して調整してもらう
同じ成分の薬でも、メーカーによって大きさが異なるのはよくあること。大きい錠剤を小さい物へ変更すると、飲みやすくなる可能性もあるのです。2つの成分が1錠に入っている薬を別々にすると、1錠ずつが小粒になる場合もあります。
錠剤以外の形状を希望する
薬によっては、錠剤以外の形状も選択肢です。粉薬、液剤、ゼリー剤、貼り薬など。ラムネのように溶ける「OD錠」も普及しています。薬剤師に、今より飲みやすい形状があるのかどうか、薬剤費がどう変わるかなど、詳しい相談をしましょう。最終的には、薬剤師から医師へ希望を伝え、医師の判断で薬の指示を変えてもらいます。
薬を誤嚥してしまったら医療機関を受診しよう
薬が気管に入り、呼吸が苦しいといった緊急事態が発生した場合は、ためらわず救急車を呼びましょう。また、頭をなるべく低くしてかがみ、強く吐き出すと、重力に引っ張られて薬が出てきやすいでしょう。自力で受診できる状態ならば、かかりつけ医か、喉を専門的に診てくれる耳鼻咽喉科がおすすめ。
自分で症状を判断するのは難しいので、悩みすぎずかかりつけ医を受診して、判断を仰ぐと安心です。繰り返しむせる場合は、以下のような専門の医療機関を受診して、検査やリハビリテーションを受けてみましょう。飲み込みの訓練は、言語聴覚士が専門。病院のリハビリテーション部門に所属する場合や、訪問リハビリテーションで自宅まで来てもらえる場合もあります。
まとめ
錠剤を飲み込むのは、健康な方でも意外と難しいもの。飲みにくいと思ったら、薬を飲むときの姿勢を見直したり、服薬補助ゼリーやオブラートなどを使ったりして飲みやすくするような対策がおすすめです。
またかかりつけ医やかかりつけ薬剤師に相談して飲みやすい形状に変更してもらうことも良いでしょう。それでも難しい場合は、飲み込みの検査ができる医療機関や、介護施設を検討することも重要です。必要な薬とは安全に付き合いたいもの。専門家の力を借りつつ服用しやすい方法を探すことをおすすめします。


