訪問リハビリテーションとは?内容や人員基準、介護保険適用料金を解説
「訪問リハビリテーション」とは、リハビリテーションの専門スタッフが利用者の自宅を訪問して、在宅にてリハビリテーションを行うことを指します。寝たきり状態の方、体力の低下により通院ができない方、日常生活に対して不安な方が対象です。訪問リハビリテーションについて、細かく解説していきます。
訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションとは、専門スタッフが自宅を訪問し、高齢者や要介護者が可能な限り、自宅にて自立した生活を送れるようにリハビリテーションを実施。
専門スタッフは、病院、診療所、介護老人保健施設(訪問リハビリテーション事業所)、訪問看護ステーションなどに勤務する「理学療法士」、「作業療法士」、「言語聴覚士」が担当します。
病気、ケガによる筋力低下や加齢による活動量の低下によって、日常生活を送る上で介助が必要な方の自宅へ訪問します。実際に生活現場でリハビリテーションが行えるため、それぞれの方に最適なものが提供されるのです。
また、利用者へのサポートだけではなく、介護を行う家族への心理的なサポート、介助の指導なども実施。ケアマネジャー、看護師、介護職員などと連携を取りながら専門性を発揮します。
なお、医療保険制度を利用してのリハビリテーションは疾患によって異なりますが、発症してから原則90~180日までと定められており、日数を過ぎると継続できません。しかし、介護保険制度を利用したリハビリテーションであれば日数に制限なく行えるため、リハビリテーションを継続したい方におすすめです。また、施設や病院への通院が難しい場合や、退院後、 退所後の生活に心配事がある方にも適したサービスだと言えます。
施設でのリハビリテーションとは異なり、利用者が自分の家でリラックスした状態で実施可能。訪問リハビリテーションの事業所数は、2022年(令和4年)で 5,214件、介護保険の受給者数は約136,000人であり、毎年増加傾向にあるのです。
訪問リハビリテーションの対象者
訪問リハビリテーションの対象者となる方は、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
要介護認定を受けた方

様々な病気やケガが原因で要介護状態になっており、65歳以上の「要介護認定」(要介護1~5)を受けている方が対象。
また、要支援1、2の介護予防対象者も「介護予防訪問リハビリテーション」の対象であり、要介護1~5の方と同様の訪問リハビリテーションが受けられます。
なお、40~65歳未満の介護保険制度における第2号被保険者は、「特定疾病」によって要介護になった場合のみ利用可能。この特定疾病には、以下の疾患が該当します。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
主治医からリハビリテーションが必要と認められている方
訪問リハビリテーションは、要介護と認定されるだけでなく、主治医からリハビリテーションが必要と判断された場合に利用可能。例えば、以下のような状態や症状がある場合に適応となります。
- 両上下肢、体幹の筋力が低下して歩行が困難
- 体が思ったように動かない
- 手の動く機能の低下
- 身体に麻痺や拘縮がある
- 食べ物を上手く飲みこめない
- 言葉がはっきり出ず、会話が上手くできない
訪問リハビリテーションのサービス内容
訪問リハビリテーションで行われるサービス内容は、以下の通りです。
健康状態・病状の観察
脈拍、血圧、体温、呼吸などのバイタルサイン、病状の観察と助言を実施。利用者と介護者の健康状態を確認し、再発予防と予後の予測を行います。変化があった場合には、主治医や看護師、ケアマネジャーに情報を共有して対応されるのです。
機能訓練

関節拘縮を防いだり、身体の関節の可動域(関節が動く範囲)を改善したりする目的で関節可動域練習を実施。
また、全身の筋力低下の進行予防、筋力強化を目的とした筋力トレーニングや、バランス機能の維持・改善を目的にバランス訓練も行います。
痛みがある場合には痛みのレベルを評価し、痛みを軽減するためのリハビリテーションを施行。さらに、摂食嚥下機能(飲みこみの能力)、コミュニケーション機能を評価して改善を図ります。
利用者が持つ機能を評価してから機能訓練を実施するため、個別性に優れたリハビリテーションを受けることが可能です。
日常生活動作の訓練
起き上がり、立ち上がり、歩行、排泄、食事、発声などの日常生活動作の訓練をします。実際に日常生活で困っていることを聴取し、生活場面でのリハビリテーションが可能。例えば、ベッドからの起き上がりや立ち上がり訓練、自宅内での杖を使っての歩行訓練、トイレ内でのトイレ動作訓練などが行われます。
マッサージ
訪問リハビリテーションでは麻痺症状、むくみなどの症状がある方に対して、血行改善を目的にマッサージを実施。麻痺があることで血行不良になっている場合には、専門スタッフがマッサージを実施することで、動きやすい体へ改善が期待できます。
住宅改修のアドバイス、福祉用具の選定
日常生活動作の訓練をした際に、身体機能の改善だけでは動作が楽にならない場合や、生活する上で障害になっている場合には、住宅改修(介護リフォーム)や福祉用具の利用について、訪問リハビリテーションではアドバイスを実施。例えば、ベッドからの立ち上がりを大変に感じている方、自宅内での歩行での移動を大変に感じている方に対して、廊下や部屋の中に手すりの設置をアドバイスします。
なお、住宅改修や福祉用具の手続きには、ケアマネジャーに依頼する必要があるので、必要な改修や福祉用具については情報共有が行われるのです。
介護方法の指導・相談
介護者が自宅内で介護をする際に困っていることを聴取して、介護方法の指導及び相談に乗ることも可能。介護をしている場面を実際に見せてもらい、専門家の立場から最適なアドバイスを行います。
訪問リハビリテーションの費用
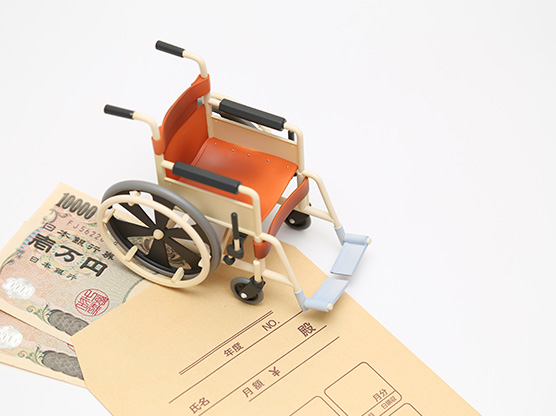
介護認定を受けている方の訪問リハビリテーションは、介護保険制度を適用。65歳未満の方、65歳以上で介護認定を受けていない方は、医療保険を適用します。なお、介護保険と医療保険の併用は原則としてできません。
また、訪問リハビリテーションは1回20~60分、週に1~2回利用する場合が多く、自己負担額は原則1割。一定以上の所得がある場合には、2~3割が自己負担です。
なお、自己負担1割の場合において、要介護1~5の方と要支援1・2の方の費用は、下記の通りになります。
| 訪問リハビリ(要介護1~5)の費用(1割負担の場合) | ||
|---|---|---|
| 費用・内容 | 自己負担 | |
| 基本料金 | 292円/ 1回(20分) |
|
| 加算 | リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーション計画を作成し、定期的な見直しをした場合 |
230円~/ 月(見直しの内容によって変動) |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所または介護保険初認定3ヵ月以内に、週2回以上、訪問リハビリを実施 |
200円/ 1日あたり |
|
| サービス提供体制強化加算 3年以上の経験があるリハビリ専門職が、1名以上いる場合 |
6円/ 1回20分あたり |
|
| 移行支援加算 サービス提供を終了した利用者に、その後の社会参加などに関する条件を満たす場合 |
17円/日 | |
| 介護予防訪問リハビリ(要支援1・2)の費用(1割負担の場合) | ||
|---|---|---|
| 費用・内容 | 自己負担 | |
| 基本料金 | 292円/ 1回(20分) |
|
| 加算 | リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーション計画を作成し、定期的な見直しをした場合 |
230円/月 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 退院・退所または介護保険初認定3ヵ月以内に、週2回以上、訪問リハビリを実施 |
200円/ 1日あたり |
|
| サービス提供体制強化加算 3年以上の経験があるリハビリ専門職が、1名以上いる場合 |
6円/ 1回20分あたり |
|
| 事業所評価加算 リハビリマネジメント加算を算定、評価対象期間に利用実人員数が10名以上、要支援状態区分の維持・改善数割合、リハビリテーションマネジャー加算算定者数割合を満たす場合 |
120円/月 | |
介護保険制度によるサービスは単位数で決められており、訪問リハビリテーションを利用する際の費用は、単位に対して地域区分で決められた金額をかけて計算。そのため、地域によって自己負担額が異なるので、実際に利用する際には費用を事前に確認する必要があります。
訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションとの違い
訪問リハビリテーションと「通所リハビリテーション」(デイケア)との大きな違いは、自宅でリハビリテーションをするか、施設に通所して個別または集団でリハビリテーションを行うかです。それぞれのメリット、デメリットは、以下の通りになります。
| 訪問リハビリと通所リハビリのメリット・デメリット | ||
|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション | 通所リハビリテーション | |
| メリ ット |
|
|
| デメリット |
|
|
訪問リハビリテーションのメリット
- 1自分に合ったリハビリテーションが可能
- 専門スタッフが利用者の身体機能や日常生活動作を評価して、ひとりひとりに合ったリハビリテーションが受けられるのです。実現したい目標を設定し、リハビリテーションに対して積極的に取り組むことが可能となります。
- 2住み慣れた自宅でリラックスした状態でのリハビリテーションが可能
- 周りの目が気になってしまう方も、住み慣れた自宅でリラックスした状態でのリハビリテーションが可能。通所が難しい方、集中しにくい方におすすめです。
- 3通院・通所しなくても良い
- 専門スタッフが自宅を訪問するため、利用者が通院・通所する必要がありません。通院が困難な方も利用しやすく、通院する時間、交通費などの手間がかからない点もメリットです。
訪問リハビリテーションのデメリット
- 1大型の機器などを使えない
- 自宅でリハビリテーションを行うため、病院・施設で使用する大型の機器などが利用できません。そのため、機器を使用して、本格的なリハビリテーションをしたい方には向いていないのです。
- 2緊急時の対応に不安がある
- 自宅内でリハビリテーションをするため、緊急時の対応に不安を感じる方もいるかもしれません。また、医療対応が遅れてしまう可能性もあります。
- 3他の利用者とのコミュニケーションは取れない
- 自宅を訪問する専門スタッフとのコミュニケーションは取れますが、他の利用者とのコミュニケーションを取る機会は皆無。リハビリテーションに対して消極的だったり、他の利用者とコミュニケーションを取ったりしたいと思っている方には向いていません。
通所リハビリテーションのメリット
- 1専用の機器などがあり、設備が整っている
- 施設でのリハビリテーションになるため、機器が充実している場合が多く、機器を利用しての筋力強化訓練が可能。より大掛かりな機能訓練をしたい方には、通所リハビリテーションがおすすめです。
- 2食事や入浴などの他の介護サービスを受けられる
- 通所リハビリテーションの施設では、看護師や介護スタッフもいるので、食事や入浴などの他の介護サービスを利用できます。自宅での入浴が困難で、かつリハビリテーションを受けたい方には大きなメリットです。
- 3他の利用者とのコミュニケーションが取れる
- 多くの利用者が来所しており、交流を図ることもできます。外出機会が減っていて、他者とのコミュニケーションを取りたいと思っている方には最適です。
- 4送迎がある
- 施設まで送迎があるため、家族が送迎する必要はありません。そのため通院が困難な方でも、リハビリテーションが受けやすくなっています。
通所リハビリテーションのデメリット
- 1利用時間が長く、利用者への身体への負担が大きい
- 利用時間は施設によって異なりますが、時間が長くなることで身体への負担が大きくなる可能性が存在。短時間の通所リハビリテーションでも、最低1~2時間の利用時間になるので、送迎時間を合わせると訪問リハビリテーションよりも時間が長くなる場合が多いのです。そのため、体力が落ちている方にとっては、通所することが負担になる場合もあります。
- 2個別の時間が施設によって異なる
- 施設における個別リハビリテーションの時間は、訪問リハビリテーションと異なり時間が定められていません。そのため、個別リハビリテーションは10~20分間などまちまち。個々に合わせた機能評価は行われますが、リハビリテーションの時間が少なく、物足りなく感じる方もいるかもしれません。
- 3日常生活に即したリハビリテーションをできない
- 日常生活で困っていることに関して聴取が行われます。しかし、訪問リハビリテーションで行われるような、生活場面でのリハビリテーションをすることはできません。
訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションは併用可能
訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションには、それぞれメリットとデメリットがあるため、どちらにしたら良いか迷う場合も多いでしょう。どちらの介護サービスも併用可能なので、決められない方は両方を利用するのがおすすめ。訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの介護サービスを提供している事業所では、同じ専門スタッフがリハビリテーションを実施してくれる場合もあります。
自分のペースで進めたい人には訪問リハビリテーションがおすすめ
訪問リハビリテーションは、個別の対応をしてくれるため、自分のペースで進めたい人に最適。通所リハビリテーションでは、集団でリハビリテーションをすることもあるため、自分に合ったペースで受けるのは難しい場合もあります。リラックスした状態で、自分に合ったリハビリテーションを受けたいならば、訪問リハビリテーションを選択しましょう。
訪問リハビリテーションを利用する手順
介護保険制度を利用して、訪問リハビリテーションを開始する場合には、まずはケアマネジャーに相談する必要があります。利用する際の手順は以下の通りです。
- 1担当のケアマネジャーに相談
- まずは、担当のケアマネジャーに訪問リハビリテーションを利用したい旨を伝えます。その後、希望するリハビリテーションの内容により、希望に合った介護事業者をケアマネジャーが複数選定。利用者へ紹介されるのです。
- 2事業者の決定、主治医へ指示書の作成依頼
- ケアマネジャーに紹介してもらった介護事業者から、自分に合った介護事業者を決定。主治医に訪問リハビリテーションが必要であるとの「指示書」を依頼します。指示書は、介護保険制度において3ヵ月に1回、医療保険制度では1ヵ月に1回の発行が必要。利用者自身で主治医まで依頼することも可能ですが、ケアマネジャーが代行することもできます。
- 3ケアプランの作成
- ケアマネジャーが、訪問リハビリテーションのサービスを記載した「ケアプラン」(介護サービス計画書)を作成。作成してもらったケアプランの内容を確認し、問題がなければ同意して、介護事業者と契約に進みます。
- 4介護事業者と契約・利用開始
- 介護事業者と契約を行い、訪問リハビリテーションの利用を開始。なお、訪問リハビリテーションのスタッフは、ケアプランに基づいて「リハビリテーション実施計画書」を作成し、利用者から同意を得る必要があります。
- 5リハビリテーション実施計画書の見直し・修正
- リハビリテーション実施計画書は、初回はおおむね2週間以内、そのあとは3ヵ月ごとに見直しを実施。課題やリハビリテーション目標を修正して、利用者の状態に応じた目標を再設定します。
訪問リハビリテーションを行う介護事業者を選ぶ際のポイント
訪問リハビリテーションを行っている介護事業者の数は多く、自分の希望に合った介護事業者を探すのは大変。最適な介護事業者を選ぶポイントを紹介します。
必要なリハビリテーションが実施できるか
まずは、自分が行いたいリハビリテーションを実施できるかどうかを確認。理学療法士、作業療法士が在籍している介護事業者はたくさんありますが、言語の訓練などを行う言語聴覚士が在籍している介護事業者は少ないのです。そのため、言語聴覚士のリハビリテーションを受けたい場合は、言語聴覚士が在籍しているかどうかを事前に確認する必要があります。
希望にあった日程で利用できるか
利用したい曜日、時間帯に空きがあるかどうかも確認。例えば、通所リハビリテーションと併用している場合には、通所リハビリテーションへ行っていない日に訪問リハビリテーションを利用したいことを伝える必要があります。また、土日に利用したい場合には、土日も営業している介護事業者かどうかも重要なチェックポイントです。
緊急時の対応方法
訪問リハビリテーション中に万が一、体調の変化があった場合に、どのような対応が行われるかは非常に重要。緊急時の対応がマニュアル化してあり、スタッフ間でも対応が統一されている介護事業者であれば、安心して利用できます。
在籍スタッフの経験は豊富かどうか
担当予定のスタッフの経験が豊富かどうかも確認しておくのがおすすめ。新人のスタッフでもきちんとリハビリテーションをしてくれる場合もありますが、経験が豊富であれば細かな所に気が付き、的確なアドバイスが期待できます。
認知症ケアを得意としているかどうか
認知症の方のリハビリテーションを依頼する際には、認知症ケアを得意としている専門スタッフが在籍しているかどうかも重要です。
福祉用具業者とのつながりがあるかどうか
家庭内で生活するには、福祉用具の選定が重要となることが多いため、福祉用具業者と連携がある介護事業者を選ぶのがおすすめ。連携していれば、利用者の状態に応じた福祉用具のレンタル・購入の話をする際にスムーズに進みます。
担当者が休む場合の対応はどのようになるか
担当スタッフの都合によって、予定の日にリハビリテーションができない場合が存在。そのため、担当スタッフが休みの場合における対応もチェックポイントです。代理のスタッフが来てくれるのか、日程や時間が変更となるのかなど、事前に聞いておくと利用後の心配が少なくなります。
訪問リハビリテーション終了後の案内はあるか
リハビリテーションを実施することで、機能が回復したあとにその後のサービスについて案内してくれるかどうかも、チェックしておくのがおすすめ。例えば、機能を維持するためにデイサービスを案内してくれたり、他の介護サービスを案内してくれたりする介護事業者を選んでおくと安心して利用できます。
訪問リハビリテーションにおける専門スタッフ
介護事業者が、訪問リハビリテーションを提供するために必要な人員基準として、専任の常勤医師1名以上(医療機関との兼務可)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士においては一定数が在籍していなければなりません。なお、2019年(令和元年)度における常勤換算数は、理学療法士2.91人、作業療法士1.18人、言語聴覚士0.37人となっています。
常勤換算数でも分かるように、理学療法士、作業療法士と比較して、言語聴覚士が配置されていない介護事業者が多いのです。そのため、嚥下障害の訓練、失語症に対してリハビリテーションを行いたい場合、介護事業者を探すのが難しい点に注意が必要。ここでは、各専門スタッフについて解説していきます。
理学療法士

理学療法士は病気、ケガなどで身体に障害がある方に対して、「基本動作能力」の改善、維持、障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法を実施します。基本動作能力とは、寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩くなどの動作のことです。
具体的には、関節の可動範囲を改善するための関節可動域訓練、筋力を増強させる筋力強化訓練、脳血管障害後の麻痺の回復、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける手法を用いてリハビリを実施。また、動作練習や歩行練習を行って能力の向上を図り、日常生活の自立を目指していきます。
作業療法士
作業療法士は、病気やケガなどで身体に障害がある方に対して、実際の生活動作に則した「作業訓練」を通じて、日常生活へ復帰させる専門スタッフです。具体的には、下記の作業訓練が行われます。
- 自力による食事
- 自宅内での移動
- 自力での排泄
- 自力による服や靴の着脱
- 自力による調理や掃除
- 1人での買い物
言語聴覚士
言語聴覚士は話す、聞く、食べることなどコミュニケーションに関するリハビリテーションを行う専門スタッフです。言語障害(失語症、構音障害、高次脳機能障害)、聴覚障害、言葉の発達の遅れ、声や発音の障害などについて検査・評価し、改善訓練、指導及び助言を実施。具体的には、飲みこみが上手くいかない方に対して反射を高める訓練、言葉が出にくい方には、発声の訓練をしていきます。
まとめ
訪問リハビリテーションでは、専門スタッフが利用者の自宅を訪問して、在宅でひとりひとりに合ったリハビリテーションを提供。訪問リハビリテーションの最大のメリットは、居宅介護における困りごとを相談して、実際の生活場面にてリハビリテーションが受けられることです。
また、利用者だけではなく、介護を行う家族へのサポートも行います。訪問リハビリテーションは、最適な個別リハビリテーションを受けたい方におすすめの介護保険サービスなのです。


