健康型(自立型)有料老人ホームの費用を解説|目安・内訳
健康型(自立型)有料老人ホームは、食事、掃除、洗濯などのサービスを受けられる高齢者施設です。プライバシーも確保されており、イベント、レクリエーションなどのサービスも充実しています。しかし施設が充実している分、費用は「住宅型有料老人ホーム」より高額になる場合が多いのです。健康型(自立型)有料老人ホームの入居一時金、月額利用料など費用に関する内容を詳しく解説します。
健康型有料老人ホームにかかる費用相場

健康型有料老人ホームの費用は大きく分けて、外部サービスへ支払う費用と、施設へ支払う費用の2種類。施設費は、入所時に支払う「入居一時金」と、毎月支払う「月額利用料」で、外部サービス費は、医療費、介護サービス費、娯楽費などです。
健康型(自立型)有料老人ホームの特徴、サービス内容、入居条件、必要な費用の概要は以下の通りになります。
| 健康型(自立型)有料老人ホームの概要 | ||
|---|---|---|
| 特徴 | ・図書館、温泉、スポーツジムといった生活を豊かにする施設が充実していることが多い ・外部の医療機関との連携で健康管理サービスも提供 |
|
| サービス | ・介護を必要としない入浴、排泄、生活支援 ・食事提供 ・健康管理 ・安否確認(見守り) ・生活相談 ・緊急時対応 ・リハビリテーション ・レクリエーション |
|
| 入居条件 | ・60または65歳以上 ・基本的に自立しており、介護不要 |
|
| 費用 | 入居 一時金 |
0~数億円 |
| 月額 利用料 |
約10~40万円 | |
入居一時金
入居一時金とは、家賃の前払い分と敷金などの初期費用。敷金にあたる分は「初期償却」とされ、退去時の修繕費などに充てられます。家賃として充当される期間と金額は、施設や入居一時金として納める金額によって異なってくるため、一定ではありません。健康型有料老人ホームの入居一時金は、設備やサービスが充実している分、他の施設と比べて高額な場合が多いとされています。入居一時金がない施設もありますが、その分月額料金が高くなる可能性があるのです。
なお、家賃としての前払金は、施設側が定めた「償却期間」と「償却率」に応じて年々償却され、「未償却分」は施設の退去時に返還されますが、敷金に相当する初期償却は退去時の修繕費などに充てられるため、返還されません。
月額利用料
月額利用料とは、毎月支払う「生活費」です。月額利用料には居住費、食費、管理費の他に、理美容費、イベント参加費、買い物代行費などが含まれます。なお、健康型有料老人ホームにおける月額利用料の相場は、10~40万円と高齢者施設のなかでは高額。また、月額利用料には医療費、介護サービス費などは含まれせん。
退去時に入居一時金が返還金として戻ることも
入居一時金のうちの「家賃としての前払金」にあたる金額を、何ヵ月分の家賃としているかが償却期間です。退去時に償却期間が残っている場合、未償却分は返還金として手元に戻ってきます。仮に償却率30%、償却期間5年で入居一時金を600万円支払った場合、未償却期間中に返金される未償却分をシミュレーションしてみると、下記の通りになるのです。
| 未償却分のシミュレーション | ||
|---|---|---|
| 償却額 | 未償却額 (返金額) |
|
| 契約時 | 180万円 (初期償却) |
420万円 |
| 1年目 | 最大84万円 (7万円×12ヵ月) |
336万円 |
| 2年目 | 252万円 | |
| 3年目 | 168万円 | |
| 4年目 | 84万円 | |
| 5年目 | 0円 | |
シミュレーションでは、毎月7万円ずつ償却されています。つまり毎月家賃として7万円ずつ支払っているので、5年間は月額利用料内における家賃が0円の状態です。5年経たずに退去する場合、7万円を残りの月数でかけた金額が返還されます。
なお、シミュレーションにおける、償却額として記載の「最大84万円」とは、償却7万円の12ヵ月分という意味であり、1年間に何ヵ月入居していても償却額が84万円という訳ではありません。
また、返還金の計算式は以下の通りです。
入居一時金×(1-初期償却率)÷償却月数×(償却月数-入居月数)=返還金
仮に償却率30%、償却期間5年で入居一時金を600万円支払い、入居後1年半で退去する場合は、以下の金額が返還されます。
- 1年間の均等償却額:(600万円-180万円)÷5年=84万円
- 1ヵ月の均等償却額:84万円÷12ヵ月=7万円
- 3年半分の返却金:7万円×42ヵ月(残った月)=294万円
もちろん、償却期間が終了しても、家賃を追加で支払えば、施設に住み続けることも可能。償却期間は5~10年と施設によって様々であり、返還金がどれくらいになるのかは事前に確認しておきましょう。
入居後すぐに退去する場合は、クーリングオフが適用される
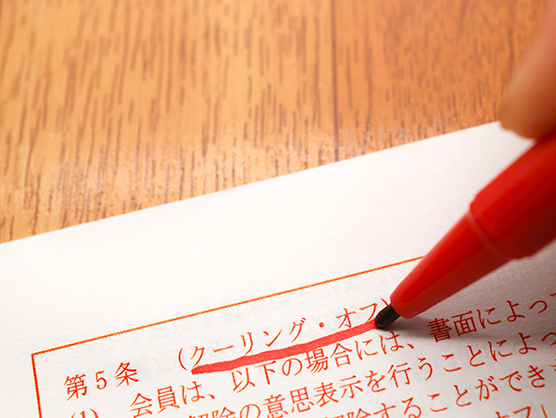
健康型有料老人ホームへ入居後、なんらかの理由により短期間で退去する場合、「クーリングオフ」が適用されます。老人ホームにおけるクーリングオフの正式名称は「短期解約特約」です。この制度により、入居しても90日以内であれば、契約を解除できます。
以下のようなケースがクーリングオフの対象になります。
- 施設の雰囲気が良くない
- 他の入居者様と馬が合わない
- 希望していたようなサービスが受けられない
- 施設のスタッフになじめない
- 転んで骨折し、介護が必要になった
- 体調悪化で急遽入院することになった
- 逝去
クーリングオフを利用すると、入居一時金として支払った金額のほとんどが返金されます。クーリングオフで返金される金額は、入居一時金から日割りの月額利用料を差し引いた金額です。90日以内に退去しなければクーリングオフが適用されなくなるので、退去することを決めた場合は、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
また、厚生労働省の調査によると、2022年(令和4年)6月30日時点で、老人福祉法の基準を満たさない無許可の有料老人ホームが、全国にある有料老人ホームの4.1%にあたる626件も存在することが分かりました。無許可の有料老人ホームは、年々減少傾向にはありますが、入居を検討している施設が、国の認可を受けているかどうかも確認しましょう。
入居施設が倒産した場合の保全措置
「保全措置」とは、万が一、入居施設が倒産しても未償却分の前払金を保障する制度です。2021年(令和3年)4月1日以降、施設が倒産した際に「500万円か未償却分[返還債務残高]のいずれか低い方」を保障されるように改正されました。
保全措置の改正以降は入居契約書、及び重要事項説明書、パンフレットなどに明確な記載が義務付けられており、入居者様本人や家族でしっかり確認することが重要。また、償却額の計算も単に入居一時金を償却期間の月数で割った金額ではなく、いつ退去しても返金されない初期償却があることも、理解しておく必要があります。
健康型有料老人ホームにおける月額利用料の内訳
月額利用料とは居住費、食費、管理費、その他費用のことです。個人で行う趣味費、医療費、外部介護サービスの利用費などは含みません。健康型有料老人ホームでは、居室設備や娯楽設備の充実度によって月額利用料が高額になる傾向があります。
居住費

居住費は、賃貸住宅で言うところの家賃、及び居室と設備の利用料に相当します。入居一時金で一定期間の家賃分全額または一部を納めている場合、居住費の負担の相場は、0~10万円程度です。しかし、入居一時金がない、居室にミニキッチン、及び浴室などが整備されている、居室が広い、設備が豪華、地代の高い都市部にあるなどの要因によって、相場より高額になるケースもあります。
食費
食費は、朝食、昼食、夕食と、1日3食施設から提供される食事にかかる費用で、相場は3~6万円。利用した回数に応じて毎月金額が変動します。また減塩食、きざみ食など、調理に一手間かかる特別食を希望した場合も、追加料金を請求されるケースが多いのです。ホテル並みに豪華な施設では食事にもこだわっており、食費が高額になる場合があります。イベント時の食事、おやつ代などを食費として計上するかどうかは施設ごとの判断により異なり、毎回一律ではありません。
管理費
施設の維持管理費、事務費、人件費などが管理費。施設によっては水道光熱費、電話代を含める場合があります。充実した施設では職員数も多く、施設が広いと施設の維持費も高くなるため、管理費が高額になる場合も。なお、管理費の相場は10~20万円前後になります。
その他費用
施設によって管理費として計上されたり、食費として計上されたりする場合もありますが、その他の費用としては、主に以下のような項目があります。
-
- 日用品費
- おむつ、紙パンツ、歯ブラシ、入れ歯洗浄剤、トイレットペーパー、居室用ティッシュペーパーなど
-
- レクリエーション参加費
- レクリエーションで使用する小物、おやつなど
-
- 理美容代
- 散髪代
-
- 水道光熱費:
- 管理費に組み込まれる場合も多い
-
- オプションサービス費
- 生活支援、見守り、緊急対応、買い物代行、通院時の付き添い
レクリエーションに参加したり、オプションサービスを利用したりしなければ、その他の費用は1万円前後になる場合が多いです。その他、ゴルフや釣りなどの趣味、習い事などをする場合には費用が発生します。基本的に、支払いはすべて得た収入の範囲内で行いますが、施設利用外の月額費用として発生することもあります。
外部の介護保険サービスにかかる費用

健康型有料老人ホームは、介護を必要としていないことが入居条件のため、施設側で介護サービスを用意していません。介護保険サービスを受ける場合、外部の介護サービス事業所を利用することになります。
この際、要支援・要介護認定がなければ、全額自己負担。また、要支援・要介護認定がある場合における、自己負担の割合は、単身世帯か2人以上の世帯かで異なります。
| 65歳以上で単身世帯の場合 | |
|---|---|
| 65歳以上で本人の合計所得金額が280万円未満の場合 | 1割負担 |
| 65歳以上で本人の合計所得金額が280万円以上340万円未満の場合 | 2割負担 |
| 65歳以上で本人の合計所得金額が340万円以上の場合 | 3割負担 |
| 65歳以上が2人以上の世帯の場合 | |
|---|---|
| 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円未満の場合 | 1割負担 |
| 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、生計をともにし、同じ住所に住む65歳以上の世帯所得が346万円未満 | 1割負担 |
| 1割負担者同様(同一世帯の65歳の160万円以上220万円未満)で、世帯所得の合計が346万円以上 | 2割負担 |
| 1割負担者かつ2割負担者の要件(220万円以上)を超える65歳以上の同一世帯者における合計の所得が346万円以上かつ463万円未満 | 2割負担 |
| 65歳以上の単身者における年間所得が220万円以上で、同一世帯所得が463万円以上 | 3割負担 |
さらに、健康型有料老人ホームで「訪問介護サービス」を利用する場合、要支援・要介護認定を受けたあとに、ケアマネジャーが作成したケアプランに含まれる介護保険サービスが対象となります。訪問介護サービスは、食事や排泄の介助などを行う「身体介護」、生活技能を高める機能訓練を中心とした「生活援助」、移動時の車両乗降、及び通院を介助する「通院等乗降介助」の3種類の利用が可能です。
| 身体介護を中心に介護保険サービスを受ける場合の自己負担額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 介護給付単位 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
||
| 1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
||
| 20分未満 | 167単位 | 167円 | 334円 | 501円 |
| 20分以上 30分未満 |
250単位 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 30分以上 1時間未満 |
396単位 | 396円 | 792円 | 1,188円 |
| 1時間以上 | 579単位 (30分追加ごとに +84単位) |
579円 | 1,158円 | 1,737円 |
| 生活支援を中心に介護保険サービスを受ける場合の自己負担額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 介護給付単位 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
||
| 1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
||
| 20分以上 45分未満 |
183単位 | 183円 | 366円 | 549円 |
| 45分以上 | 225単位 | 225円 | 450円 | 675円 |
介護給付1単位につき10円が基本。
身体機能の回復、維持、認知機能の向上などを目的に機能訓練を行う「デイケア」(通所リハビリテーション)も、健康型有料老人ホームから通うことができます。通常規模のデイケアを利用した際の自己負担額は、以下の通りです。
| デイケアにおける自己負担額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 要介 護度 |
介護給付費 単位 |
自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
||
| 1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
|||
| 1時間以上 2時間未満 |
1 | 366単位 | 366円 | 732円 | 1,098円 |
| 2 | 395単位 | 395円 | 790円 | 1,185円 | |
| 3 | 426単位 | 426円 | 852円 | 1,278円 | |
| 4 | 455単位 | 455円 | 910円 | 1,365円 | |
| 5 | 487単位 | 487円 | 974円 | 1,461円 | |
| 2時間以上 3時間未満 |
1 | 380単位 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
| 2 | 436単位 | 436円 | 872円 | 1,308円 | |
| 3 | 494単位 | 494円 | 988円 | 1,482円 | |
| 4 | 551単位 | 551円 | 1,102円 | 1,653円 | |
| 5 | 608単位 | 608円 | 1,216円 | 1,824円 | |
| 3時間以上 4時間未満 |
1 | 483単位 | 483円 | 966円 | 1,449円 |
| 2 | 561単位 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 | |
| 3 | 638単位 | 638円 | 1,276円 | 1,914円 | |
| 4 | 738単位 | 738円 | 1,476円 | 2,214円 | |
| 5 | 836単位 | 836円 | 1,672円 | 2,508円 | |
| 4時間以上 5時間未満 |
1 | 549単位 | 549円 | 1,098円 | 1,647円 |
| 2 | 637単位 | 637円 | 1,274円 | 1,911円 | |
| 3 | 725単位 | 725円 | 1,450円 | 2,175円 | |
| 4 | 838単位 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 | |
| 5 | 950単位 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | |
| 5時間以上 6時間未満 |
1 | 618単位 | 618円 | 1,236円 | 1,854円 |
| 2 | 733単位 | 733円 | 1,466円 | 2,199円 | |
| 3 | 846単位 | 846円 | 1,692円 | 2,538円 | |
| 4 | 980単位 | 980円 | 1,960円 | 2,940円 | |
| 5 | 1,112単位 | 1,112円 | 2,224円 | 3,336円 | |
| 6時間以上 7時間未満 |
1 | 710単位 | 710円 | 1,420円 | 2,130円 |
| 2 | 844単位 | 844円 | 1,688円 | 2,532円 | |
| 3 | 974単位 | 974円 | 1,948円 | 2,922円 | |
| 4 | 1,129単位 | 1,129円 | 2,258円 | 3,387円 | |
| 5 | 1,281単位 | 1,281円 | 2,562円 | 3,843円 | |
| 7時間以上 8時間未満 |
1 | 757単位 | 757円 | 1,514円 | 2,271円 |
| 2 | 897単位 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 | |
| 3 | 1,039単位 | 1,039円 | 2,078円 | 3,117円 | |
| 4 | 1,206単位 | 1,206円 | 2,412円 | 3,618円 | |
| 5 | 1,369単位 | 1,369円 | 2,738円 | 4,107円 | |
費用を抑えるなら郊外の健康型有料老人ホーム、サ高住
健康型有料老人ホームでは、居室内にトイレ、キッチンが備わっていることもあり、施設によっては温泉、図書館、理美容室、スポーツジム、プールなど設備が充実。しかしその反面、全体的な費用が高額になりやすいのが欠点です。そこで費用を少しでも抑えたい場合は、郊外の健康型有料老人ホームの選択、あるいは「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)を検討してみましょう。
郊外の健康型有料老人ホーム
健康型有料老人ホームが高額になるのは、ホテル並みに設備が充実しているからだけではありません。もうひとつの理由として土地代があります。そのため、同じ広さの居室であっても、都市部よりも郊外の施設の方が良心的な価格になるケースが多いのです。しかし、住み慣れた土地を離れ、郊外にて新しい生活を始めてみると、不安やストレスから体調を崩す場合もあります。費用だけで決めずに実際に施設に行って確かめ、十分に検討しましょう。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
健康型有料老人ホームと同じような施設に、サービス付き高齢者向け住宅があります。サ高住には一般型と介護型があり、一般型サ高住は、介護が必要ない60歳以上の高齢者向け施設という点で、健康型有料老人ホームとほぼ同じです。賃貸契約のため食事、掃除、洗濯などのサポートは外部サービスを利用します。
一般型のサ高住は、介護度が上がると住み続けられませんが、要介護レベルが軽度の場合は、外部の介護サービスを受けられる点も健康型有料老人ホームと同じです。介護型は自立~要介護度5までの60歳以上の方、または60歳未満でも要介護認定を受けている方が対象であり、要介護レベルが上がっても住み続けられます。
また、2020年(令和2年)の時点では、健康型有料老人ホームが全国に約20施設に対し、サ高住は7,660施設と約380倍も多いのも魅力。サ高住は費用もかなり安く抑えられる上に選択できる施設も多いため、健康型有料老人ホームに比べると入居までの時間がかかりません。選択肢のひとつとして検討することをおすすめします。
自分にあった健康型有料老人ホームを見付けること
寿命には「平均寿命」と「健康寿命」の2種類があります。健康寿命とは「健康上の理由で日常生活が制限されることなく生活できる期間」です。2019年(令和元年)の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳なのに対し、健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳となっています。重要なのは健康寿命を長くして、介護が必要な期間をできるだけ短くすること。健康型有料老人ホームでは、日々の生活を楽しんで過ごせる工夫が多く、まさに健康寿命を延ばす環境と言えます。健康型有料老人ホームを選ぶ際のポイントとして、自分自身の体力や日々の暮らし方、経済的な課題などを総合的に検討することが重要です。


