介護難民とは?現状や原因、解決策について解説
介護難民とは、介護を必要とする状態であるにもかかわらず、介護サービスを受けられない状況にある人のことです。ひとりで暮らす高齢者の増加、介護士不足などが原因で、今後増えていくと予想されています。介護難民が増えている原因と、介護難民にならないための対策等について見ていきましょう。
介護難民とは

介護難民とは、介護を必要とする状態であるにもかかわらず、自宅でも施設でも介護サービスを受けられない状況にある人のことです。
介護難民の具体的な数値は公表されておらず、正確な人数を知ることはできません。しかし、厚生労働省のデータによると、要介護認定を受けている方も介護サービス(介護予防サービスを含む)を受けている方(表上では受給者数)も、年々増えていることが分かります。
| 要介護認定者数 | |
|---|---|
| 要介護 (要支援) 認定者数 |
|
| 2019年(平成31年)3月末 | 658万人 |
| 2020年(令和2年) 3月末 |
669万人 |
引用:令和元年度介護保険事業状況報告(年報)のポイント、厚生労働省
| 受給者数の年次推移 | ||
|---|---|---|
| 年間累計 受給者数※1 |
年間 実受給者数※2 |
|
| 2018年 (平成30年度) |
約6,071万人 | 約597万人 |
| 2019年 (令和元年度) |
約6,204万人 | 約611万人 |
| 2020年 (令和2年度) |
約6,316万人 | 約622万人 |
| 2021年 (令和3年度) |
約6,483万人 | 約638万人 |
※1:5月から翌年4月の各審査月の介護予防サービスまたは介護サービス受給者数の合計
※2:4月から翌年3月の1年間において、一度でも介護予防サービスまたは介護サービスを受給したことのある者の数で、同じ方が2回以上受給した場合はひとりとして計上
引用:令和3年度介護給付費等実態統計の概況、厚生労働省
2020年(令和2年)度から2021年(令和3年)度だけを見ても、1年間で累計受給者数は167万人、実受給者数は16万人増加。介護を必要とする人が増えるペースが速いので、介護難民が増える可能性が高いと予想できます。また、実際に特別養護老人ホームに入所を希望していても、入所できない方は約27.5万人です。
| 特別養護老人ホームの入所申込者の状況 | |
|---|---|
| 介護度 | 待機人数 |
| 要介護3以上 | 25.3万人 |
| 要介護1・2の 特例入所対象者 |
2.2万人 |
※2022年(令和4年)4月時点
引用:特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)、厚生労働省
これらのすべての方が介護難民になるわけではありませんが、介護を必要としている人の数に対して、介護制度が十分でない現状が分かります。
都市部で深刻化
日本創成会議が2015年(平成27年)6月に発表した「東京圏高齢化危機回避戦略」では、2025年(令和7年)に東京圏だけで約13万人が介護難民になると試算されています(引用:東京圏高齢化危機回避戦略、東京圏高齢化危機回避戦略図表集、一都三県の介護入所施設の収容能力の現状と見通し、日本創生会議)。高度経済成長期に東京に移住してきた世代が高齢者になり、高齢者人口が急増するため、問題は地方よりも都市部のほうが深刻であると言われているのです。
介護難民が増えている原因
高齢者の増加

日本の総人口は1億2,495万人(2022年[令和4年]10月1日現在)であり、65歳以上人口は3,624万人、総人口に占める 65歳以上人口の割合(高齢化率)は 29.0%です。総人口は年々減少していますが、高齢化率は年々増加しています。(引用:令和5年版高齢社会白書、内閣府)
第1次ベビーブーム世代(1947~1949年[昭和22~24年]に出生)が、2015年(平成27年)の段階で65歳を超えており、さらに2025年(令和7年)には75歳以上に。団塊の世代にあたる約800万人が、介護サービスを徐々に受けるようになることが予想されています。
介護職員・介護施設の不足
介護をする側の職員や施設不足も原因のひとつ。厚生労働省によると、介護職員の必要数は以下のようになっています。
| 第8期介護保険事業計画に基づく 介護職員の必要数 |
||
|---|---|---|
| 介護職員の 必要数 |
2019年(令和元年度) 時点で働いていた 約211万人を基準比 |
|
| 2023年 (令和5年度) |
約233万人 | +約22万人 |
| 2025年 (令和7年度) |
約243万人 | +約32万人 |
| 2040年 (令和22年度) |
約280万人 | +約69万人 |
引用:第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について、厚生労働省
要介護認定を受ける方が増えている現状で、2025年(令和7年)には介護職員が約243万人必要と予想されていますが、2019年(令和元年)時点で約211万人しかいません。実際に、全国の介護保険サービス事業を実施する事業所に対するアンケートでは、事業所全体での不足感([大いに不足]、[不足]、[やや不足])は全体の 60.8%と、過半数を占める結果に。(引用:令和2年度「介護労働実態調査」結果の概要について、公益財団法人介護労働安定センター)
現在勤務する介護職員も足りていない現状があり、新規に介護施設を展開しようとしても職員の確保が難しいのが現状です。
介護難民とならないための対策
介護に関する情報収集をしておく
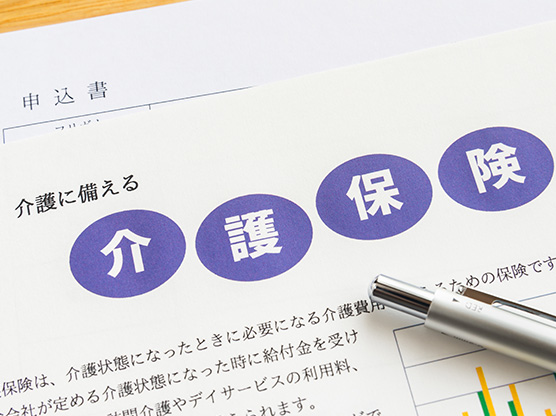
介護が必要になる前から、介護に関する情報収集をしておくのは対策のひとつです。健康な状態のときには介護制度や施設について知らない方が多いですが、いざ介護状態になった際に、様々な制度や施設について一気に調べるのは大変。地域の介護施設、介護サービス、介護保険に必要な手続きを事前に調べておくのがおすすめです。
また、周辺地域の施設の情報を調べておくことで、介護に必要な資金も試算できます。いざ介護が必要になった際に困らないように、どのような介護を受けたいかや、家族でどのようなサポートが可能かを相談しておくのが大切です。
施設入居に十分な資金を準備する
家族が自宅で介護できない場合には施設入居を検討する必要がありますが、施設によっても費用が異なるので、十分な資金を準備しておく必要があります。
安価に入居できる施設は、公的な施設である特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など。ただし、これらの施設は費用が安くて人気が高いので、入居待ちになる場合が多いです。また、2014年(平成26年)に「介護保険法」が成立したことで、特別養護老人ホームへの入居条件は「要介護3以上」となったため、すべての人が申込みできるわけではありません。もしも資金に余裕があれば、サービスが豊富な介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームなどを選択肢に入れられます。
地域包括ケアシステムを利用する
国が構築している地域包括ケアシステムを利用するのもおすすめ。地域包括ケアシステムとは、すべての高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい生活を人生の最期まで継続できるように、地域内で支援やサービスを提供する体制を指します。
- 1医療、看護
- かかりつけ医や地域の連携病院など医療と看護にかかわるサービス
- 2介護、リハビリテーション
- 在宅系サービスと介護予防サービス
- 3介護予防
- いつまでも元気に暮らすための介護予防をするサービス
- 4生活支援、福祉サービス
- 高齢者の生活をサポートする仕組みづくりをするサービス
- 5住まい
- 自宅やサービス付き高齢者向けの住宅など、高齢者の住まいを確保するためのサービス
(引用:地域包括ケアをご存じですか? 厚生労働省近畿厚生局)
例えば、病院を退院しても地域で安心して過ごせるように、訪問診療・看護、リハビリなどを自宅で受けられるように支援してくれます。また、介護サービスだけではなく、配食や見守り、買い物支援などもサポート。地域で元気に暮らすための体操教室や趣味の集い場などを開催し、介護予防目的にも提供されています。中学校区を基本として、おおむね徒歩30分以内に必要なサービスを受けることが可能です。
家族のサポートを受ける
介護が必要になった場合に、家族のサポートが受けられる場合は、在宅介護も考えておくと安心。在宅介護で利用できるサービスには、訪問介護、訪問看護、デイサービス、デイケアなど様々なものがあります。家族だけで介護をするのではなく、介護のプロの手を借りることで、家族の心身の負担を軽減できるのです。
しかし、特定の家族のみが介護を負担して、ストレスがたまるケースもあります。介護うつなどの問題が起きないように、家族全体で事前に役割分担をするなど、介護について話をしておくと安心です。
地方へ移住する
東京に居住している方は、地方へ移住するのも選択肢のひとつ。地方では都市圏よりも介護職員数や施設数が豊富で、介護サービス費用も安いので、施設入居したい方におすすめです。
医療、介護ともに受け入れ能力のある地方都市には、北九州市(福岡県)、室蘭市(北海道)、函館市(北海道)など全国41圏域が発表されています(引用:東京圏高齢化危機回避戦略、東京圏高齢化危機回避戦略図表集、日本創生会議)。介護が必要になる前に地方に移住したり、移住先について調べておいたりすると安心です。
病院やサービスを利用する
特別養護老人ホームは、系列の病院や社会福祉法人によって運営されています。特別養護老人ホームに入居を考えている場合には、同じ系列の法人が運営している病院や施設を利用することで、施設間で在宅介護の状況について情報共有がしやすいのがメリットです。施設側に情報が共有されていることで、入居審査の際に考慮してもらえる可能性があります。なるべく早く入居したい場合には、在宅介護が困難な状況を伝えておくのもひとつの方法です。
生活機能を維持・向上させ、介護予防に取り組む
介護が必要な状況にならないように、生活機能を向上し、介護予防に取り組むことも重要。内閣府の高齢者の健康に関する調査においても、健康を意識した取り組みの重要性が表れています。
- 1健康についての心がけ
- 40代以前から健康に心がけている方は健康状態が良い
- 2健康と社会活動への参加
- 社会活動に参加する方は健康状態が良い
- 3健康と生きがい
- 健康状態が良い方ほど生きがいを感じている
(引用:令和5年版高齢社会白書、内閣府)
40代以前から休養や散歩など健康的な生活を意識していた人や、社会活動(健康、スポーツ、地域行事など)へ参加する習慣のある人は、健康状態が良いと回答した割合が高くなっています。社会活動に参加することで、生活に充実感ができた、新しい友人ができた、健康や体力に自信がついたと回答した割合が高く、前向きな精神状態にも繋がっていることが分かるのです。さらに、健康と生きがいは非常に強い相関関係が見られるという結果でした。
特に男性は、仕事を退職すると地域とのかかわりが希薄になり、外出の機会が減って活動量が減ってしまうことが多いです。社会活動に参加するのが苦手な方は、家事など自宅でできることに積極的に取り組むことで、生活機能の維持を意識しましょう。
病気になってしまった場合にも、リハビリなどに取り組むことで、身体機能の低下をできる限り防ぐことが大切です。
民間の施設も検討しよう

公的な施設である特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などは、費用が安く、人気が高い施設です。
特に特別養護老人ホームは、介護サービスと生活費を合わせて月々約10万円であり、入居一時金などもかからずに利用できるので、待機者が多い状態になっています。実際に、特別養護老人ホームに入居を希望していても、入居できない人の総数は全国で約27.5万人です。(引用:特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度) 厚生労働省)
公的施設への入居が難しい場合には、民間施設も検討するのがおすすめ。公的施設と変わらない費用で利用できる民間施設も増えてきています。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、「サ高住」と呼ばれる、バリアフリー構造である高齢者向けの賃貸マンションです。安否確認や生活相談のサービスが付いている他、買い物に出かけたり、外泊したりするのに届け出は必要なく、自宅同様の自由度の高い生活ができます。現状介護が必要な状態ではなくても、60歳以上であれば、将来に備えて居住することも可能です。
種類、特徴
サービス付き高齢者向け住宅は、介護型と一般型の2種類に分類され、一般型が全体の約92%を占めています。
| サービス付き高齢者向け住宅の特徴 | |
|---|---|
| 一般型 |
|
| 介護型 |
|
サービス内容
安否確認と生活相談の提供が義務付けられているため、日中の時間帯には、介護や看護・医療などの資格を持つ職員が施設に必ずいます。食事サービスや生活支援サービスを行う施設も少なくありませんが、これらの提供義務はありません。
費用
サービス付き高齢者向け住宅の初期費用、月額費用は以下の通りです。
| サービス付き高齢者向け住宅の費用 | ||
|---|---|---|
| 入居一時金相場 | 月額費用相場 | |
| 一般型 | 数十万(家賃の2~3ヵ月分) | 8~20万円程度 (食費、水道光熱費、安否確認、生活相談サービス別途必要) |
| 介護型 | 数十万~数千万円 | 10~30万円程度 (家賃、管理費、水道光熱費、食費、介護保険の自己負担額を含む) |
賃貸住宅なので、賃貸借契約の費用として、敷金または保証金が必要となる場合があります。介護型は、有料老人ホームと同じように利用権方式を採用している場合も。利用権方式では、建物に住む権利と介護サービスなどを利用するための料金がひとまとめになっており、入居一時金や前払い賃料として高額な費用が必要になることもあります。
施設数が多く入居待ちが少ない
サービス付き高齢者向け住宅は、2011年(平成23年)に「高齢者住まい法」が改正されたのちに年々増加しており、入居待ちが少ない状態です。2012年(平成24年)3月には889棟しかありませんでしたが、2022年(令和4年)3月には8,064棟まで増加しています(引用:サービス付き高齢者向け住宅の登録状況、サービス付き高齢者向け住宅登録事務局)。新規の物件も多く、自分の希望に合った住宅を見つけられる可能性も高いです。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設で、24時間体制で介護サービスを受けられます。食事や入浴、排泄などのサービスだけではなく、レクリエーションや設備面などのサービスも充実。ただし、原則として65歳以上の方が対象です。
種類、特徴
介護付き有料老人ホームは、介護専用型、混合型、自立型の3種類。入居対象者は要介護者で、施設によって費用やサービス内容が異なります。また、看取り可能な施設が多く、終の棲家として利用されることが多いです。
公的な施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設)と比較すると費用は割高ですが、介護サービスが充実しているのが特長。また、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているので、介護保険サービスを毎月定額で利用できるのもメリットです。
| 介護付き有料老人ホームの特徴 | |
|---|---|
| 介護専用型 |
|
| 混合型 |
|
| 自立型 |
|
サービス内容
食事や掃除洗濯の他、食事・入浴・排泄・着替えの介助、見守り、生活相談、買い物代行、レクリエーションなどを提供。リハビリテーションは、施設によって提供される場合とされない場合があります。
費用
施設の立地、建物の新しさ、設備や介護の充実度によって、かかる費用に幅があります。
| 介護付き有料老人ホームの費用 | |
|---|---|
| 入居時費用相場 | 月額費用相場 |
| 0~数百万円 | 15~30万円 |
施設数が多く選べる施設が多い
施設の数が多く、施設によって特徴も異なるので、自分に合った場所を選べます。公的な施設よりも待機数が少なく、入居しやすいのもメリット。選択肢が多くて選べない方は、ケアマネジャーなどの専門家に相談するのがおすすめです。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、民間企業によって運営されている自立・要支援、要介護度が低い高齢者の方を対象とした施設。食事の提供や掃除など生活支援が中心で、施設内で介護サービスは提供されません。入居条件は基本的に、65歳以上で自立~要介護5の人としている施設が多いですが、施設によって入居条件は様々であり、64歳以下でも入居できる施設があります。
種類、特徴
住宅型有料老人ホームは、介護専用型、混合型、自立型の3種類に分類されます。
| 住宅型有料老人ホームの特徴 | |
|---|---|
| 介護専用型 |
|
| 混合型 |
|
| 自立型 |
|
サービス内容
住宅型有料老人ホームでは、食事の提供や掃除洗濯、買い物の代行、来訪者への対応、レクリエーション、イベントなどのアクティビティ、健康相談、緊急時の対応、日常の生活相談、見守りサービスなどを提供。日中はスタッフが常駐しているので、緊急時でも安心です。
費用
入居時の初期費用の支払い方法は、一括払いと月々の分割払いの2種類があります。月額費用には、家賃や管理費、食費、水道光熱費などが含まれ、外部の介護サービスを利用する場合には、別途介護費用が発生。月額費用の内訳は施設によっても異なるので、事前にシミュレーションをしておくのがおすすめです。
また、介護保険は上限額以内であれば、基本は1割負担で利用できますが、介護度が高い場合には、利用額が上限額を超える場合もあります。介護付き有料老人ホームとは違い、介護保険サービスにかかる金額が一定ではない点には、注意が必要です。
| 介護付き有料老人ホームの費用 | |
|---|---|
| 入居時費用相場 | 月額費用相場 |
| 0~数百万円 | 15~30万円 |
国による介護難民の解決策
国は介護難民に対して、以下のような解決策を取っています。
地域包括ケアシステムの推進
地域包括ケアシステムは、すべての高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活を継続できるように、地域全体でサポートするシステムです。医療や看護、介護、リハビリテーション、介護予防、生活支援、福祉サービス等、生活を支援する体制を整えています。
自立支援・重度化防止の推進
寝たきりや介護状態にならないようにするために、日頃から運動やできる範囲内での家事をし、身体機能を維持することを推奨。地域の介護予防活動を積極的に実施して、高齢者の健康状態の維持を推進しています。
人材の確保・介護現場の革新

介護職の人材を確保するために、介護未経験者に対する入門研修を創設して、研修終了後には職場の紹介や介護体験イベントを実施。
また、2017年(平成29年)から在留資格に「介護」が加わり「介護」のビザで就労するには、介護福祉士資格を取得することが必須となりました。介護福祉士を目指す外国人留学生の支援も行い、外国人が養成学校へ入学できるようにサポートも実施しています。
また、介護ロボットやICT(情報通信技術)の導入も推進しており、職員の身体的負担の軽減を推進しているのです。
制度の安定性・持続可能性の確保
令和3年度介護報酬改定では、必要なサービスは確保しつつ、給付費抑制に繋がる内容を追加(引用:制度の安定性・持続可能性の確保、厚生労働省)。介護保険サービスを今後も長期間運用していくための工夫を実施しています。
- 1評価の適正化、重点化
- 区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し、訪問看護のリハの評価・提供回数などの見直しなど
- 2報酬体系の簡素化
- 月額報酬化(療養通所介護)、加算の整理統合(リハ、口腔、栄養など)
まとめ
高齢化に伴い、介護難民は年々増え続けています。今後、誰にとっても他人ごとではない問題です。特に都心部では問題が深刻で、職員や施設が不足傾向。将来、身の回りの人や自分自身が介護難民にならないよう、介護に関する情報収集をしっかり行い、可能なら資金を用意しておきましょう。
なるべく待ちの少ない施設を探して入居を希望したり、在宅介護をする場合は負担を抱えすぎないように介護サービスを利用するなど、できるだけ無理のない介護を続けるための工夫が重要となります。


