介護に疲れたら?起きる問題や知っておくべき支援や対策
「介護に疲れた」と感じる原因は、主に精神的・肉体的ストレスによるものです。周囲に協力してもらえる人がいなければ、疲労によって体調を崩したり、「介護うつ」を引き起こしたりする可能性も考えられます。また、介護の疲れが限界を超えると、要介護者への虐待につながるリスクも少なくありません。そのような事態に陥る前に対策を理解しておくことが重要です。介護疲れの実態、問題と原因、介護疲れを軽減する方法を解説します。
介護疲れの実態

厚生労働省の2023年(令和4年)度の「国民生活基礎調査」によると、介護が必要となった原因は以下の通りです。
- 1位:認知症
- 2位:脳血管疾患(脳卒中)
- 3位:骨折・転倒
元気だった親が病気、ケガなどによって突然倒れ、介護が必要になるケースは少なくありません。また、高齢による機能低下や認知症でも、介護が必要となります。突然始まり、終わりが全く見えない介護。家族にも身体的・精神的な負担がかかり、次第に介護疲れを感じる人は少なくありません。
また、鳥取市による「在宅介護実態調査」では、介護者が感じる不安として以下のようなものがありました。
- 認知症状への対応:13.1%
- 食事の準備(調理等):11.0%
- その他の家事(掃除・洗濯・買い物等):8.6%
- 入浴・洗身:8.3%
このように、同居している家族への介護負担が大きくなることで、介護うつ、虐待と発展するリスクもゼロではないのです。
介護疲れによる問題

ストレスの感じ方は、受け止め方や、性格、考え方により、人それぞれです。しかし介護疲れが続くと、次第に身体的・精神的に追い詰められて、深刻な状況に発展していく可能性が高まります。介護疲れによる問題点は、主に以下の3点があります。
- 1体調不良、介護うつ
-
介護疲れによる問題のひとつは、体調不良や介護うつにつながりやすいことです。介護は体力を要するもので、要介護者が寝たきりの場合、24時間体制で体の向きを変えたり、おむつを交換したりといった介助を必要とします。また、認知症による徘徊などがあれば、夜中でも付きっきりで対応しなければいけないケースは少なくありません。そのため、介護をする人が十分な睡眠を取れずに体調を崩したり、介護うつとなったりするのです。介護うつの主な症状は、以下の通りとされています。
- 食欲がない
- よく眠れない
- 考えがまとまらない
- やる気が起きない
- 気持ちが焦る
- これまで楽しかったことが楽しめない
- わけもなく疲れている など
まじめな性格の人ほど、介護のすべてを完璧にやらなければと頑張り過ぎてしまうもの。質の高いケアを提供できる反面、注意しなければならないのは、ストレスの増大。また、介護に専念することで外出の機会が減り、気分も沈みがちになるのです。
- 2虐待行為
-
介護が続き、精神的にも肉体的にも疲れが溜まってくると、要介護者へ辛く当たったり、暴力を振るったりなどの虐待行為も起きることがあります。
厚生労働省が行った2021年(令和3年)度の「養護者による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数」調査によると、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等による虐待相談・通報件数は、年々増加傾向にあるのです。
養護者による高齢者虐待の相談・通報件数と
虐待判断件数相談・通報件数(件) 虐待判断件数(件) 2020年
(令和元年)34,057 16,928 2021年
(令和2年)35,774 17,281 2022年
(令和3年)36,378 16,426 虐待の発生要因として最も多いのは、全体の55.0%を占める「認知症の症状」。ついで、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」が52.4%、虐待者の「精神状態が安定していない」が48.7%となっています。
虐待者の続柄は、要介護者の息子が38.9%、夫が22.8%、娘が19.0%と、男性が半数以上。これまで仕事中心の生活をしていた男性が、慣れない介護にストレスと負担を抱え、虐待に発展すると考えられています。また、虐待行為は、「身体的虐待」が67.3%と最多。ついで「心理的虐待」が39.5%、「介護等放棄」が19.2%。特に要介護者に重度の認知症が持つ場合、「介護等放棄」を受ける割合が高くなっています。
- 3介護離職、離婚
-
介護が長期化すると、仕事との両立に限界を感じ、介護離職する人は少なくありません。厚生労働省の雇用動向調査によると、2022年(令和4年)に離職した人は約7,600,000人。そのうち「介護・看護」を理由に離職した人は、約830,000人(11.0%)でした。
実際に介護を理由に離職し、ケアに集中できるようになったとはいえ、介護にはお金がかかります。経済的な不安を感じることで精神的ストレス、介護うつ、虐待などが発生するリスクが高まるのです。また、精神的なストレス、経済的な不安定さが、夫婦間の仲を悪化させ、離婚へ発展するケースも存在。介護疲れは、介護者の将来や家族環境への影響など、様々な問題を引き起こしやすくなるのです。
介護疲れの原因
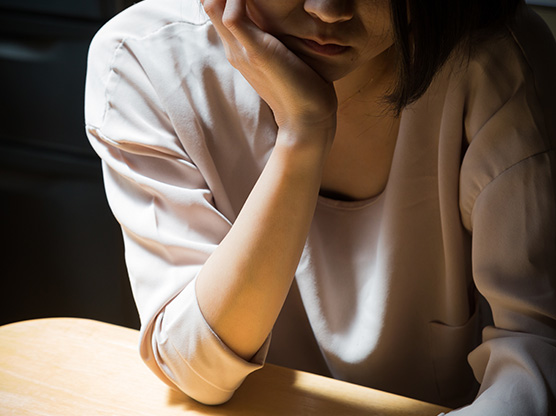
介護疲れの原因は、主に精神的・肉体的・経済的な問題。家庭の事情、要介護者と介護者の性格、人間関係など様々な要因が重なって負担が大きくなっていきます。
介護疲れの主な原因は、主に以下の7点が考えられます。
- 1身体的な負担が存在
- 介護では、入浴やシャワーの介助、ベッドから車椅子への移乗、おむつ交換、トイレの介助などを行わなければなりません。筋力の低下などで自分の力では立てない場合、体を支える必要があり、介護者の足腰に負担がかかります。
- 2生活リズムの乱れ
- 24時間介護が必要な場合、夜中でもおむつ交換や体の向きを変えたりしなければなりません。介護者は十分な睡眠時間が確保しづらく、長く介護を続けていると、次第に介護に疲れを感じてしまいます。
- 3自分ひとりで抱え込む
- 自分ひとりで抱え込み過ぎてしまうことも、介護疲れの原因のひとつです。介護をひとりで行っていたり、周りに協力してもらえる人がいなかったりすると、介護者は精神的に追い込まれてしまうことがあります。
- 4要介護者との心理的距離が近い
- 介護に疲れるのは、要介護者が身近な親であるために心理的距離が近いからです。家族とは気楽な関係でありつつ、小さなことが受け流せず、言い過ぎてしまう場面も少なくありません。不満や苦情も口にしやすい関係。そのために介護者は、「なぜこれだけやっているのに」と責められているように感じ、精神的なストレスを抱えやすくなります。
- 5介護の終わりが見えない
- 介護は、終わりが見えないのも特徴のひとつ。いつまで続くか先が見えないため、精神的なストレスを抱えやすいのも介護疲れの原因です。「長く介護を続けてきたけれど、限界」と思う介護者は少なくありません。
- 6自分の時間が確保できない
- 自分の時間を確保できないことも、介護疲れの原因となります。介護をしつつ、子育てや仕事も行っていれば、自分のために時間を費やすことは困難です。次第に身体的・精神的な負担がかかり、介護疲れにつながります。
- 7経済的な余裕がない
- 経済的な余裕がない場合の精神的な負担も、介護疲れの原因のひとつ。介護にはおむつや保清剤などの消耗品、車椅子や介護ベッドのレンタル費用が必要です。訪問診療や訪問介護などを利用すれば、さらに経済的な負担がかかります。状況によって、介護離職や介護休暇が必要となるかもしれません。収入減少による精神的な負担は、介護疲れにつながります。
介護疲れを軽減する方法
介護疲れは、誰にでも起こりうることです。問題となるのは「介護うつ」や「虐待」などへ発展すること。こうした問題を未然に防ぐために、介護疲れを軽減する方法をご紹介します。
介護疲れを自覚する
まず大切なのは、介護疲れを自覚すること。体がだるい、疲れが取れない、やる気が出ない、注意力が落ちてきた、 などの症状がないか、自分の体と心に目を向けてみます。
また、イライラしたり怒りっぽくなったりしているのも介護疲れの症状のひとつです。感情的になるのは、長引く介護で疲れている証拠。介護疲れを軽減するためには、まずは自分が「疲れていること」を自覚しなければなりません。
ストレス発散方法を見つける
介護に疲れたと自覚したら、自分なりのストレス発散方法を見つけてみます。「介護でそんな時間は作れない」と思う方もいらっしゃるでしょうが、10分でも良いので「自分のための時間を作る」ことが大切です。
人によってストレス発散方法は様々。以下のリラックス方法は、介護のすきま時間に取り入れられます。
- アロマオイルを使う
- 好きな音楽を聴く
- 瞑想をする
- マッサージグッズを使う
- 本を読む
- 好きなテレビや映画を見る
- アイピローをして寝る
- 外の空気に触れる
少しまとまった時間を確保できるのであれば、同じ介護の悩みを持つ人と話したり、友人と会ったりして、気分転換を図るのも有効な手段です。まじめな人ほどひとつの物事に集中して取り組む傾向にあるため、適度な息抜きの時間を確保する必要があります。
質の高い睡眠を取る
介護疲れを軽減するために、「質の高い睡眠」を取ることが重要です。とはいえ、24時間付きっきりで介護が必要な場合、認知症で夜も目が離せないといった方も少なくありません。寝る前や夜中に目が覚めたときなど、軽くストレッチをして筋肉をほぐすと、眠りに就きやすくなる効果が期待できます。
介護の専門家、行政に相談

介護の専門家、行政へ相談することも、介護疲れを軽減させる方法のひとつ。主な相談先としては、以下の3点があります。
- 1住んでいる地域の自治体
-
介護疲れを軽減するために、自治体を活用するのも有効な手段のひとつ。医療機関や介護事業所などとの連携の中心となる自治体。高齢者が自立した日常生活を営めるよう、様々な生活支援サービスの提供、介護予防事業を行っています。
なお、自治体によって介護における支援の充実度は様々です。例として、和歌山県有田郡有田川町における高齢者助成には、以下のようなものがあります。
- 日常生活用具の給付:電磁調理器や火災報知器・自動消化器の給付
- 高齢者福祉通院外出支援事業:医療機関への送迎の運行料金補助
- 家族介護慰労金支給事業:要件を満たす介護者へ、年額100,000円の慰労金支給
- 緊急通報装置の貸与:要件を満たす対象者に通報装置を貸与
- 老人紙おむつ支給事業:条件を満たす対象者へ紙おむつ支給(年間55,000円上限)
介護について悩んだ際は、まず住んでいる地域の自治体まで相談してみましょう。介護疲れを軽減する手段が見つかる可能性が高まります。
- 2ケアマネジャー
-
介護の悩みには専門家である、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談するのも良いでしょう。ケアマネジャーには守秘義務があるため、安心して相談できます。また、介護の専門知識も深く、介護負担を軽減するために、活用できる介護保険制度にはどういったものがあるのか、具体的なアドバイスを受けることも可能です。
なお、ケアマネジャーは地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護施設に在籍しています。そのため、ケアマネジャーを探す場合は、地域包括支援センターあるいは市区町村の介護保険課にて、尋ねると良いでしょう。
すでに担当のケアマネジャーがいる場合は、ケアプランの見直しが有効です。介護疲れが起きている場合、現状と見合っていないケースも考えられるため、ケアマネジャーに相談の上で、ケアプランの見直しを図ることが大切です。
- 3地域包括支援センター
-
地域包括支援センターは、介護・医療福祉、保健など、様々な方面から高齢者及び要介護者を支援する介護の窓口です。市区町村に設置され、ケアマネジャーをはじめ保健師、社会福祉士、看護師など専門知識を持った職員が在籍。なお、地域包括支援センターの具体的な業務内容は、以下の通りになります。
- 健康のことや介護に関する相談
- 介護保険サービスの利用相談
- 成年後見人制度など権利擁護の相談
- 高齢者の虐待通報
- 要支援の人のケアプラン作成
介護保険サービスを利用する
介護疲れを軽減するため、積極的に介護保険サービスを利用しましょう。 介護保険サービスは、要支援・介護状態にある「40~64歳までの医療保険加入者で特定疾患の患者」と「65歳以上の高齢者」が対象とされ、要介護者の収入に応じて1~3割の自己負担額で受けられます。
なお、介護保険サービスを受けるためには、「要介護認定」を受けていなければなりません。受けていない場合は、市区町村の窓口、地域包括支援センターまで申請が必要です。
| 介護保険サービスの種類 | |||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの種類 | 特徴 | 種類 | 内容 |
| 居宅 サービス |
要支援、介護者が居宅に住んだまま受けられるサービス | 訪問 サービス |
|
| 通所 サービス |
|
||
| 短期入所 サービス |
|
||
| 施設 サービス |
必要とする介護度に応じた介護保険施設に入所し、受けられるサービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人 ホーム) |
|
| 介護老人 保健施設 |
|
||
| 介護医療院 |
|
||
| 地域密着型サービス | 要支援、介護者に提供されるサービス | 訪問、通所型 サービス |
|
| 認知症対応型 サービス |
|
||
| 施設、特定施設型 サービス |
|
||
他にも、車椅子やベッドなど福祉用具の貸与や販売、手すりやスロープ設置など住宅改修費の支給など、経済的な負担軽減にもつながる介護保険サービスがあります。
また、介護保険サービスで受けられるもののうち、以下の3点について解説します。
- 1訪問介護
- 訪問介護とは、要介護者が可能な限り住み慣れた自宅で日常生活を送れるよう、介護士が身体介護、生活援助を行うサービスです。身体介護とは食事・排泄・入浴などの介護を指し、生活援助とは掃除・洗濯・調理・買い物などになります。介護事業所によっては、通院目的の乗車、移送、降車の介助を提供するところもあるのです。
- 2通所サービス
- 通所サービス(デイサービス)とは、介護施設に通い、食事や入浴などの日常生活支援や機能訓練を提供する介護保険サービスです。要介護1~5の人が対象で、要支援1・2の人は利用できません。また、利用者の自宅から施設までの送迎も行ってくれます。デイサービスに通っている間、介護者が他に時間を使うことができるため、介護疲れの軽減につながります。
- 3短期入所サービス
- 短期入所サービス(ショートステイ)とは、介護施設が要介護者の短期間の入所を受け入れて、食事、入浴など日常生活の支援、機能訓練を提供する介護保険サービスです。ただし、連続利用日数は30日まで。介護者の病気、冠婚葬祭、出張などでも利用できるため、仕事との両立にも活用できます。また、介護者の身体的・精神的負担の軽減も利用条件となっているのです。
介護保険制度適用外の介護サービスを利用する
介護保険制度の対象にならない、介護保険制度適用外におけるサービスの利用も、介護疲れの軽減につながります。費用は全額自己負担になりますが、介護度によって利用制限がある介護保険制度に比べ、より自由度の高いサービスが受けられるのです。介護保険外サービスの種類には、以下のものがあります。
- 被介護者の外出支援
- 配食
- 訪問美容
- 紙おむつ、パットの配達
介護保険制度適用外の介護サービスについては、担当のケアマネジャー、市区町村の地域包括支援センターにて相談も可能です。
介護施設への入所
介護施設の入所は、最も介護疲れを軽減できる手段。要介護者の意思を尊重して、居宅介護を選択する人は少なくありません。しかし、長期の介護疲れによって体調不良、介護うつ、虐待などにつながってしまう前に、状況に合わせて介護施設への入所を検討することも重要です。
介護保険制度により、入所可能な介護施設は以下の通りになります。なお、介護施設には、自立~要支援の人は入所できません。入所対象は基本的に、65歳以上の要介護1~5の認定を受けている方のみです。
| 介護保険制度によって 入所可能な介護施設 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 介護施設 | 特徴 | 入居 対象 |
認知症の受け入れ | ケア 内容 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 費用が比較的安いため、待機期間が長い | 要介護3以上 | ◯ |
|
| 介護老人保健施設(老健) | 自宅への復帰が目的 | 要介護1以上 | ◯ |
|
| 介護医療院 | 要介護者の長期療養と生活支援が目的 | 要介護1以上 | ◯ |
|
| 介護療養型医療施設(療養病床) | 要介護者の長期療養と生活支援が目的 | 要介護1以上 | ◯ |
|
「特別養護老人ホーム」(特養)は、一度入所できれば、終身にわたって利用でき、看取り対応の施設も増加しています。「介護老人保健施設」(老健)は、医療施設から退院するのは不安な方が、リハビリ目的で入所する施設で、自宅への復帰を目指しているため、長期利用はできません。
また、「介護医療院」は、要介護の高齢者に対し、医療処置や介護の提供を目的としており、重い病気及び認知症のある方が入所対象。さらに「介護療養型医療施設」(療養)は、医療と看護体制が整備されているため、寝たきり及び要介護度の高い方に適した介護施設です。ただし、2024年(令和6年)3月31日までには介護医療院へすべて転換予定で、2012年(平成24年)以降より新設されていません。
レスパイトケア入院の活用
介護疲れを軽減する目的で、「レスパイトケア入院」を活用する方法があります。レスパイトケア入院とは、介護者の負担軽減を目的とした、要介護者の一時的な入院措置です。レスパイトケア入院を利用することで、介護者が休息を取ったり、冠婚葬祭などの対応を取ったりすることが可能になります。また、レスパイトケア入院における1回の入院期間は、原則14日以内。さらに、医療機関への入院となるため、介護を専門家に任せられる安心感があります。
なお、レスパイトケア入院については、地域包括支援センターや担当のケアマネジャー、かかりつけ医などに確認すれば、対応している医療機関が把握できます。
まとめ
慣れない介護が続き、疲れてしまうことは珍しくありません。自分だけで対応しようとすると、介護うつなどの状態になり、生活が上手くいかなくなることも考えられます。ひとりでの介護が限界だと感じたら、迷わず行政及び地域包括支援センターまで相談しましょう。


