介護休暇とは?日数、取得条件、給与の扱い、申請方法を解説
「介護休暇」とは、要介護状態にある家族を介護、世話をするために労働者が取得できる休暇制度です。法律で定められている休暇であり、利用することで介護と仕事の両立が可能になります。また、介護休暇を取得できる日数は定められており、条件を満たす必要があるのです。「介護休暇とは?日数、取得条件、給与の扱い、申請方法を解説」では介護休暇を取得できる日数、対象者、取得条件、給与の扱い、申請と手続きの方法と「介護休業」との違いについて詳しく解説。さらに介護休暇、介護休業のどちらを利用すれば良いかも、例を挙げて紹介します。
介護休暇とは
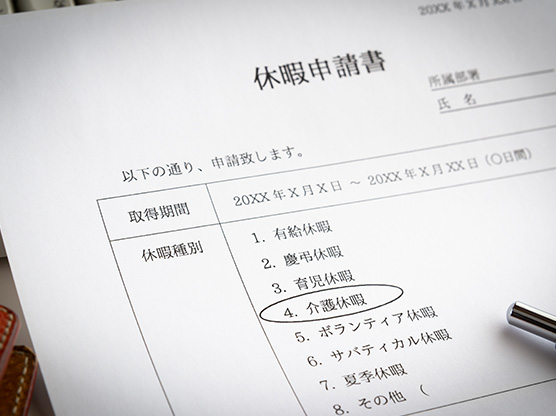
介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護をするために、労働者が取得できる休暇制度です。要介護状態とはケガ、疾病、身体上、精神上の障害で2週間以上常に介護が必要な状態のことを指し、「介護認定」を受けている必要はありません。
また、介護休暇は法律で定められており、活用することで介護と仕事の両立が可能になります。取得した介護休暇は、通院の介助、介護保険制度などの手続き、介護事業所との打ち合わせなどにも利用可能です。
介護休暇を取得できる休暇の日数
介護休暇は、対象の家族1人に対して年間5日間まで、対象の家族が2人の場合には10日間まで取得できます。ただし、対象家族が3人以上であっても10日以上を取得できない点に注意が必要。事業主が定めていない場合は、介護休暇の取得期間は、毎年4月1日~翌3月31日までになります。なお、取得できる単位は、1日または時間単位です。
介護休暇の取得条件
介護休暇の取得条件は以下の通りになります。
介護休暇を取得できる対象者
対象になる家族の介護を行う労働者(日雇いを除く)
介護の対象となる家族
父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者(事実婚を含む)、配偶者の父母
介護休暇を取得できる対象者は正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトの方でも取得可能。ただし、労使協定を締結している場合には、入社6ヵ月未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は取得できません。
介護休暇中の給与の扱い
介護休暇中においては法律で給与の扱いについては定められていないため、各企業によって有給かどうかは異なります。大企業では、給与の何割かを支給してくれる場合もありますが、ほとんどの企業では無給。無給の場合、有給休暇を取得した方が金銭面では有利になります。ただし、有給休暇が少ない人にとっては、介護休暇を活用することによって、仕事と介護の両立ができ、介護離職が防げるのです。介護休暇を取得する前に、給与の支払いについても、総務担当者まで確認しておくのが良いでしょう。
介護休暇の申請・手続き方法
有給休暇の取得時と同様に、介護休暇は口頭、書面での申請が可能。介護休暇の申請方法は、企業の就業規則によっても異なるため、給与の支払い同様に、総務担当者まで確認しておきましょう。
介護休業とは
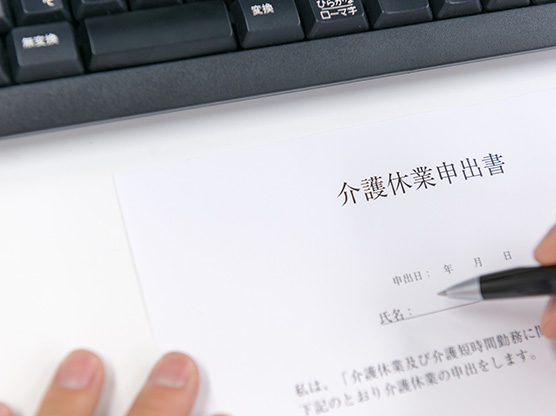
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために、長期間の休みを労働者が取得できる制度であり、数週間~数ヵ月の休暇が取得できます。
要介護状態では、介護休暇と同じく介護認定を受けている必要はありません。介護休業においても介護保険制度、介護事業所との手続きなどに利用できます。
介護休業を取得できる休業の日数
介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日間が取得可能。また、1回目は30日、2回目は30日、3回目は33日など、分割しても介護休業を取得することができます。
介護休業の取得条件
対象者となる家族は介護休暇と同様です。
介護休業を取得できる対象者
対象になる家族の介護を行う労働者(日雇いを除く)
対象となる家族
父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者(事実婚を含む)、配偶者の父母
パート、アルバイト、契約社員など期間を定めて雇用されている方は、介護休業を申し出た時点で取得予定日から93日経過し、その後半年は雇用契約がされない場合には、取得できません。また、労使協定を締結している場合には、入社1年未満、申出の日から93日以内に雇用期間が終了する、あるいは1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外になります。介護休業は、介護離職を防ぐための制度でもあるので、雇用契約が継続しない可能性がある方は対象とならないのです。
介護休業中の給与の扱い
介護休業においても、法律によって給与について定められていないため、取得中は支払われない企業が多いとされています。ただし、条件を満たしていれば、雇用保険から「介護休業給付金」の給付が受けられる場合もあるのです。
介護休業の申請・手続き方法
勤務する総務担当まで、介護休業を開始する2週間前までに書類を提出して申請する必要があります。企業の就業規則によっても異なるので、申請前に確認しておくと良いでしょう。
介護休業給付金の給付について

一定の条件を満たしている労働者であれば、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。なお、介護休業給付金の支給条件は、労働契約に期間が定められていない場合と定められている場合で条件が異なるのです。
正社員など契約期間が定められていない場合は、介護休業開始日前2年の間に、被保険者期間が12ヵ月以上必要です。一方で契約社員、派遣社員など契約期間が定められている場合は、介護休業の開始を行う2年前において、被保険者期間が12ヵ月以上必要。さらに介護休業開始時に同一事業者に1年以上雇用されており、かつ介護休業開始日から起算して93日を経過したあとも雇用されている条件があります。
この介護休業給付の金額は、休業開始時の賃金(日額)×支給日数(最大93日)×67%で計算。ただし、介護休業期間中に勤務し、勤務日数が10日を超えると該当する期間は支給されません。
介護休暇と介護休業の違い
介護休暇と介護休業の違いとは、どのようなものがあるのでしょうか。それぞれの違いについては、以下の通りになります。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 取得可能な休業の日数 |
|
|
| 取得可能な対象者 |
|
|
| 給与の扱い |
|
|
| 申請方法 |
|
|
介護休暇と介護休業の大きな違いは、「取得可能な日数」。介護休暇は対象家族1人に対して最大5日であるのに対して、介護休業では通算93日までとされています。長期的な休暇が必要な場合は、介護休業の取得を検討しましょう。なお、介護休暇は取得当日の申請で取得可能ですが、介護休業は開始する2週間前までに書類で総務担当者まで申請を行い、手続きが必要となります。
介護休暇と介護休業のどちらを選ぶべきか?
介護休暇、介護休業のいずれも介護のために取得する制度ですが、どちらを取得した方がいいか悩む場合もあるかもしれません。ここでは、それぞれに適したケースを紹介します。
介護休暇の取得が適したケース
介護休暇は、取得する当日の申請でも可能であり、1日、時間単位でも取得可能。そのため、急遽休みが必要になる場合、短時間の休みを取る必要がある際におすすめです。具体的な例としては以下の通りになります。
- 通院の付き添い
- 介護保険などの手続き代行
- ケアマネジャーへの相談や面談
- 要介護者の体調不良
- 日常生活上の介護
介護休業の取得が適したケース
介護休業は、長期的な休みが取得できるので、仕事と介護を両立させるための準備期間として利用するのがおすすめです。具体的な例は以下の通りになります。
- 介護施設入居を準備
- 同居での介護を準備
- 家族の看取り
介護施設へ入居する際には、施設探しから手続きまで時間がかかるため、介護休業制度を取得することでじっくりと検討できるのです。また、在宅介護を始める場合にも、介護保険サービスの利用に慣れるまで、活用すると良いでしょう。さらに、家族の看取りをしたいと考えている場合にも、長期間の休みを取れる介護休業を利用するのが適しています。
介護休暇で対応が難しい場合は、介護施設への入所も
介護休暇、介護休業について紹介してきましたが、在宅介護での対応が難しくなってきた場合には、介護施設への入所を検討しましょう。介護度が高くなるにつれ、要求されるケアと知識が大きくなります。
専門知識を持つスタッフが在籍する介護施設ならば、介護の負担を大幅に軽減することが可能であり、要介護者との「共倒れ」を防ぐこともできるのです。在宅介護が困難になった際は、市区町村に設置された「地域包括支援センター」、あるいは役所の福祉課まで介護施設への入所について相談しましょう。
まとめ
介護休暇とは要介護状態にある家族を介護や世話をするために取得できる休暇制度です。取得できる日数は、対象家族1人につき5日間であり、制度を取得できるのは入社6ヵ月以上の労働者と定められています。介護休業も同様に、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休暇制度ですが、取得可能な日数、取得できる条件も異なるので、注意が必要。なお、いずれの制度を利用しても在宅介護での対応が困難な場合には、介護施設への入所を検討しましょう。


