血管性認知症とは?症状や余命、治療について解説
高齢者に多い認知症には、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など様々な種類があり、「血管性認知症」もそのひとつです。血管性認知症は、脳卒中により脳内の神経組織が損傷されることで引き起こされる認知症。「血管性認知症とは?症状や余命、治療について解説」では、血管性認知症における概要、症状、進行、原因、診断方法などを解説します。
血管性認知症の概要
認知症とは脳の機能障害により、本来の認知能力が低下する状態です。また、認知症は現時点において、完治するための治療法が存在しません。
血管性認知症とは
血管性認知症は、脳卒中によって引き起こされる、脳内の神経組織の破壊を原因とした認知症の一種です。アルツハイマー型認知症に次いで多く見られるものであり、高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病が要因となることもあります。血管性認知症の主な症状は、記憶力の低下、判断力の低下、言語障害、運動障害など。これらの症状は、脳内の神経組織への血液供給が不十分になることで引き起こされます。
アルツハイマー型認知症との違い
血管性認知症とアルツハイマー型認知症の大きな違いは、原因と症状の特徴、進行の仕方です。血管性認知症では、血管に問題が起きた部位によって機能が失われるため、症状にはバラつきが見られます。一方のアルツハイマー型認知症では、記憶障害から始まって徐々に広がり、認知症状が顕著になっていく傾向があるのです。
血管性認知症では記憶障害、人格障害などの認知症の典型的な症状は比較的軽度ですが、遂行機能の低下、抑うつ症状、感情の制御困難などの精神症状が頻繁に見られます。また、血管性認知症では片麻痺、言語障害などの神経症状があり、早期段階から歩行障害、尿便失禁などの身体的な問題が発生することも。一方、アルツハイマー型認知症では、記憶障害が初期症状として現れ、徐々に認知機能の低下が拡大していきます。
血管性認知症における余命
血管性認知症の発症後の生存期間については、一般的に男性は約5.1年、女性は約6.7年。ただし、個人の状態、進行速度によって余命も変動します。生活習慣病が基礎にある場合、脳梗塞、脳出血の再発を繰り返すこともあるのです。
血管性認知症の原因

血管性認知症の原因は前述の通り、脳梗塞、脳出血など、脳血管障害によるものです。脳血管障害の中でも、脳梗塞が7割を占めるとされています。
脳血管障害の要因となるのが、生活習慣病です。高血圧、糖尿病、脂質異常症が代表的で、高血圧では、血圧は日中や夜間で変動し、上昇と低下を繰り返します。
長期間にわたって高血圧が続くと、血管が徐々に硬くなり、動脈硬化などの症状が出現。高血圧は、血管の詰まりや動脈硬化を促し、脳梗塞のリスクが向上します。また、糖尿病では、高血糖状態が血管へ徐々に損傷を与え、血管の健康を悪化させていくのです。
さらに脂質異常症においては、高コレステロール状態が動脈硬化を進行させ、血管を詰まらせるリスクが増大。これらの生活習慣病が組み合わさることで、脳の血管に負担をかけ、脳梗塞、脳血管障害が引き起こされる懸念が高まっていきます。
血管性認知症の特徴と症状
血管性認知症の特徴
血管性認知症の特徴のひとつは、「まだらに症状が出る」ことです。朝にできていたことが、夕方にはできなくなってしまうことがあります。また、もの忘れがひどくても判断力と理解力は衰えていないという状態も、まだら症状の一種。これは、脳血管の損傷がない場所は、正常な認知機能が保たれているためとされています。他にも、自律神経が乱れることで症状が出ることも特徴のひとつです。
血管性認知症の症状
血管性認知症では、以下のような症状が見られます。
感情失禁が起きる
失語、失行、失認が起きる
アパシー
血管性認知症の診断方法
血管性認知症の診断

血管性認知症では、医師による問診により、病状を評価します。患者の症状と病歴を詳しく聞き取り、認知症テストを行って「神経心理学的評価」を実施。神経心理学的評価により、認知機能の低下、記憶障害、言語障害、注意力の欠如など、血管性認知症に特徴的な症状を確認します。
次に、血液検査などの身体検査を行い、血液循環や神経系の異常を評価。その後、脳画像検査、脳血流検査、心血管検査を経て血管性認知症かどうかを判定します。
血管性認知症の検査と評価
脳画像検査
脳画像検査にはCT、MRIがあり、CTでは脳の横断的な断層画像を撮影し、脳梗塞や脳出血などの異常を検出。MRIでは、強力な磁力を用いて脳の詳細な断層画像を映し出し、脳梗塞や脳卒中の痕跡、血管の異常などを視覚化します。
脳血流検査
脳血流検査には、SPECT(単一光子放射断層撮影)と、PET(陽電子放射断層撮影)があり、脳の血液循環、血流パターンを評価するために実施。SPECTでは、血液に放射性物質を注入し、脳内の血流や代謝活動を測定し、一方のPETでは、放射性の元素を使用して、脳内の代謝活動や神経受容体の状態を観察します。
神経心理学的評価
認知機能の評価を目的として、患者に認知テストや記憶テスト、言語能力テストなどを実施。これにより、記憶障害、言語障害などの認知症の特徴を評価します。
心血管評価
心血管評価とは、心電図及び心臓超音波検査により、心臓や血管の状態を評価することです。
血管性認知症の進行
血管性認知症では初期、中期、末期によって現れる症状に違いがあります。また、脳血管障害を起こすたびに段階が進むことが特徴です。
血管性認知症の初期症状
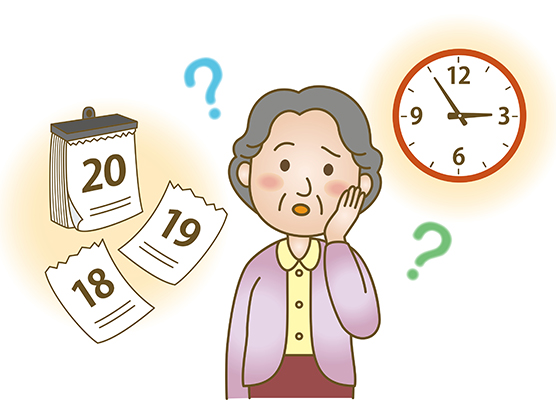
血管性認知症の初期症状には、記憶障害よりも、意欲低下が現れることが少なくありません。症状は常に出ているわけではなく、まだらに出ることも。
そのため、本人や周囲も初期症状を見過ごしてしまう可能性があるのです。他にも失認、失語、失行などの症状も出るようになります。
血管性認知症の中期症状
血管性認知症が中期へ進行すると、発音障害や嚥下障害などの症状が見られることがあるのです。発音障害は言葉をはっきりと発することが難しくなる状態であり、嚥下障害では食べ物を飲み込むことに困難を伴います。特に嚥下障害は注意が必要であり、放置すると肺炎を起こすなどのリスクが高まるため、早めの対応が必要です。
さらに、夜間せん妄、感情の制御が困難な状態、焦燥感などの症状も見られます。なお、中期では歩行障害や排尿障害、転倒のリスクも増加。日常生活の中で介護、支援を必要とする時間が増えていくため、家族の負担も増大する時期なのです。
血管性認知症の末期症状
血管性認知症の末期では、脳内の血管障害が深刻化し、神経細胞の機能がほぼ完全に低下していく状態になります。認知機能障害に加えて、重度の運動障害、失禁、記憶障害などが見られることも。患者はほとんどの時間を寝て過ごすようになるため、家族あるいは医療機関、高齢者施設における常時介護が必要となるのです。
血管性認知症の治療方法
血管性認知症は治るのか

血管性認知症は、完全に治癒する方法はありません。そのため、脳血管障害を再発させないために高血圧、血流を改善するための服薬や、基礎疾患を治療して悪化させないことに注力することになります。
また、早期発見と治療が重要であるため、定期的な健康診断を欠かさないことも重要です。以下では、血管性認知症において行われる薬物療法と非薬物療法を紹介します。
薬物療法
薬物療法として、血管性認知症に効果がある薬はありませんが、血管性認知症の原因となる脳卒中を起こさないようにするための薬を使用。血液が固まることを防ぎ、血栓をできにくくする働きがある、抗凝固剤の「ワーファリン」などが代表的です。
非薬物療法
非薬物療法として行われるリハビリテーションでは、理学療法と作業療法の両面からアプローチ。リハビリテーションは、認知機能の維持と身体機能の改善を目指し、日常生活の質を向上させることが目的です。
理学療法では、適度な運動や体操を通じて筋力とバランス、歩行能力の向上を図り、転倒を予防して、引き続き日常生活で自立することを促進。一方の作業療法では記憶力、注意力、問題解決能力などを鍛える作業を通じて、認知機能の維持、向上を目指します。
血管性認知症の予防
血管性認知症の原因となる脳卒中を防ぐためには、日常生活における注意点が存在。ここでは、2つの注意点について解説をします。
生活習慣の改善
食生活の改善
食生活では野菜、果物、穀物、たんぱく質、健康な脂質などをバランス良く摂取することを心がけましょう。食物繊維は、血糖コントロールなどにも役立ちます。野菜、果物、穀物、豆類などから適切な量の食物繊維が摂取可能です。また、魚介類に含まれるオメガ3脂肪酸は、脳の健康に良い影響を与えるとされています。さらに調理法も重要。揚げ物など油っぽい調理は避け、蒸したり焼いたりするなどの調理法を選ぶようにしましょう。
睡眠の改善

睡眠の質を向上させるためには、毎晩同じ時間に寝る習慣を作り、朝起きる時間も一定にすることで、体内時計を整えることが重要です。寝室は静かで暗く、快適な温度と湿度を保つようにしましょう。
また、日中に適度な活動を行うことで、夜の睡眠を促進することが可能。運動を取り入れて、活発な過ごし方を心がけましょう。なお、夜には過度の運動、興奮を引き起こす活動を避けるべきです。
また、血管性認知症を発症している場合、睡眠障害が現れることがあります。不眠、過度の眠気などの症状が見られる場合は、すみやかに医師へ相談し、専門的な評価と管理を受けることが重要です。適切な睡眠障害の治療を受けることで、睡眠の質の改善が期待できます。
禁煙
喫煙は血管を収縮させ、血流を制限。また、喫煙は体内の炎症反応を引き起こす可能性も。炎症反応は血管内の血液循環を妨げ、血管内膜の損傷を引き起こす要因となるのです。さらに禁煙によって血管の損傷、詰まりを減少させ、脳に十分な酸素、栄養を供給することが可能になります。
アルコールの適量化
アルコールは脳の機能に干渉し、認知機能の低下、血管の損傷を引き起こすことが知られているため、適切なアルコール量の摂取と頻度を心掛けましょう。
適度な運動
適度な運動を行うことで、脳の血流を増加させる効果があります。運動により心臓のポンプ作用が高まり、血液がスムーズに全身に送られるため、脳への酸素や栄養供給が向上。これにより、認知機能の改善が期待できます。また、適度な運動は、筋力やバランス、柔軟性などの身体的機能を維持して転倒や怪我のリスクを減らし、日常生活の自立性を維持することも可能なのです。


