高齢者医療制度とは?保険料や仕組みを分かりやすく解説
高齢者医療制度とは、65歳以上の高齢者に対して、医療費を助成する制度のことです。高齢者が医療費負担を軽減し、健康な生活を送るために重要な役割を果たしています。定年退職の年齢は所属している組織によって様々ですが、年齢が65歳に達すると、今まで医療保険に加入していた人は高齢者医療制度に移行。高齢者医療制度には、「前期高齢者医療制度」と「後期高齢者医療制度」の2種類があり、65~74歳の方は前期高齢者医療制度、75歳以上になると後期高齢者医療制度へ加入する仕組みです。高齢者医療制度について詳しく説明していきます。
前期高齢者医療制度とは
前期高齢者医療制度とは
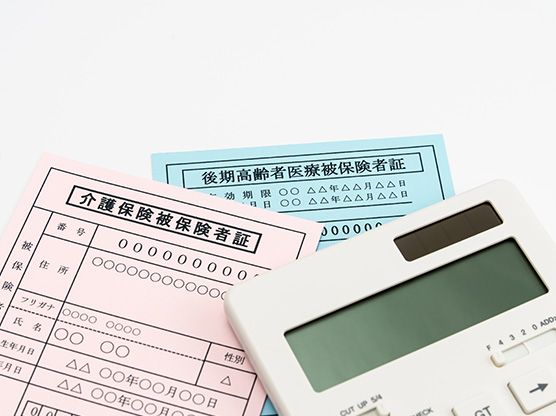
前期高齢者医療制度は、65~74歳の前期高齢者が、医療費を一部負担することで、必要な医療を受けることができる制度です。
健康保険組合などの被用者保険、 国民健康保険間の医療費負担を調整しつつ、介護保険制度と連携して運営されています。
前期高齢者医療制度の対象者
前期高齢者医療制度の対象者は、65~74歳の高齢者です。前期高齢者医療制度に加入するための特別な手続きはありません。
なお、前期高齢者医療制度における65~69歳の医療費負担割合は、今までと変わらず3割の支払いとなります。70歳に到達すると、特に手続きを取らなくても「高齢受給者証」が交付、発送され、医療費負担割合が2割に変わる仕組みです。
ただし、「現役並み所得者」(市町村民税の課税所得が1,450,000円以上ある70~74歳の国保被保険者及びその被保険者と同一世帯に属する70~74歳の国保被保険者)とみなされた高齢者については、医療費負担割合が3割のままとなります。
前期高齢者医療制度の保険料
前期高齢者医療制度の保険料は、国民健康保険や被用者保険の保険料と同様です。前期高齢者医療制度の保険料は、基本的には対象者の所得によって保険料が設定され、所得が上がれば保険料も増加します。
前期高齢者医療制度の仕組み
前期高齢者医療制度は、多くの前期高齢者が加入している国民健康保険と、若年層が多く加入している健康保険組合といった被用者保険との財政的な負担の差をなくすための制度です。
被用者保険から「前期高齢者納付金」という名称で、国民健康保険の財政負担を軽減させる仕組みになっています。そのため、65歳に達して前期高齢者になっても、75歳に達するまでは従来通りの負担で医療を受けることができるのです。
後期高齢者医療制度とは
65~74歳の方を「前期高齢者」と称したとき、75歳以上の方を「後期高齢者」と言います。ここでは、後期高齢者医療制度について説明しましょう。
後期高齢者医療制度の対象者

後期高齢者医療制度の対象者は、75歳以上の方及び一定程度の障害(寝たきり状態など)があると認定された65~74歳の方となっています。一定程度の障害状態にあると認定された方は、前期高齢者の年齢であっても、本人の意思によって後期高齢者医療制度に移行することが可能です。
ただし、保険料を自分自身で支払う必要があるため、65~74歳の方については後期高齢者医療制度ではなく、家族の被扶養者扱いで医療保険に加入していることも可能とされています。
また、対象日の基準は、従来の医療制度では誕生月の翌月から対象となりますが、後期高齢者医療制度では75歳の誕生日当日からが対象。そのため、「後期高齢者医療被保険者証(従来の医療保険証に変わる物)」は75歳の誕生日前月末頃までには自宅に届く予定とされています。なお、一定程度の障害の状態とは、以下の通りです。
- 国民年金法における障害年金1級・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 療育手帳「A」
- 身体障害者手帳1・2・3級
- 身体障害者手帳4級(音声言語機能の著しい障害)
- 身体障害者手帳4級(両下肢のすべての指を欠く、下肢の下腿1/2以上欠く、下肢の機能の著しい障害)
後期高齢者医療制度の保険料
厚生労働省の「後期高齢者医療制度の令和4~5年度の保険料について」では、後期高齢者1人当たりの平均保険料は、全国平均で月額6,472円となる見込みです。これは、2020~2021年(令和2~3年)よりも114円増加した金額となっています。
なお、最も高い保険料は東京都の8,737円、最も安い保険料は秋田県の4,097円となっており、地域によって負担する保険料に差があることが分かりました。
後期高齢者医療制度の仕組み
後期高齢者医療制度への加入は、75歳の誕生日当日からとなっています。
加入手続きは必要なく、対象年齢に到達すると自動的に高齢者医療制度へ移行する仕組みです。
ただし、65~74歳で「一定の障害の程度(寝たきり状態など)」があると都道府県が認めた方については、希望することで前期高齢者医療制度の対象であっても後期高齢者医療制度に移行することが可能。この場合、後期高齢者医療制度加入の手続きが必要です。
まとめ
65歳以上になると自動的に「高齢者医療制度」に移行し、定年退職後も今までと変わらない医療を受けることができます。保険料は、高齢者医療制度に移行したあとも、年金から天引きか、特別徴収(都道府県が発行した納付書で支払う方法)によって支払い続けなければいけません。
医療費の負担割合は所得によって3割負担、2割負担、1割負担に区分。しかし、高齢者の医療費が増額し続けた場合は、3割負担、2割負担の人を増やす基準の改定が検討される可能性が高まっているため、自分の所得がいくらなのか、今から確認しておきましょう。


