認知症の中核症状とは?周辺症状(BPSD)との違いや治療法を簡単に解説
認知症の症状は、「中核症状」(ちゅうかくしょうじょう)と「周辺症状」(しゅうへんしょうじょう)の2つに分けられます。中核症状は、脳の神経細胞の損傷が原因で発生する能力の低下のことで、「新しい情報を記憶できない」、「日付や場所の認識が難しい」、「物事の段取りを考えることが困難」といった問題が含まれ、これらは初期の段階からほぼすべての認知症患者に見られる症状です。一方、周辺症状は、中核症状と環境的要素、身体的要素、心理的要素との相互作用によって引き起こされる、精神的症状や行動的障害のこと。中核症状について、詳しく見てみましょう。
認知症の中核症状とは
中核症状と周辺症状の違い

中核症状は、主に記憶障害や言語障害、意思決定ができないこと、時間や場所の認識が難しいことなどです。
一方、周辺症状は認知症の中核症状とは異なる表現で、不安や抑うつ、幻覚や妄想などを含む精神症状、睡眠障害、食行動の変化などの生物学的症状を指します。これらの症状は個々の患者により異なり、病状の進行に伴い変化する可能性があるものです。
中核症状は、認知症においてはほぼ必ず見られる症状ですが、周辺症状はすべての患者に出現するわけではありません。周辺症状には幻覚、妄想(盗難に遭ったと思い込む物盗られ妄想が典型的)、抑うつ、意欲の低下などの精神的な症状と、徘徊や興奮などの行動的な異常が含まれます。最近では、これらの症状は「BPSD」(認知症の行動・心理的症状)とも呼ばれるようになりました。
なお、認知症の進行とともに特定の周辺症状が出現しやすい時期があります。例えば、抑うつや不安、「物盗られ妄想」は初期から見られることが多いです。幻覚や妄想、徘徊は中期によく見られ、食物以外の物を食べる異食や、うなり声などは認知機能が著しく低下した末期に見られます。
認知症の中核症状の種類と対応方法
記憶障害

記憶障害は、一般的な「もの忘れ」と混同されがちですが、本質的には異なります。もの忘れは、「何かを忘れている」という自覚がありますが、記憶障害の場合忘れているという自覚そのものがないのです。
認知症では、大脳の損傷により記憶障害が発生しますが、運動機能を調節する小脳への影響は少ないのが一般的。認知症でも、身体機能に異常がないのであれば、以前から行っていた行動は忘れにくく、すぐに思い出せなくてもきっかけや、少しの練習で思い出すことが可能です。この種の記憶は「手続き的記憶」と呼ばれます。自転車の乗り方や泳ぎ方など身体で覚える記憶は、一度身に付ければ認知症でも失われにくいです。
また、個々の経験に基づく「エピソード記憶」は、一般的な知識や常識に関する記憶とは異なる非常に個人的な記憶で、アルツハイマー型認知症の場合は初期段階で忘れやすくなる傾向があります。
判断力障害(見当識障害)
見当識障害は、時間や日付、場所、周囲の状況などを適切に認識するのが難しくなることです。これは、アルツハイマー型認知症の進行に伴って、記憶障害に続いて現れる典型的な症状で、「時間認識の障害」と「場所認識の障害」、「人間関係認識の障害」の3つの主要な種類があります。初期の段階には時間と場所の認識障害が見られ、病状が進行すると人間関係認識の障害が現れることが多いです。
時間認識の障害
場所認識の障害
人間関係認識の障害
実行機能障害
実行機能障害は、認知症の初期症状のひとつで、物事を整理したり、計画を立てたりする能力が低下する現象です。料理や洗濯、掃除など日々の家事など、これまで普通に行えていた行動が難しくなります。さらに、乗車しようとした電車が出発してしまった場合に、次の電車を待つなど、予期せぬ状況への対応が上手くできずに混乱することもあるのです。
認知症の種類別の中核症状
アルツハイマー型認知症
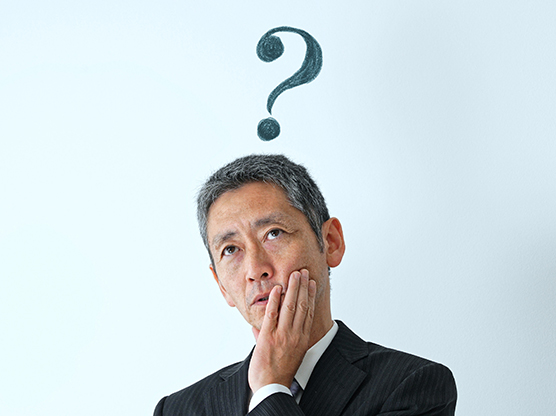
アルツハイマー型認知症などでは、ドアが見えていても部屋から出られなかったり、目の前にある物を渡すよう言われても、言われた物と目の前にある物の関連性が分からず、取れなくなったりするような症状が現れます。
また、「約束そのものを忘れる」、「食事をしたことを記憶していない」など、行為自体を忘れてしまう様子が見られたら、アルツハイマー型認知症のおそれがあるのです。
その他に、「日付や曜日の認識ができなくなる」、「物や人の名前を思い出せなくなる」、「失敗を繰り返し、言い訳を繰り返す」、「同じ話を繰り返す」などが症状として挙げられます。
脳血管性認知症
脳血管性認知症とは、脳梗塞や脳卒中など脳内の血管の病気によって起こる認知症です。症状と重症度は、脳の病気が起きた場所と範囲によって変わります。主な症状は、行動の実行にかかわる障害、言語障害、行動失調や認知の障害などで、脳卒中が繰り返されるたびに病状が深刻化するのが特徴です。
また、脳卒中が発症した部位や範囲によって症状は大きく変わります。例えば、前頭葉やその付近に損傷がある場合、実行機能障害が出やすくなり、左脳に損傷がある場合は言語障害が発生しやすくなるのです。また、右脳に損傷がある場合は空間認識能力や左側の空間への注意力低下などが見られることがあります。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、レビー小体という塊が脳の神経細胞に溜まることで起こる認知症です。理解力・判断力の低下、実行機能障害、失認(しつにん:人の顔や物が正しく理解できないこと)等の認知機能の障害が起こります。記憶障害は比較的軽度ですが、失認はレビー小体型認知症の代表的な症状です。
認知症の中核症状の改善・治療方法
薬物療法

中核症状に対する薬物療法は、1980年代から数多くのアプローチが試みられてきました。
認知症患者の脳内では、神経伝達物質である「アセチルコリン」が不足していることが分かっていたため、その不足を補う治療が行われたのです。
最初は、アセチルコリンを直接補給する試みが行われましたが、効果はありませんでした。そこで、アセチルコリンの生成を妨げる酵素を抑制する薬や、神経伝達物質であるグルタミン酸の作用を調整する薬などが開発され、現在も使用されています。
また、普段服用している薬の影響や、生活環境が良くないことが原因で中核症状が起こることも。中核症状を抑えるには、患者の生活のなかで要因となりうる物事をできるだけ詳しく調査し、取り除いた上で薬物療法を行うことが望ましいとされています。
現在、アルツハイマー型認知症の進行を止めたり、発症を予防したり、症状を改善させたりするための、根本治療薬の開発が進行中です。アルツハイマー型認知症は、「アミロイドβ」(あみろいどべーた)というタンパク質が蓄積することによって起こるとされているため、アミロイドβを取り除くための薬の開発が期待されています。
非薬物療法
非薬物療法とは、医薬品を使用せずに治療を行うことで、リハビリテーションや心理的介入(感情や思考を改善させるためにする、グループセッション等の取り組み)があります。
認知症の患者とその家族をサポートするための対話や環境整備も、治療の一環です。記憶力や方向感覚、行動能力の低下などの症状に対して、使う言葉を工夫する、反復習得を推奨する、スタッフの反応を一貫させるなど、患者がより理解しやすくなる環境を作り出します。
リハビリテーション(理学療法、作業療法)
心理療法
その他の治療法
認知症ケアのポイント
認知症の患者の介護には、認知症を深く理解し、どのように接すると良いかを知っておくことが重要です。ここでは、4つのポイントに絞って紹介します。
- 1患者の気持ちを理解する
-

認知症は、すべての認識能力が一度に失われる病気ではありません。認知症の症状は患者ごとに異なり、病状の進行度によっても変わります。
例えば、自分がどこにいるのか、目の前にある物体が何であるのかを理解できなくなったとしても、そうした混乱や自分の理解能力が下がっていると自覚したときの不安な気持ちを、鮮明に感じているのです。
このような感情を抱えながらケアを受けると、「家族を困らせている」という罪悪感や「自分はひとりでは何もできない」という自己否定的な感情が増幅し、BPSDの発生や悪化を誘因します。
認知症患者に接する人は、同じ状況に置かれたら自分はどう感じるだろうか、どんな心情になるだろうかと想像しながら思いやりを持ってコミュニケーションを図ることが重要です。
- 2患者との信頼関係を大切にする
-
毎日の接触や介護の過程で信頼関係を築くことは、認知症ケアにおいて極めて重要で、根気が必要です。特に、家族が介護者となった場合、認知症患者の失敗や誤解に対して、過去の関係性や習慣から叱責してしまうことがあります。
しかし、認知症の患者でも自尊心や羞恥心を持っているため、怒りを向けられたり無視されたりすると、ストレスを感じてBPSDの悪化を招くこともあるのです。このような場合は、認知症患者を不安にさせないような対話・行動を取ることが重要。
また、患者が安心してリラックスできる環境を整備し、嬉しさや安心を感じられるようなコミュニケーションを取ることも大切です。このような、ポジティブな心の交流が認知症患者との信頼関係を育て、症状の進行や悪化を避けることにもつながります。
- 3患者にペースを合わせる
-
認知症の進行に伴い、中核症状の影響で多くの日常的な動作が困難になり、行動の速度が遅くなることがあります。しかし、認知症患者も「自分でできることは自分で行いたい」という気持ちを持っているため、認知症患者が自力で行える活動は自分でやってもらうのが重要です。できるだけ患者の自己決定権を尊重することで、彼らの生活の質を維持することができます。
さらに、認知症患者が特定の出来事を忘れてしまった場合、周囲の人は患者に強く追求したり、必要以上に思い出させようとしたりするのを避けましょう。その代わりに、患者の話に対して理解と共感を示し、彼らの現在の認識に沿った会話をすることが重要です。これによって、患者のストレスや混乱を軽減することができます。
- 4安定した環境を維持する
-
認知症の進行に伴い、患者は環境の変化に対する感受性が高まり、生活の小さな変化にもストレスを感じることがあります。このようなストレスや不安は、BPSDの悪化を招く可能性があるため、発生源をなるべく取り除くことが重要。
例えば、日常の習慣やルーティンの変更、部屋の模様替えなどは可能な限り避けましょう。移動や新たな施設への入居など、避けられない環境変化がある場合でも、患者が以前から使っていた家具や身の回りの品などを使って、安心できる環境を作ることが求められます。
このように、患者にとってなじみ深い、安心感を得られる環境を作って維持することは、BPSDの管理と改善に寄与するとともに、患者の生活の質を高めるために重要な要素となるのです。


