レビー小体型認知症とは?症状や原因から進行速度、治療法まで解説
「レビー小体型認知症」は神経変性疾患の一種であり、その特徴は徐々に進行する記憶と認知機能の低下です。レビー小体型認知症は、脳内に「レビー小体」と呼ばれる不正なタンパク質が異常蓄積することが起因とされ、患者の日常生活に様々な困難をもたらします。レビー小体型認知症は、アルツハイマー症認知症やパーキンソン病に次ぐ、高齢者における認知症の第3位の原因。レビー小体型認知症の原因、症状、診断方法、及び治療法について詳しく解説していきます。
レビー小体型認知症の概要
レビー小体型認知症は、脳の神経細胞に不正なタンパク質であるレビー小体が蓄積することによって引き起こされる神経変性疾患。認知機能の低下、運動機能の障害、精神症状などが特徴的な症状です。
レビー小体型認知症の特徴
認知機能の低下

レビー小体型認知症では、記憶力の低下や判断力の喪失、注意力の散漫さなどが徐々に現れます。これらの「認知機能の低下」は、患者の日常生活に支障をきたすようになり、例えば買い物をする際に物品の値段が分からなくなったり、家族との会話がスムーズにできなかったりするのです。進行するにつれて、これらの認知機能の低下は深刻化していきます。
運動機能の障害
レビー小体型認知症では、パーキンソン病と似た運動症状が現れることがあり、手足の震えや筋肉のこわばり、歩行の困難さなど、「運動機能の低下」が顕著。患者の日常生活にも大きな影響を与え、食事の取り分けや箸の操作が困難になり、移動や立ち上がりが難しくなることがあるのです。
精神症状
レビー小体型認知症には、幻覚や妄想、不安感、抑うつ症状などの「精神症状」が伴うことがよくあります。幻覚では患者が存在しない人や物を見たり、妄想では誰かが自分を監視していると感じたり、家族が敵意を持っていると思い込んだりすることがあるのです。これらの症状は病状が進行するにつれて悪化し、患者自身だけでなく、家族にとっても大変な負担となっていきます。
睡眠障害
レビー小体型認知症では、睡眠時無呼吸や早朝覚醒、昼夜逆転などの「睡眠障害」も存在。これは、患者が夜間に繰り返し目覚めることや、昼間に眠気を感じることが多くなる原因とされます。睡眠障害は、患者の日常生活や精神状態に悪影響を与え、昼間の眠気が原因で集中力が低下して事故のリスクが高まり、コミュニケーションが困難に。また、睡眠不足は認知機能や精神症状の悪化を招くことがあるのです。
レビー小体型認知症の平均余命
レビー小体型認知症患者の平均余命は、おおよそ7~10年とされています。パーキンソン症状が徐々に悪化して認知機能も低下していくことから、末期にはほとんどの場合寝たきりの状態になり、24時間体制での介護が必要。また、転倒や「嚥下障害」(食物を飲み込む力の低下)による食事中の窒息などの突然死も報告されているのです。
他の認知症や病気との違い
レビー小体型認知症は、レビー小体型認知症と似た症状が出やすい、「アルツハイマー型認知症」、「パーキンソン病」とはいくつかの点で異なります。
症状の進行
アルツハイマー型認知症では、認知機能の低下がゆっくりと進行し、特に記憶障害が顕著な症状として表面化。一方、レビー小体型認知症では認知機能の低下だけでなく、運動機能の障害、精神症状が複雑に関連しながら進行していきます。
精神症状
レビー小体型認知症では、幻視・幻覚、妄想が初期によく見られるのに対し、アルツハイマー型認知症では後期に現れることが多いとされています。
運動機能障害
運動機能の障害に関しては、レビー小体型認知症とパーキンソン病の間に共通点が存在しますが、それぞれに独自の特徴が存在。パーキンソン病では、主に手足の震えや筋肉のこわばり、歩行障害などの運動症状が中心で、認知症状は後期に出現することが一般的です。
一方、レビー小体型認知症では、運動症状と認知症状が早い段階から同時に進行。運動機能の障害にはパーキンソン病と同様の症状が見られ、症状の進行速度や重篤度では個人差が大きく予測が難しいことがあります。
診断の難しさ
アルツハイマー型認知症、パーキンソン病との正確な鑑別診断には「脳画像検査」、「神経心理検査」、「血液検査」などを使用。しかし、これらの検査手段でも確実に区別できない場合があることから、最終的な診断は病理学的検査によって確定されることが多いのです。
レビー小体型認知症の症状
レビー小体型認知症の典型的な症状には、認知機能障害、幻視・幻覚、パーキンソン症状、レム睡眠行動障害、せん妄、自律神経症状、抑うつ状態などがあります。これらの症状は個々の患者で異なる組み合わせ、程度で現れます。
レビー小体型認知症の兆候

- 記憶力が低下する
- 時々思考がぼやける、集中力がなくなる
- 気分、調子が日によって変わる
- 存在しない物を見たり聞いたりする
- 現実とはかけ離れた考えや信念を持つ
- 睡眠中に叫んだり、寝言を言ったり、動き回ったりする
- 動きが遅くなる、ぎこちなくなる
- 足を引きずって歩いたり、歩幅が小さくなったりする
- 筋肉が硬くなり、表情や感情が乏しくなる
- よく転ぶ、気を失うなど
認知機能障害
「認知機能障害」では、記憶力の低下、注意力、判断力の衰えが主な症状。「物事を理解することに問題はなく頭が冴えているのに、反応が鈍くぼんやりとしている」というように、認知機能に変化が見られることが特徴です。この症状は、数分から数時間続くこともあれば、数週間~数ヵ月に及ぶこともあります。
アルツハイマー型認知症では、新しい情報や出来事を記憶することができない認知機能障害が初期から目立ちますが、一方、レビー小体型認知症における認知機能障害では、比較的障害が軽いという違いが存在するのです。
幻視・幻覚症状
「幻視・幻覚」は、レビー小体型認知症の独特の症状。病状の進行とともに悪化することがあり、患者に不安や恐怖感を与えることがあります。なお、幻覚とは、対象物は存在しないものの、明確な感覚がある状態。レビー小体型認知症患者の約80%が幻視・幻覚を経験すると言われています。
パーキンソン症状
「パーキンソン症状」は、手足の震えや筋肉のこわばり、歩行障害などの運動機能に関する症状で、パーキンソン病と共通の症状であり、レビー小体型認知症診断におけるひとつの指標です。
レム睡眠行動障害
「レム睡眠行動障害」は、睡眠中に突然動き出す現象。通常、夢を見るレム睡眠時には体が動かないよう筋肉がリラックス状態になりますが、この障害の場合、筋肉がリラックスせずに動くことがあります。そのため、実際に体を動かしてしまい、場合によっては叫び声を上げることもあり、怪我をするリスクがあるため注意が必要です。
せん妄
「せん妄」は意識が混濁し、集中力が低下し、感情が不安定になる状態。レビー小体型認知症は、認知機能の低下、運動機能の障害、精神症状が複雑に絡み合って進行する病気であるため、病気が進行するにつれて、せん妄が起こりやすくなります。
自律神経症状
自律神経症状とは、レビー小体型認知症患者が「自律神経」(体の内部の働きを調節する神経)に関連した症状です。例として座ったり立ったりする際、血圧が急激に下がることがあり、立ちくらみ、及びめまいを引き起こして転倒のリスクが向上。また、尿が出にくくなる、または頻繁にトイレに行く必要があるなど、排尿問題が起こることもあります。
鬱症状
鬱症状は悲しみや無気力、興味喪失などの精神症状。レビー小体型認知症の患者は病気の進行に伴い、生活の制約、社会的な孤立感が原因となって、鬱症状を発症することがあるのです。
レビー小体型認知症の進行
レビー小体型認知症の進行速度

レビー小体型認知症の進行速度は、一般的にアルツハイマー型認知症よりも速いとされています。無論、進行速度は個人差が大きく、症状が急速に進む人もいれば、ゆっくり進行する人もいるのです。
また、レビー小体型認知症の初期から完全介護が必要となる末期に至るまでの期間は、おおよそ10年と考えられています。進行速度の速さは、年齢、遺伝的要素、健康状態、生活環境によって変化。早期に適切な治療が開始されれば、症状の進行を遅らせることができる場合もあります。
レビー小体型認知症の初期
レビー小体型認知症の初期では、鬱症状、レム睡眠行動障害、嗅覚異常、便秘などの症状が現れることが一般的。なお、初期段階では症状が目立たないことが多く、患者は時間や場所の認識を保ち、周囲の人々と円滑にコミュニケーションを取ることができる場合があります。
しかし、病状が進行すると幻視・幻覚や妄想といった症状がより顕著に。また、病状が進むにつれて運動機能や言語能力の低下、不安定な歩行、認知機能の低下によって日常生活への支障が大きくなっていきます。こうした変化が徐々に進行するため、早期発見と適切な治療が、生活の質を維持する上で重要となるのです。
レビー小体型認知症の中期
レビー小体型認知症の中期ではパーキンソン症状が悪化し、患者はサポートがないと歩行が困難になっていきます。初期段階では認知機能が良好な時期と悪い時期が交互に訪れますが、中期になると悪化している時間が長期化。その結果、コミュニケーションが困難な場合が増加します。
また、徘徊や妄想といった「BPSD」(心理・行動症状)が現れるようになり、幻視・幻視症状も徐々に悪化して日常生活において介助が必須。家族が介護に費やす時間も増えることが予想されます。さらに、社会的スキルの低下や自己管理能力の喪失も発症し、自宅での生活や仕事が困難になり、専門的なケアが必要となってくるのです。このため、患者のニーズに対応した柔軟かつ継続的なサポートが必要とされます。
レビー小体型認知症の末期
レビー小体型認知症の末期では、パーキンソン症状、認知機能障害が一層悪化し、患者は完全介護が必要な状態へ。歩行が困難になり、多くの患者は車椅子での移動が必要になります。歩ける状態であっても、転倒リスクが高まるため、介護者は常にサポートを提供しなければなりません。
また、パーキンソン症状によって嚥下障害が見られることも珍しくありません。嚥下障害が進行すると、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)により命を落とすリスクが高まるため、介護者は注意を払う必要があります。
この段階になると、患者は日常生活を行う能力をほとんど失い、すべてにおいて介助が不可欠。さらに、感情の不安定さ、不眠症が一層顕著になることがあります。
レビー小体型認知症の原因

レビー小体型認知症の原因は、大脳や中脳の神経細胞内へ不正タンパク質の「αシヌクレイン」(あるふぁしぬくれいん)が異常蓄積しレビー小体を形成することで、神経細胞が減少して発症。このレビー小体により中脳のドパミン神経細胞が喪失し、パーキンソン症状が現れるのです。
また、レビー小体は脳だけでなく末梢神経にも形成されるため、起立性低血圧や便秘などの自律神経障害も頻繁に発生。なお、レビー小体型認知症と遺伝の関係はまだ完全には解明されていませんが、一般的には遺伝しないとされています。
さらに、レビー小体型認知症の発症には環境や加齢、生活習慣の影響も大きいと考えられているのです。例えば、喫煙や過剰なアルコール摂取、不適切な食生活、ストレスや睡眠不足などがリスク要因として挙げられています。
レビー小体型認知症の検査方法と診断基準
レビー小体型認知症の検査方法

レビー小体型認知症の診断では、特徴的な症状や行動の確認が重要。必要に応じて、認知機能検査や画像検査も行われるのです。
問診
問診では、患者本人や家族から、日常生活での変化や困難になったことなどを詳しく聞きます。
認知機能検査
認知機能検査では、医師との対話や指示にしたがって動作を行い、記憶力、計算力、見当識、言語理解力などを評価していくのです。
脳の画像検査
脳の検査では、以下のものが行われます。
| MRI検査・CT検査(脳の形を調べる) |
|---|
| 脳の形や萎縮の有無、萎縮部位や進行度を調べます |
| 脳SPECT検査・糖代謝PET検査 (脳の機能を調べる) |
| 脳の血流や糖の代謝を観察し、脳の機能状態を評価します |
| ドパミントランスポーターシンチグラフィ検査(タンパク質の機能を調べる) |
| ドパミン神経の変性、脱落が起きているかどうかを確認します |
| MIBG心筋シンチグラフィ検査 (心筋の交感神経の機能を調べる) |
| 心筋の動きにかかわる交感神経が正常に機能しているかを評価します |
これらの検査を通じて、医師は患者の症状や脳の機能状態を評価し、レビー小体型認知症を判定。ただし、検査結果だけでは診断の確定が難しいこともありますので、症状や経過などを総合的に判断して、他の認知症との鑑別診断も行われます。
レビー小体型認知症の診断基準
レビー小体型認知症の診断に、最も不可欠な症状は認知機能障害です。その他には、幻視・幻覚症状、レム睡眠期行動異常症、認知機能の変動、パーキンソン症状が挙げられます。これら4つの症状のうち、2つが現れる場合にレビー小体型認知症と診断されることが一般的です。
認知症の検査では、問診や認知機能検査に加えてMRIなどの画像診断が行われます。レビー小体型認知症では、アルツハイマー型認知症と比較して脳の萎縮が少ないとされるのです。さらに、SPECT検査を用いて脳の血流状態、ドパミン神経細胞の減少度合いを調べることで、レビー小体型認知症の特徴を確認することが可能。
また、「MIBG心筋シンチグラフィ検査」によって自律神経の機能を評価し、他の類似疾患との鑑別診断に重要な役割を果たします。加えて、家族や介護者からの情報収集も重要。患者の日常生活や行動の変化、症状の経過を詳しく把握することで、より正確な診断が可能となります。
レビー小体型認知症の治療
レビー小体型認知症への対処方法
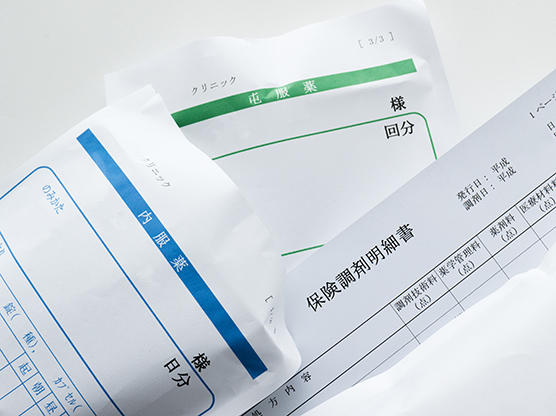
現在、レビー小体型認知症を完全に治す方法は存在しませんが、治療によって病気の進行を遅らせたり、認知症に伴う症状を軽減したりすることが可能です。例えば、幻視・幻覚、認知機能障害、パーキンソン症状などを薬物療法で緩和することができます。また、薬物療法以外のアプローチとして、リハビリテーション、機能訓練で患者の残存能力を最大限活用し、質の高い生活を目指すこともできるのです。
レビー小体型認知症の薬物療法
レビー小体型認知症の治療には、精神症状をコントロールする抗精神薬、運動症状を改善する抗パーキンソン病薬、そして自律神経障害に対する血圧コントロールが行われます。しかし、レビー小体型認知症の患者は抗精神薬に対して過敏な反応を示すことがあり、薬の量を少しずつ増やしながら調整することが重要。また、抗精神薬は運動症状を悪化、抗パーキンソン病薬には精神症状を悪化させることがあるため、薬の使用は慎重に行う必要があります。さらに、アルツハイマー型認知症の治療薬が効果を示す場合もあるのです。
レビー小体型認知症の方への対応
症状を否定しない
レビー小体型認知症の主な症状である幻視・幻覚は、患者にとっては明確に見える形で現れても、家族や介護者には見えないもの。しかし、否定することは控えるようにしましょう。否定することで患者は自尊心が傷付くことがあり、症状の悪化を招くこともあります。そのため、症状が現れた際は共感するなど寄り添った気持ちが大切。また、幻視・幻覚は周囲が暗いときや不安を感じる状況で起こりやすいため、室内照明の調整も大切な対策のひとつなのです。
症状に合わせた対応をする

レビー小体型認知症によってパーキンソン症状が現れると、身体が思うように動かせず、転びやすくなります。ケアを提供する際にはこの点に考慮して注意が必要です。また、レビー小体型認知症の進行期には、嚥下困難が発生しやすくなります。食事のサポートを行う場合は飲み込みやすさに配慮しましょう。レム睡眠行動障害がある場合は周りを明るくし、目覚めやすい環境を整えます。
なお、認知機能の状態は変動して1日の中でも異なり、良い状態のときにリハビリやケアを行うようにすると良いでしょう。また、薬剤への過敏性があるため、異常があればすみやかに主治医に相談することが重要です。
安全に過ごせる環境づくり
レビー小体型認知症の患者は、部屋にある物を誤認することがあるため、目立つ洗濯物を室内に干したり、特定の場所に目立つ色の物を置いたりしないようにしましょう。また、パーキンソン症状による転倒を防ぐため住居のバリアフリーの改修、歩行の安全を確保するために、玄関マットやカーペットを取り除き、部屋のコードを壁に固定することなど環境整備が重要です。患者と家族が安心して暮らせるよう、環境づくりに積極的に取り組みましょう。
介護を拒否されたときの対応
食事を拒む
患者が食事を拒む場合、食事内容や環境を改善することが必要です。食事を拒否する原因が「症状によるものか」、「食事習慣や環境によるものか」を検討した上で、適切な対応を考えましょう。
入浴を拒む
お風呂で幻視・幻覚が現れると、入浴を拒否することがあります。強制的に入浴させるのではなく、幻視・幻覚が消えるのを待ちましょう。また、患者が浴室の環境が気になる場合は可能な限り変更します。さらに、暗い夜の入浴が困難であれば、明るい昼間に試すこともおすすめ。幻視・幻覚が出現しないタイミングを見極めることで、安心して入浴できるようになることが期待できます。
介護が限界を迎えた場合
症状が進行し重篤化すると、認知症患者は自ら動くことが困難になり、一日中寝たきりの状態になることもあるため、その結果として介護者の負担は増大。介護者が適切に休む環境が整わず、身体的・精神的なストレスが蓄積されることは避けたいため、限界に達する前に専門施設への入居などを検討することも重要な選択肢です。
レビー小体型認知症の方が利用できる介護サービス
デイサービス

「デイサービス」は、高齢者や認知症患者が日中に利用できる介護サービス。主な目的は、介護者の負担軽減と、利用者の社会的な交流の促進です。デイサービスを利用することで、レビー小体型認知症の患者は社会的な交流を持ち、症状の進行を遅らせることが期待できます。また、介護者は一時的な休息を得ることができ、身体的・精神的な負担を軽減することが可能です。
訪問型介護サービス
「訪問型介護サービス」は、レビー小体型認知症の患者が自宅で過ごしながら、介護スタッフが定期的に自宅を訪れて、必要な支援を提供するサービス。訪問型介護サービスは、患者の状態や家族の負担に応じて、柔軟にサービス内容を調整できるのが特徴です。また、自宅での生活を続けることで、患者の心身の安定が図られることも大きなメリットとされています。なお、訪問型介護サービスの利用には、一定の条件や手続きが必要であり、適切なサービスを受けるためには、自治体の制度を調べることが重要です。
施設介護サービス
「施設介護サービス」は、専門のスタッフによって24時間態勢で専門施設にて介護サービスが提供されます。これにより、家族が一時的または長期的に介護負担を軽減し、患者も安心して必要なケアを受けることができるのです。
レビー小体型認知症の方に対応している施設
グループホーム

「グループホーム」は、レビー小体型認知症の方を含む認知症患者のための共同生活施設で、通常、数人から10人程度の入居者様が一緒に暮らし、介護スタッフが24時間体制でサポートしています。グループホームでは、家庭的な雰囲気を大切にし、患者の自立を支援しながら、個々のニーズに応じたケアを提供しているのです。
介護付き有料老人ホーム
「介護付き有料老人ホーム」は、レビー小体型認知症の方にも対応できる施設。施設の特徴として、プライベートな居室を提供しながらも、必要に応じて専門の介護スタッフが24時間態勢でサポートを行います。さらに、医療機関との連携が整っており、緊急時や健康状態の変化にも迅速に対応可能。また、介護付き有料老人ホームでは、入居者様同士のコミュニケーションを促すスペースが設けられており、社会的なつながりを維持しながら生活できます。
住宅型有料老人ホーム
「住宅型有料老人ホーム」は通常の高齢者施設と比較して、より家庭的な雰囲気が特徴。入居者数が少なく、通常10人以下の規模で運営されることが多いため、入居者様同士のコミュニケーションが密になりやすく、個々のニーズに対応しやすい環境が整っています。また、施設が一般住宅に近い形で建設されており、地域住民との交流も存在。このような環境がレビー小体型認知症の方にとって安心感や安定感を与え、ストレスを軽減する効果が期待できるのです。
さらに、専門スタッフが24時間体制でサポートを提供し、必要に応じた医療機関と連携。個別のケアプランに基づいて、入居者様の状態や興味に応じたアクティビティ、リハビリテーションが提供されることも特徴です。
レビー小体型認知症の予防方法
生活習慣を整える
食生活の改善
バランスの良い食事を心がけることで、必要な栄養素を摂取し、脳の健康を維持することができます。特に、脳に働きかける「オメガ3脂肪酸」、「抗酸化物質」が豊富な青魚、野菜を積極的に摂ることが望ましいです。
運動の習慣化
適度な運動を習慣化することで、血行を促進し、脳の働きを活性化させることができます。運動は、散歩やストレッチなど気軽に取り入れられるものから始めて、無理のない範囲で続けましょう。
睡眠の質を向上
睡眠不足や睡眠の質の低下は、脳の機能低下につながります。良質な睡眠を確保するために、一定の就寝・起床時間を設定し、リラックスできる寝室環境を整えましょう。
ストレスの軽減
ストレスは脳の働きに悪影響を与えます。ストレス発散法やリラクセーション方法を見付けて、適度に心身を休めることが大切。例えば、趣味や友人との交流を楽しむことで、ストレスを軽減できます。
知的刺激を行う
知的刺激を行うことで脳を活性化させ、認知機能の衰えを防ぐことが可能。読書やパズル、語学学習など、興味を持てることを日常生活に取り入れましょう。
コミュニケーションを積極的に取る
コミュニケーションは、レビー小体型認知症の予防に役立つとされています。コミュニケーションを通じて、脳の機能を活性化し認知機能の衰えを遅らせることが期待できるためです。
社会的繋がりの強化

親しい友人、家族とのコミュニケーションは、社会的繋がりを強化し、孤立感やストレスを軽減します。また、他人とのかかわりを持つことで、自分以外の視点を知り、新しい情報や刺激を得られることから、脳の活性化が期待できるのです。
言語能力の維持・向上
会話を通じて、言語能力を維持・向上させることが可能。話す、聞く、読む、書くなどの言語活動は脳を鍛える効果があり、認知機能の衰えを防ぐとされています。
情報処理能力の維持
コミュニケーションを取ることで新しい情報や意見を受け入れ、処理する機会が増大。これにより情報処理能力が維持され、脳の柔軟性が向上します。
認知刺激の提供
コミュニケーションでは、異なる考え方や知識を共有することで認知刺激を提供。相手との対話を通じて新たなアイデア、視点を得ることにより脳が活性化されるのです。
感情の共有と理解
コミュニケーションを通じて感情を共有し、他者の感情を理解する能力を維持できます。感情の共有は、ストレスの軽減や心の安定に役立ち、精神的健康を維持する効果があるのです。


