認知症を予防するゲーム・食べ物・脳トレなどを紹介
近年、研究により、認知症の予防に役立つライフスタイルや習慣が明らかになってきました。認知症のリスクは年齢とともに増加しますが、日々の生活のなかで少しずつ心掛けることによって、将来認知症になるのを防ぐことができるかもしれません。認知症の予防法について、詳しく見てみましょう。
主な認知症の原因
認知症は、脳の細胞が損傷を受けることによって、記憶力や思考力、判断力、日常生活における動作能力などが徐々に衰える病気です。
認知症には、複数の種類があります。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は世界で最も多い認知症と言われ、日本の認知症の約70%を占めています。アルツハイマー病の原因は、脳内に「アミロイドβ」(あみろいどべーた)と言うタンパク質が異常に蓄積し、神経細胞が死んでしまうことです。アルツハイマー病の危険因子として、年齢や家族歴、遺伝、軽度認知障害、外傷性脳障害などが報告されています。
血管性認知症

血管性認知症は、脳への血流が遮断され、脳細胞が損傷することによって引き起こされる認知症です。認知症のなかでも、高齢者の認知症の原因として2番目に多いと報告されています。
血管性認知症が生じる要因は、脳卒中や脳梗塞、動脈硬化など血管の問題。血管性認知症の症状は、徐々に進行する訳ではなく、脳に血管性の問題が起こるたびに、そのつど段階的に進行していくのが特徴です。脳卒中の患者には、血管性認知症が多いとされています。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、脳内の神経細胞内に「レビー小体」と言うタンパク質の塊ができることで引き起こされます。レビー小体型認知症では、認知機能障害(知覚機能や記憶機能、注意機能、実行機能の低下)やパーキンソン症状(動作が緩慢になる、無表情、小声、筋肉や関節などが硬くなる、小刻みで歩くなど、パーキンソン病に似た症状)などが出現。
レビー小体型認知症の発症初期の特徴として、認知機能障害は目立たないことが多いです。また、1日のなかで物事の判断などをしっかりできる状態と、そうでない状態が入れ替わることを指します。一般的に、レビー小体型認知症は女性よりも男性に多いとされており、認知症のなかでは発症率は20%程度です。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、難病に指定される認知症で、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで引き起こされます。初期には、物忘れなどがあまり見られず、自ら何かに取り組もうという姿勢が失われたり、趣味をしなくなったり、引きこもりがちになったりする自発性の低下や、食事や嗜好の変化が発生。また、外部からの刺激に欲求が抑えられず、本能のままに行動してしまう「脱抑制」(だつよくせい)が生じることが多いです。
前頭側頭型認知症では、脳の後方にある機能は維持されていることから、視空間認知(見た物の向きや位置を認識する能力)や記憶などは保たれますが、前頭葉の機能低下に由来する行動異常などが現れます。
認知症予防の方法とポイント

認知症の決定的な予防法は、まだ見付かっていません。
しかし、定期的に運動をしたり、食生活に気を配ったりして生活習慣を見直すことで、認知症のリスクを減らすことができるとされています。
心臓と脳の健康
心臓病のリスクを増加させる高血圧や糖尿病、高コレステロールなどは、アルツハイマー病の発症リスクを増加させるとされています。心臓と脳の関係は「心脳連関」(しんのうれんかん:循環器の疾患と脳の活動には関連があるとする視点)として、従来注目を集めてきました。
これまでに研究されてきた報告では、高齢心不全(しんふぜん:心臓の働きが悪くなり、全身に血液を十分に送り出せない状態)の患者は、認知症のリスクが2~4倍となり、認知症を発症する頻度や認知症の重症度も心不全の重症度と相関。心疾患のために心臓の機能が低下し、脳の血流が低下することによって、アルツハイマー病につながりやすいと報告されています。
運動と食事
定期的な運動は、アルツハイマー病や血管性認知症のリスクを下げるとされる方法です。東京都健康長寿医療センター研究所(東京都板橋区)は、運動不足の人を10%減らせれば、アルツハイマー型認知症患者を約380,000人減らすことができると報告。
また、運動習慣のある人と運動習慣のない人を長期間調査した結果、週に1回以上の運動を行っている人は、運動を行っていない人に比べてアルツハイマー型認知症のリスクが40%程度低かったという研究もあります。
認知症予防のための食事として、タンパク質やミネラル、ビタミンなどの栄養バランスの良い食事や、脳の活動に必要な栄養素であるEPA(エイコサペンタ塩酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)、葉酸などを補うと良いでしょう。一方で、肉の脂身やマーガリン、ショートニングなどの動物性油といった飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を豊富に含む食材は、認知症リスクを高める恐れがあります。
日常生活でできる認知症予防トレーニング
認知症の予防には、頭を使ったり、体を動かしたりすることがとても重要です。
ゲーム

認知症予防には、脳を刺激するゲームが有効です。特に、パズルやクイズ、記憶ゲームなどは脳の様々な部分を活性化し、記憶力や思考力を鍛えるのに役立ちます。
例えば、問題解決能力と脳の柔軟性を鍛えるにはパズルゲームがおすすめ。パズルゲームにはジグソーパズルやスライドパズル、ナンバープレースなどがあります。
また、クイズゲームも認知症予防には最適です。クイズゲームでは、答えを考えることで記憶力を活性化させます。一般知識クイズや音楽クイズ、映画クイズなど、患者の興味のある分野のクイズを選ぶと良いでしょう。その他にも、短期記憶と長期記憶の両方を鍛える記憶ゲームや、カードゲームの「神経衰弱」、色や音を記憶する「シモン」などがあります。
また、友人や家族と一緒に遊ぶことで、社会的なつながりを保てるのもメリット。適度な運動やバランスの良い食事などと併せて日常に取り入れてみましょう。
脳トレ
脳トレは、脳の機能を維持・向上させるための一連の活動やエクササイズのこと。記憶力や注意力、認知能力を鍛えられるので、認知症予防に役立ちます。脳トレは、数字を使ったものや言葉を使ったもの、読書や音楽など多岐にわたり、例えば、脳の論理的思考と問題解決能力を鍛えたいと思ったら、算数などの問題を解くのがおすすめです。
また、多言語話者は認知症の発症が遅い傾向があるという研究結果もあるため、新しい言語を学ぶことは、脳の柔軟性を高め、記憶力を向上させると考えられています。
読書は語彙力を増やし、新しい情報を吸収する能力を鍛え、音楽を聴く、演奏する、歌うなどの活動は、脳の様々な部分を活性化。特に楽器を演奏することは、手と脳の協調性を高め、記憶力向上に効果的です。脳トレは、楽しみのひとつとして日常生活に簡単に取り入れることができます。
体操
体操は、身体活動を通じて脳の健康を維持し、認知症予防に役立つ重要な要素。例えば、ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、心肺機能を高めて血流を改善し脳への酸素供給を増やします。ウォーキングよりも強度の高い運動を週に3回以上行っている人達は、ウォーキング以下の運動強度で週3回運動を行っている人達に比べて、認知症発症リスクが激減したという報告もあるほどです。
運動を取り入れることで気分を晴れやかにし、認知症発症リスクも下げられます。ヨガや太極拳などのバランスを必要とするような運動は、脳に新たな神経回路を作り出し、脳の柔軟性を高める効果も。筋力トレーニングに代表される無酸素運動は、全身の筋力を維持し、認知機能を保つのに役立ちます。また、筋力トレーニングは、骨密度を高めバランスを改善し、転倒による怪我のリスク軽減も期待できるでしょう。
認知症予防に効果的な運動
運動は、脳の血流をよくするだけでなく、ストレスの軽減によって睡眠の質が向上したり、ポジティブな気持ちになったりなど、心身の健康にもつながります。
有酸素運動
有酸素運動は、ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳など長時間継続して行う運動のことで、心肺機能を高めて全身の血流を改善し、脳への酸素供給を増加。厚生労働省は、週3回以上、1回30分程度の有酸素運動を推奨しています。
無酸素運動

無酸素運動は、筋トレなど大きな力を使って短時間で行う運動のことを指します。認知症を予防するためには、週2回から3回以上、30分以上の運動がおすすめ。これまで運動してこなかった人は、まずは短時間歩くことから始めると良いとされています。
特に、筋力トレーニングは骨密度を高めバランスを改善し、転倒による怪我のリスクを減らす効果が期待できます。
認知症予防に効果的な食べ物と食べ方
認知症の予防には、バランスの良い食生活を送ることが大切です。
地中海食
地中海食は、新鮮な野菜や果物、全粒穀物(精白していない穀物)、オリーブオイル、ナッツ、豆、魚を主体として、鶏肉や卵、乳製品、赤ワインを適度に摂取し、そして赤肉を極力控える様式で、イタリアやギリシャなどの地中海沿岸の人々が食べている伝統的な料理です。
研究では、地中海食のみを食べることが難しい場合、部分的にでも地中海食を実践することが認知症予防に役立つと示されています。地中海食では、不飽和脂肪酸や抗酸化物質を積極的に摂取するため、血管の老化を防ぐことができ、認知症の予防につながるのです。
認知症予防のための食生活

間食を繰り返さないことも、認知症予防に効果があります。間食を繰り返すと血糖値が上昇し、脳血管性認知症につながるリスクもあるのです。1日3食規則正しく食べ、間食をできるだけ控えてみましょう。
さらに、アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイドβは、睡眠が安定している人よりも、睡眠が不安定な人の脳に多くたまることが分かってきています。毎晩7~8時間の睡眠を規則正しいリズムで取るようにしましょう。
年代別の認知症予防法
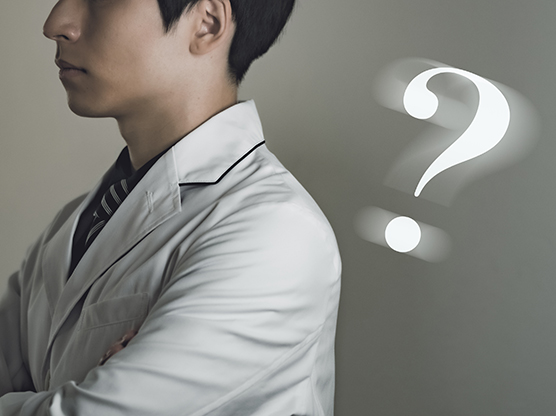
認知症の予防は、年齢に関係なく始めることが可能です。
将来絶対に認知症が発症しないとは断言できませんが、予防法を実践することで、発症するとしてもその時期を遅れさせることができると考えられています。
30代までの認知症予防
30代以前から意識的に認知症予防に取り組むことで、脳の健康を長期的に保ちやすいと考えられています。まず、健康的な生活を習慣付けましょう。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、そしてストレスの管理は脳の機能を保つための基本的な要素です。
特に食事は、脳に必要な栄養素を摂るために重要なので、野菜や果物、魚などの食材を中心にした食事を心掛けましょう。また、脳を活性化させるために新しいことを学ぶことも大切です。新しい分野の学習は脳の神経回路を活性化し、脳の機能を維持・向上。語学学習や楽器の演奏、新しいスポーツなど、自分の興味のある分野で新しいことを学び続けることをおすすめします。さらに、友人や家族との交流、地域活動への参加などを通じて、社会とのつながりを保ちましょう。
30代まではこれからの人生を左右する重要な時期です。この時期に認知症予防に取り組むことで、将来的な脳の健康を保つための基盤を作ることができます。
40~50代の認知症予防
40~50代は、認知症予防にとって重要な時期です。この年代では、生活習慣病のリスクが高まり、それが脳の健康に影響を及ぼすおそれがあります。そのため、この時期には特に健康的な生活習慣の維持と、脳の活性化に努めることが重要。
まず、食生活に注意を払うことが大切です。特に塩分や糖分が過剰になると高血圧や糖尿病のリスクが高まり、脳血管疾患や脳血管性認知症の原因となる恐れがあります。バランスの良い食事を心掛け、特に野菜や果物、魚などの健康的な食材を多く摂るようにしましょう。日本人の食事摂取基準では、高血圧予防のため1日の塩分摂取量は男性で8g、女性で7g未満とされています。
運動もまた認知症予防にとって重要な要素です。BMIは男女ともに40代で18.5から24.9、50代では20.0から24.9を目標に設定されています。年齢が上がるにつれて基礎代謝が低下し太りやすくなるため、適度に運動を行い体重管理を行いましょう。
また、40~50代になると生活に変化が起こりにくく、新しいことを学ぶ機会が減りやすいです。新しいことを学んだり、趣味を持ったり読書をするなど、脳を使う活動を意識的に取り入れて脳の活性化につなげていきましょう。
60代の認知症予防
60代になると認知症のリスクが高まるため、認知症の予防策を積極的に行うことが重要です。この年代では健康的な生活習慣の維持はもちろん、脳の活性化を促す活動を続けることが求められます。60代になると認知症の発症リスクは上昇しますが、「修正可能リスク」と呼ばれる、過剰飲酒や喫煙、運動不足などのリスク因子を改善することで、認知症の発症リスクを40%程度軽減させられるそう。
また、社会的なつながりを保つことは認知症予防に有効で、社会的孤立を避けることもできます。友人や家族とのコミュニケーションは、脳を活性化してストレスを軽減させるため、地域の活動やボランティアなどに参加するのもおすすめです。
生活習慣病は認知症のリスクを高める

生活習慣病は、心臓病、高血圧、糖尿病など、主に生活習慣によって引き起こされる病気です。
生活習慣病は脳血管性認知症のみではなく、アルツハイマー型認知症のリスクを高めることが知られています。特に、心臓病や高血圧は脳への血流を制限し、脳の機能を損なう可能性が高いのです。
また、糖尿病は「インスリン抵抗性」(体内でインスリンを上手く生み出せず、血糖値の調節が難しくなる状態)を引き起こし、これが脳の機能に影響を及ぼすと考えられています。
国の認知症予防策
日本では、認知症の予防策を考え、その実践に力を入れています。
認知症予防の啓発活動
政府や地方自治体は、認知症の予防についての啓発活動を行っています。啓発活動は、パンフレットやWebサイトによる情報提供、認知症予防のセミナー、ワークショップの開催などです。
健康診断と健康相談
一部の自治体では、定期的な健康診断を通じて認知症の早期発見を図っています。また、健康相談を通じて、認知症予防のための生活習慣の改善や適切な運動方法などについてのアドバイスを行っているのです。
コミュニティの活動

地域コミュニティを活用した認知症予防の活動も行われています。地域の高齢者が参加できる運動クラブや学習会の開催、地域住民向けの認知症予防教室の設置などです。
これらの取り組みは認知症の予防だけでなく、早期発見や早期介入、そして認知症患者やその家族の支援にもつながります。
認知症サポーター養成
認知症サポーター養成とは、認知症患者とその家族が社会生活を送る上で必要な支援を提供する人材を育成することです。認知症サポーターは、地域社会での認知症の理解と支援の拡大に貢献する存在。認知症の人々とその家族が抱える問題を理解し、適切な支援を提供することで、認知症の人々が自分らしく、尊厳を持って生活を続けられる社会の実現に向けて活動します。
それでも認知症になってしまった場合の対応
認知症になってしまった場合でも、適切な対応とケアにより、患者自身の生活の質を維持し、家族や介護者の負担を軽減できる場合があります。
早期発見と早期治療
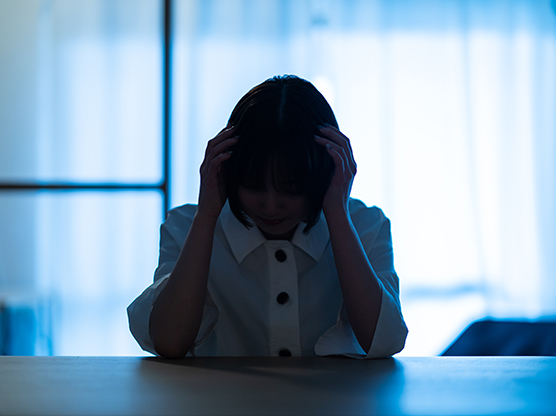
認知症の症状が見られた場合、早期に適切な診断と治療を受けることで、症状の進行を遅らせることが可能となる場合があります。
また、認知症と思われた症状が、他の治療可能な疾患によるものである場合もあるため、認知症かもしれないと思ったら医師に診断を仰ぎましょう。
サポート体制の整備
認知症の患者は日常生活のなかで様々な支援を必要とします。家族だけでなく、専門的なケアスタッフや地域の支援体制を活用することで、患者の生活を支えることが可能です。また、認知症の患者とその家族が情報を得られるように、医療機関や地域の支援センターなどと連携を取ることも重要となります。
リハビリテーション
認知症の患者に対するリハビリテーションは、身体機能の維持や向上、自立した生活の支援を目指します。理学療法(ストレッチやマッサージ、電気療法など)、作業療法(日々の生活に必要な動作を改善させる療法)などの専門的なリハビリテーションを受けることで、患者の生活の質向上が期待できるでしょう。
また、在宅介護で介護者の心身の負担を軽減するために、患者が一時的に入院できる「レスパイト入院」(レスパイト[respite]:休息・息抜きという意味)もあります。レスパイト入院でもリハビリテーションを受けることができるので、患者にとってもおすすめです。レスパイト入院の対象になるかは医療機関ごとによって異なるため、詳しくは問合せをしてみましょう。


