任意後見人とは?できることや手続きの流れ・成年後見人との違いを解説
「任意後見人」とは、認知症などの理由で判断力が失われる前に、財産管理と生活の維持のために、患者が自分の意志で選ぶ後見人のことを言います。老人ホームに入居する際、入居者様の身元を保証する「身元保証人」がいない場合に、任意後見人を求められるケースもあるため、確認は欠かせません。同じ後見人でも「成年後見制度」とは大きく違うため、正確な理解が必要です。任意後見制度の概要、かかる費用、メリットとデメリット、手続きの流れ、老人ホームの入居における任意後見人の役割について、詳しくご紹介します。
任意後見制度とは?成年後見制度との違い
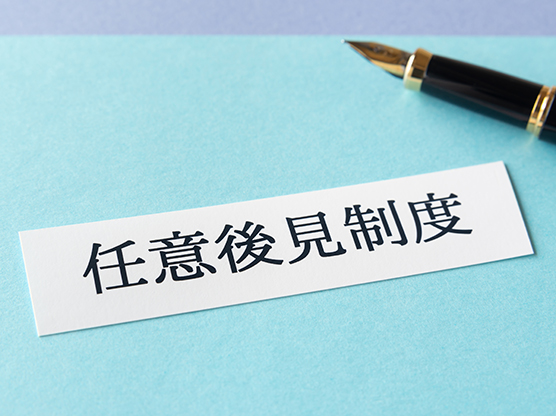
任意後見制度とは、将来的に認知症や病気などで自己判断ができなくなる不安のある方(以降:本人)が、自分で選んだ人を「任意後見受任者」とする「任意後見契約」を結ぶ制度のこと。
契約後に任意後見人は「代理権」を持ち、事前に決められたことの範囲内で、家族であってもできないすべての法律行為について、手続きを代行することが可能です。具体的には、判断能力の低くなった本人が老人ホームを利用するにあたり、入居契約や費用面などで損をしないよう、任意後見人があらかじめ本人と決めた内容にしたがって、契約行為や資金工面を代行することを指します。
成年後見制度とは、任意後見制度と家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」の2つの総称です。成年後見制度により選任された後見人を「成年後見人」と呼び、さらに成年後見人のなかでも任意後見制度により選任された後見人を任意後見人と呼びます。
法定後見制度との違い
法定後見制度とは、本人が判断能力を失っていると認められたときに、親族などが家庭裁判所に申立てると、本人の状況をもとに家庭裁判所が後見人を選任する制度です。任意後見制度では任意後見人を誰にするのか、また代行してもらう権限の範囲を本人が決定できるのに対し、法定後見制度では親族等から後見の申立てを受けたあと、家庭裁判所が決定します。
法定後見制度によって選ばれた後見人は、家庭裁判所で決められた範囲の行為を代行できる「補助人」、家庭裁判所で決められた範囲に加えて民法で定められた行為も代行できる「保佐人」、原則として本人に関係する法律行為をすべて代行できる後見人の、3種類に分けられることを頭に入れておきましょう。
もしも、家庭裁判所の選んだ法定後見人が、親族ではない弁護士や社会福祉士などの専門職だったとしても、親族は基本的に申立ての取り消しができません。法定後見人は本人の代わりに契約行為や資産管理など法的な行為を代行する権限を有するため、本当に法定後見人が必要なのか、本人や親族で慎重に話し合うことが必要です。
手続きの違い
任意後見制度と法定後見制度は、手続きも大きく異なります。任意後見制度では、本人が任意後見人に代行してもらう範囲を決め契約を結んだら、最寄りの公証役場で「公正証書」を作成し登記しなくてはなりません。公正証書とは、中立的な立場で契約などの法律行為を公的に証明する「公証人」によって作成される、公的な書類です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士、司法書士など、長年法律関係の仕事に携わった方の中から任命されます。
公正証書ができ公証人による登記も完了したら、任意後見人になる方が、後見業務を契約通り任意後見人が行っているのかどうかを監督する「任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。その後、家庭裁判所の審判を経て認められれば手続きは終了です。家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い選任されない限り、契約の効力は発生しないことに注意しましょう。
一方、法定後見制度では、家庭裁判所に法定後見を開始するよう申立てるのが特徴です。法定後見制度では、親族だけでなく、自治体の長や検察官なども申立てが可能。必要書類を添えて申立てが受理されると、あとは自動的に家庭裁判所が手続きを進めてくれます。
| 任意後見制度と法定後見制度の違い | ||
|---|---|---|
| 任意後見制度 | 法定後見制度 | |
| 制度の内容 | 本人の判断能力が失われる前に決められた任意後見人が、本人の代わりにあらかじめ決められた権限の範囲で契約など作業を代行する制度 | 本人の判断能力が低下したあとに家庭裁判所によって法定後見人が選ばれ、契約や資産管理などの法的な行為を代行する制度 |
| 後見人が できること |
あらかじめ本人と契約した範囲の作業代行 |
・原則本人に関する法的な行為の代行、ただし補助の場合は家庭裁判所が認めた範囲 ・補佐は家庭裁判所から認められた範囲に加え、民法第13条1項で定められている範囲が代行可能 |
| 手続き | 事前に本人と任意後見人の間で公正証書による契約を締結したあと、任意後見監督人選定の申立てをする | 本人の判断能力が不十分になったあとに家庭裁判所へ後見開始等の申立てをする |
| 後見の申立てを できる人 |
本人、配偶者、4親等内親族、任意後見人 | 本人、配偶者、4親等内親族、検察官、自治体の長 |
任意後見制度は3つのタイプがある
任意後見制度は、本人が任意後見受任者と契約をしたタイミングで任意後見監督人の選任申立てをして任意後見をすぐに始める「即効型」、本人の判断能力に低下が見られるようになってから任意後見を始める「将来型」、任意後見契約とは別に委任契約を結び、任意後見が始まるまでは委任契約に基づいて本人の支援をする「移行型」の3タイプに分けられます。本人の状況などによって利用するタイプが異なるため、チェックしておきましょう。
即効型
即効型は、本人の判断能力がすでに低下しているときなどに利用されるタイプです。なるべく早く任意後見制度を利用したい方が該当します。認知症などで本人の判断能力が低下していても、必ずしも自己判断で契約を結べない訳ではありません。軽度の認知症であれば自分の意思が認められ、契約を結べるケースもあります。ただし、任意後見契約を結んですぐ任意後見制度を開始したくても、公証人が本人に判断能力はないと判断すると契約は結べません。また、公正証書による契約を結んだあとでも、家庭裁判所などの判断で契約が無効になるケースもあります。
将来型
将来型は、本人の判断能力が低くなる前に、任意後見人を決めて公正証書による契約を結ぶタイプです。厚生労働省などで説明されている任意後見制度の基本的な手続きは、主に将来型を指しています。将来型では、公正証書で契約を結んでから実際に任意後見を開始するまでの期間が、長期間になるケースもあるため注意しましょう。時間が空くことで、契約時と本人の意思が変わったり、任意後見人が引越したりすると、本人の状況をすぐに判断できず、任意後見監督人の選任申立てが遅れたりする恐れもあります。そのため、任意後見人が電話などで本人の状況を頻繁に確認するなど、常に本人の様子を確認できる工夫が必要です。
移行型
移行型は、任意後見契約を結んでから実際に任意後見が始まるまでの間、本人へのつなぎの支援として委任契約を結ぶタイプです。例えば、本人に判断能力自体はあるが体は思うように動かせないなどの場合に、委任契約によって任意後見人になる方が財産管理等の事務を代行する契約を結びます。本人の判断能力も問題が発生しだしたら任意後見を開始するため、本人への切れ目ない支援が可能です。
任意後見制度にかかる費用

任意後見制度には、公正証書の作成費用や申立て費用など、様々な費用がかかります。事前に必要な額を準備しておきましょう。
また、任意後見制度を利用すると、報酬の支払いが発生します。本人の収入や貯蓄から継続的な支払いが必要なので、本人の収入源や預貯金残高などを確認しておきましょう。
公正証書の作成費用
公正証書に関する費用には、作成費用の他、任意後見人の代わりに家庭裁判所や公証人が登記申請をする「登記嘱託」(とうきしょくたく)手数料や、登記に関する事務を行う「法務局」へ納付する収入印紙代なども必要です。
| 公正証書作成や任意後見人の登記に 必要な費用 |
|
|---|---|
| 項目 | 費用 |
| 公正証書作成の基本手数料 | 1万1,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 法務局へ 納付する印紙代 |
2,600円 |
| その他 | 本人達に交付する正本の交付代や登記嘱託を郵送するための切手代など |
出典:厚生労働省 成年後見はやわかり 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
任意後見人の報酬額
法定後見人の報酬は家庭裁判所によって定められますが、任意後見人の報酬は任意後見契約に基づいて決められます。子や親族が任意後見人になるときは、報酬がかからないケースも少なくありません。しかし、弁護士など第三者に依頼する場合は、報酬を契約で示しておく必要があります。
費用は法律などで定められていませんが、目安としては月額2~6万円ほど、年間で24~72万円が報酬の目安です。任意後見人が管理する資産の額などで変動するため、注意しましょう。任意後見人の報酬目安を知るためには、裁判所が公開している成年後見人への報酬目安を参考にします。
| 資産額別任意後見人への 月額報酬目安 |
|
|---|---|
| 資産額 | 月額報酬 目安 |
| 1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000超~ 5,000万円以下 |
3~4万円 |
| 5,000万円超 | 5~6万円 |
出典:東京家庭裁判所 東京家庭裁判所立川支部 成年後見人等の報酬額のめやす
報酬の支払いは「任意後見契約」に盛り込む
任意後見人の報酬をいくらにするのかは、具体的に任意後見契約に記載しましょう。金額だけを記載するのではなく、なぜその金額になったかを表す「算定基準」も明記することが大切です。報酬を支払う時期や支払う手段についても具体的に記載しておきます。報酬額を変更するときの条件や、不動産を処分するなど特別な事務作業を行った際の特別報酬額も決めておきましょう。具体的に契約書へ明記すると、金銭トラブルを未然に防げます。なお、報酬の支払いを開始するタイミングは、任意後見契約を締結した日ではなく、任意後見が始まった日です。
任意後見監督人の報酬額
任意後見監督人に支払う報酬は、月額で約1~3万円が目安です。任意後見監督人は、任意後見制度を利用すれば必ず設置される役割なので、報酬の支払いを忘れないように注意しましょう。
| 資産額別任意後見監督人への 月額報酬目安 |
|
|---|---|
| 資産額 | 月額報酬目安 |
| 5,000万円以下 | 1~2万円 |
| 5,000万円超 | 2万5,000 ~3万円 |
出典:東京家庭裁判所 東京家庭裁判所立川支部 成年後見人等の報酬額のめやす
任意後見人の役割・仕事内容

老人ホームにおける任意後見人の役割と仕事内容は、入居者様の金銭管理や介護サービスの契約、入退去時の手続きを担います。
一般的に任意後見人は、本人の財産を管理したり、本人が生活や治療、療養する上で必要な法律行為をしたりする「身上監護」(しんじょうかんご)がほとんどです。日常生活に関する行為を除く、原則すべての法律行為であっても、限定した範囲内で契約した内容によっては代理権が異なるため、契約時に分からない項目があれば、必ず確認しておきましょう。
もし、契約で示された内容を分からないままにしていると、法律行為の範囲で本人が代行してほしい内容を希望通りに実行できない可能性があります。また、任意後見人が対応できない介護や緊急時の対応、死後の事務といった作業もあるため注意が必要です。
財産管理
本人が保有する財産には、現金だけでなく有価証券や自動車、不動産も含まれます。預貯金管理や年金の受け取り、住民税など税金の支払いも財産管理業務の範囲。必要に応じて賃貸の契約を解除したり、不動産を売却したりする行為も任意後見人の仕事です。
本人の通帳は任意後見契約を結んだ時点では、本人が所持しています。しかし、本人の体が不自由になったり判断能力に問題を有していたりすると、任意後見人が通帳を預かって銀行でのお金の引き出しが可能になるのです。通帳を預かるときには、貴重品を預かった証拠である「預かり証」を本人に渡しましょう。
財産管理の仕方
任意後見人に限らず、成年後見人になると、本人の財産状況をまとめた「財産目録」や収入と支出予定についてまとめた「収支予定表」を、随時家庭裁判所へ提出する必要があります。任意後見人の場合は、事前に後見人になる方も分かっているため、本人の判断能力があるうちに財産目録や収支予定表の内容について話し合っておきましょう。
また、本人の財産を現金で管理するときは、お金を使用した額をまとめた「出納帳」に記載しておきます。何にお金を使ったかを具体的にしておきましょう。出納帳の記載自体は義務ではありませんが、任意後見人は家庭裁判所や任意後見監督人へ、預貯金や不動産の状況など、本人の資産・生活状況を報告しなければなりません。出納帳にまとめておくと、現金でのやり取りも含め財産に関する報告をスムーズにできます。また、20万円など多額の現金を預かる場合は、別で口座を作るなどして、本人の財産と任意後見人の財産が混ざらないよう工夫しましょう。
| 出納帳の書き方例 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 本人預貯金口座 | ||||||
| 年月日 | 摘要 | 収入 | 出金 | 残高 | 入金 | 出金 | 残高 |
| 項目 | |||||||
| R5.1.3 | 預貯金口座から 引き出し |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 400,000 | ||
| 預金入出金 | |||||||
| R5.1.5 | 薬代の支払い | 1,000 | 49,000 | 400,000 | |||
| 医療費 | |||||||
| R5.1.20 | 介護施設への 支払い |
30,000 | 19,000 | ||||
| 施設利用費 | |||||||
| R5.1.25 | 年金の入金 | 19,000 | 100,000 | 500,000 | |||
| 年金 | |||||||
| R5.2.1 | 預貯金口座から 引き出し |
50,000 | 69,000 | 50,000 | 450,000 | ||
| 預金入出金 | |||||||
あくまで例のひとつなので、書き方に不安がある場合は、家庭裁判所や弁護士などの専門家に問い合わせておきましょう。
身上監護
身上監護では、施設との入居契約や要介護認定の申請手続きなど、本人が生活する上で必要な金銭面以外の手続きをします。任意後見契約の内容によっては、遺産分割の協議など、本人に関する法律行為をするケースもあるため、契約をするときにしっかり確認しておきましょう。
身上監護の例
- 施設への入退去契約手続き
- 入院時は医療機関との契約手続き
- 要支援、要介護認定申請の手続き
- リハビリなど本人が生活を送る上で必要な医療サービスの契約手続き
- 介護サービス利用にかかる契約手続き
- 遺産分割協議など契約で定められた範囲内での本人に関する法律行為
介護などは対象外
任意後見人が対応できるのは、契約や財産管理など、法律行為にかかわる事務手続きです。実際に介護をしたり施設へ送迎したりする業務は、任意後見人の仕事範囲に含まれていません。食事を作るなど、日常生活のサポートも同様に業務範囲外です。また、任意後見人は、「ケアプラン」(治療方針や介護サービスの方針や内容を決めた計画書)に対する「同意権」もありません。しかし、親族や家族が任意後見人となっているときは、後見人としてではなく家族のひとりとして対応できる場合もあるので、施設や家庭裁判所へ確認しておきましょう。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度は、本人が自分で任意後見受任者や依頼する内容を決められる一方、すでに結ばれた契約の「取消権」がないなどのデメリットもあります。
メリット
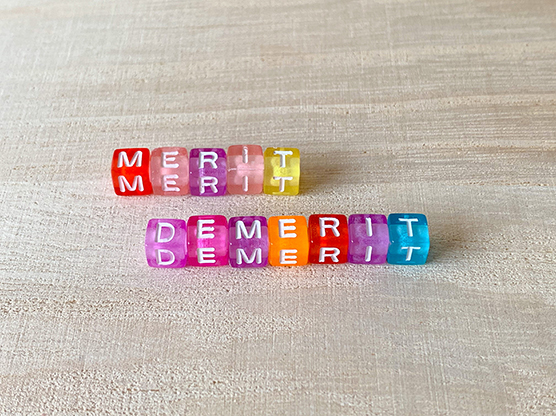
任意後見制度は、本人が希望する人物を任意後見人にできるのがメリットです。契約をする段階で本人にとって信頼できる方を任意後見人に選任できます。法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、本人の望み通りとは限りません。
また、本人が将来の生活についてあらかじめ希望しやすいこともメリットのひとつ。例えば、利用するならどの施設が良いか、できるだけ自宅で過ごしたいなど、判断能力が低下したあとの過ごし方を事前に希望できます。
公正証書により契約内容を公的に証明できることも、任意後見制度を利用するメリットです。さらに、任意後見人には任意後見監督人を付けられるのも有益。契約内容通りに仕事を行っているのか、不正はしていないかなどを第三者により監督してもらえます。
デメリット
任意後見人には、契約を取り消す取消権がありません。任意後見人の知らない間に本人が不当な契約をしてしまっても、任意後見人では契約を無効にできないため、注意しましょう。法定後見人は取消権を行使できます。
また、取消権と同様に同意権も有していません。同意権は、治療方針や介護サービスの利用方針などを、本人の代わりに同意する権利です。任意後見人に限らず法定後見人も同意権を行使できません。身元保証人や家族による同意が必要となります。本人が亡くなった際に行う死後の事務も任意後見人は対応できません。施設に入居していた本人の遺品整理や葬式の手配はできないため、「身元引受人」や親族などに依頼しましょう。
任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度は、本人と任意後見人に指定された人物との間で契約を結ぶと、利用できる制度です。
口頭や文書で契約をしていても、公正証書を作成していないなど不備があると、任意後見契約は成立しません。制度を活用するためにも、手続きの流れを確認しておきましょう。
- 1任意後見受任者を決める
-
任意後見受任者は、任意後見人として指定された方です。任意後見人になるために、特別な資格は必要ありません。家族や親族、知人、友人といった知り合いから弁護士や司法書士などの専門家まで、本人が信頼して任せられると感じた方を指定できます。個人ではなく、法人に依頼することも可能です。
任意後見人は1人以上指定できるため、1人だと不安な場合は必要な人数を指定しましょう。
任意後見になれない人
民法第847条で資格を持たない条件である「欠格事由」に該当すると、後見人になれません。任意後見人になれない条件は以下の通りです。
民法第847条で定められている後見人の欠格事由 - 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、またはした者ならびにその配偶者、及び直系血族
- 行方の知れない者
出典:e-gov法令検索 明治二十九年法律第八十九号民法 第四編 親族 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人(後見人の欠格事由)第八百四十七条
法定代理人とは、家庭裁判所から本人の代わりに民法に基づく権利を行使するよう命じられた方を指し、法定後見人も法定代理人に含まれます。後見人の役割を家庭裁判所から取り消された経験があると、任意後見人にはなれません。法定代理人の役割が取り消される条件は、後見事務を怠ったり本人の財産を不正利用したりするなど、法定代理人として適切でない行動をしていると判断されたケースなどです。
- 2任意後見人にしてもらいたいことを決める
-
任意後見制度では、契約内容は当事者間で決められます。本人が入居したい施設やかかりつけの病院など、将来のライフプランをなるべく具体的にしておきましょう。ライフプランの希望に応じて、必要な費用を記載しておくのも必要です。
任意後見人が対応できるのは、財産管理や身上監護といった法律行為のため、ペットの世話や病院への送迎など日常生活における世話を依頼したい場合は、任意後見契約とは別に委任契約を結ぶ必要があります。本人が亡くなったあとの事務に関しても同様で、依頼したいときは死後の事務に関する委任契約を結んでおきましょう。
- 3公正証書で契約を締結する
-
公正証書は必ず作成しましょう。本人と任意後見人の間で契約内容を決めたら、本人と任意後見人で公正証書を作成する場所の公証役場に行きます。事情があって直接公証役場へ赴けない場合は、公証人が代わりに手続きをしてくれるケースもあるため、確認しておきましょう。なお、任意後見人の登記については公証人が行います。
- 4任意後見監督人選任の申立てを行う
-
本人の判断能力が不十分になったとき、任意後見制度を始めるために、家庭裁判所へ任意後見監督人を選任してもらうよう申立てる必要があります。任意後見契約は、任意後見監督人が決められてから効力を持つためです。申立ては、本人、本人の配偶者、本人から4親等以内の親族、任意後見受任者でないとできません。また、申立てるときは手数料として800円が必要です。申請するために必要な書類も揃えておきましょう。申立てにあたって必要な書類を以下にまとめました。
申立てに必要な書類一覧 - 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
- 家庭裁判所が定める様式で作られた本人の診断書
- 本人の財産に関する資料
出典:厚生労働省 成年後見はやわかり 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
必要に応じて、追加で書類の提出を求められるケースもあります。
-
- 任意後見監督人とは
任意後見人が契約通りに仕事を行っているのか、不正な行為はないかなどを監督する役割が任意後見監督人の職務です。任意後見人は、求められたときに任意後見監督人へ、財産目録や収支予定表など書類を提出しなければなりません。
もし、本人と任意後見人の利益が対立する内容の法律行為を必要とするときは、任意後見監督人が本人の代わりにします。任意後見監督人が本人の代行をするときは、監督役を家庭裁判所が担当し、任意後見監督人は実行した法律行為や事務作業などに関する報告を家庭裁判所にしなければなりません。
- 5任意後見監督人の選任後、職務を行う
-
任意後見監督人の選任が終了すると、任意後見人としての職務が始まります。契約内容をよく確認し、本人の意向に沿うよう職務を行いましょう。もし、事情により任意後見契約を終わらせたい場合は、本人か任意後見人のどちらか、もしくは両方から申立てられます。
また、双方が同意している場合は、合意解除書へ公証人による認証をもらえば、認証をもらった時点から解除が可能です。任意後見契約が無効になったときは、成年後見人本人による任意後見契約が終了したことを登録する「終了登記」の申請を法務局で行います。
老人ホームにおける任意後見制度
任意後見制度は、亡くなったときに入居者様の身柄を引き取り、居室の遺品整理などを行う身元引受人や身元保証人がいない人が、施設を利用するために必要な制度です。施設へ入居する際、多くの施設では身元保証人や身元引受人を立てなければなりませんが、身元保証人や身元引受人が共に見付からない場合は、成年後見人でも良いとしている施設もあります。
具体的には、老人ホームの利用契約前に受領できる「重要事項説明書」に詳しく内容が記載されているため、よく確認しておきましょう。任意後見人がいると、入居者様の資産管理や施設の入居に関する手続きを代行できます。
銀行口座の凍結を解除でき、資産の管理をしてもらう

任意後見人は、銀行口座の凍結を解除できる権限があります。口座の持ち主が認知症であることを銀行が判断すると、不正利用や不正取引を防ぐために、銀行は当事者の口座を凍結せざるを得ません。凍結された口座では入出金はできず、公共料金や年金に関する処理は続けてもらえるケースもありますが、生活費や生活用品を購入するためなどの理由ではお金を出金できなくなります。
任意後見人がいれば、口座の凍結を解除した上で財産管理も可能です。契約で決められた範囲内で介護費用や施設利用料など、本人が施設を利用するときに必要な費用を用意できるため、施設側としても滞納の心配がなくなります。
判断能力が低下しても施設に入居できる
先述したように、任意後見人は判断能力に問題がある本人の代わりに、資産管理や契約といった法律行為ができます。介護施設や老人ホームとの入居契約も職務範囲です。施設によっては身元保証人がいなくても契約行為をできる、後見人さえいれば入居できる施設もあるため確認しておきましょう。
身元保証人との違い
任意後見人は、身元保証人を兼任できません。身元保証人は、入居者様に代わって意思決定や手続きをしたり、入居者様が施設の利用料金を支払えなかったときに連帯保証人として支払ったりする役割があります。任意後見人は、本人の代わりに財産管理など法律行為をする権限を有しているだけで、本人の連帯保証人にはなれません。本人同様の後見人が本人の連帯保証をすることは不可能なためです。
連帯保証人を必要とする施設では、任意後見人だけでは入居できないケースもあるため注意しましょう。任意後見契約を結ぶ前に、本人が利用したい施設の入居条件を確認しておくこともおすすめです。もし、身元保証人が必須の施設だった場合は、自分で身元保証人を用意できるか確認してから任意後見契約を結びましょう。
まとめ
任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、依頼する相手や代行してほしい内容を自分で決められるメリットがあります。しかし、契約の取消権や治療方針などへの同意権は有していません。任意後見人を依頼するときは、任意後見人ができる事務とできない事務の内容を理解しておきましょう。将来利用したい施設が決まっている場合は、身元保証人が必須でないかの確認も必要です。身元保証人が必須の場合は、任意後見契約を結ぶ前に身元保証人の手配が必要になります。


