パーソン・センタード・ケアとは?認知症の方を理解するための5つの要素を解説
「パーソン・センタード・ケア」とは、ケアを行う際に認知症を患った高齢者の個性と生活様式を尊重して、ひとりの人間として捉えることが大切とする考え方です。認知症の方にも個々の性格、考え方、感じ方があるのは当然であり、ケアする側もそれに応じなければなりません。「パーソン・センタード・ケアとは?認知症の方を理解するための5つの要素を解説」ではパーソン・センタード・ケアの概要、それに基づいた認知症の方へ接し方を解説していきます。
パーソン・センタード・ケアとは

パーソン・センタード・ケアとは、認知症の方をひとりの人間として尊重し、考え方や性格、生き方などを理解して接する、認知症ケアにおける考え方のひとつです。
このパーソン・センタード・ケアは、イギリスの臨床心理学者である、トム・キッドウッド氏が「その人らしさを中心にケアをすること」として提唱。認知機能が低下し、意思疎通も難しくなり行動が変化したとしても、その人らしく生きていくために、認知症の方の個性を尊重かつ維持していくことが重要であるとしています。また、最適な介護を提供するためにも、パーソン・センタード・ケアは重要な考え方であるとされ、医療の現場で活用されているのです。
認知症の方を理解する5つの要素
パーソン・センタード・ケアの考え方には、認知症の方を理解するための5つの要素が存在します。この5つの要素とは、「脳の障害」、「性格」、「生活歴」、「健康状態」、「その人を取り囲む社会心理」のこと。認知症は脳細胞に異常と変化が生じることで症状が現れ始める病気ですが、患者がこれまで歩んできた生活、環境、周囲の人間なども認知症に関係すると捉えているのが、パーソン・センタード・ケアの考え方なのです。
- 1脳の障害
-
脳の障害は、脳神経細胞の異常、脳血管疾患の後遺症などが原因で生じます。神経伝達物質の問題により、記憶障害や幻覚、動作や物の扱い方が分からないなどの症状が出現。突然、物忘れを指摘されるようになったり、見えるはずのない幻覚が見えたりすることは、患者本人が最も不安を持ち混乱します。そのため、症状が現れていることを単なる異常とはせず、認知症の方へ寄り添うことが必要となるのです。
- 2性格
-
性格は、人格を形成する大きな要素のひとつ。社交的か内向的か、自ら行動する方かそうでない方か、おっとりした方か気が短い方かなど、それぞれの個性を表す要素ともされています。個性が違えば、認知症になった際の行動や言葉も変わるもの。もともと短気な方がより荒っぽい言動をするようになったり、他人から何かされることを嫌う方はより人を避けるようになったりします。性格は、認知症の方と接する上でも重要視すべきで、患者が嫌がらないケアを行うための判断材料となるのです。
- 3生活歴
-
生活歴とは、その人がこれまで送ってきた生活様式、行動の仕方、物事の捉え方などを総じて表したもの。認知症になることで、記憶やコミュニケーション能力が低下したとしても、長年行ってきた習慣、考え方が急に変わるわけではありません。
食事の仕方、身支度の順番、好きな食べ物や飲み物など、患者の生活に深くかかわってきたことは、認知症になったあとも表面に出やすいのです。
- 4健康状態
-
認知症の方は、自身の健康状態を他人へ伝えることが困難となり、知らず知らずのうちに不快な思いをしている場合があります。咳などの風邪症状、目に見えるケガは容易に確認できますが、体内の不調は単に接しているだけでは伝わりづらく、気付かないうちに大きな問題を抱えていることもあるのです。表現が上手く行える方であれば、聞き取りも可能ですが、大半の認知症の方ではそうはいきません。そのため、食事の摂取量、行動、表情など、様々な面から観察して違和感に気が付くことが必要となります。
- 5その人を取り囲む社会心理
-
社会心理とは、患者に対して周りの接し方、扱い方によって影響する心理のことです。認知症の方は表現が上手くできないだけで、受けている扱い、言われた言葉に対して傷付いていたり、憤りを感じたりしていることもあると考えられています。
また、認知症の方に接する場合、ゆっくりと伝わりやすいような話し方を心掛けることがありますが、子供と話すような口調、少々見下したような接し方をしている場合も存在。そのような言葉、態度は患者の尊厳を傷付け、内面を悪化させてしまう要因になってしまうのです。感情は認知症状の強さにも現れやすいため、普通の方と接するのと同じような態度で、ケアに当たることが重要とされます。
軸となるパーソンフッド

パーソン・センタード・ケアにおける軸となるのが、「パーソンフッド」(その人らしさ)です。認知症の方に接する場合、相手を単に認知症の患者として捉えてしまうことに注意しなければなりません。
「もの忘れをする人」、「話がうまく伝わらない人」のように、相手を一個人ではなく認知症患者として捉えてしまうと、適切なケアやコミュニケーションが取れなくなる恐れが存在。
パーソンフッドでは、認知症の方の個性、特徴、生活スタイルなどを尊重し、「その人そのもの」を見るべきだとされています。認知症の方のすべてを受け入れることで、介護者と要介護者がお互いに尊重しあい、関係性を構築していくことが、パーソン・センタード・ケアへ繋がるのです。
認知症の方における5つの心理を知る

認知症の方は、ときに攻撃的な言葉を発したり、暴力をふるったりすることもあります。心のコントロールができず、混乱や不安を行動に表してしまうのです。こうした状態は、生活に不安、不満があることを表している場合もあります。
以下で紹介する「5つの心理」を理解して接することで、生活の質を向上させることにもなるでしょう。
- 1くつろぎ
-
「くつろぎ」とは、身体的な苦痛を感じることなく、快適に生活できている状態。認知症の方は椅子やベッドで長い時間を過ごす方も多く、常に体重のかかっている背中、臀部(おしり)に痛みと苦痛を感じる方もいます。また、部屋の温度、匂い、音などリラックスできる環境でなければ、くつろげる生活を送っているとは言えません。健康状態に問題がなく、対応なども気を付けているのに、認知症の方が不快と感じる行動を取っている場合は、まずは生活環境へ目を向けてみると良いでしょう。
- 2自分が自分であること
-
「自分が自分であること」とは、自己同一性、個性が重要であることを指しています。認知症の方が過去に歩んできた道のり、これまで大切にしてきたもの、できごとの記憶などが「自分は自分である」ということの自覚へ繋がるのです。認知症により記憶障害が起きると、自分の行ったことを覚えていなかったり、知らないうちに他人へ迷惑をかけてしまったりと、まるで自分が自分でないような感覚に襲われます。そういった不安が続くことで、心理的に不安定になり、認知症状が余計に強く現れてしまうことも。認知症の方の行動、言動を介護者などから伝えることは、認知症の方に自分が自分であることを自覚して貰うためにも必要です。
- 3結び付き
-
「結び付き」とは、自分と他者とのかかわり、大切にしてきた物事に対しての感情、記憶、こだわりなどを指します。認知症によって理解力、記憶力が低下しても、長い期間かかわってきた人物、大事な記憶、愛着のある物とのかかわりは、認知症の方の心の支えです。行動や言動が不安定なときは、そういった大切な思い出、人物の存在が認知症の方の安心感に繋がり、生活の平穏を保つ手助けになります。
- 4携わること
-
認知症が進行すると、一見して理解不能で必要のない行動を取る方も。しかし、このような行動の背景には、「誰かの役に立ちたい」、「自分なりに何かをしてみたい」という心理が働いている場合があります。行動の内容によっては他人に迷惑がかかる可能性、本人及び他者へ危険が及んでしまうようなこともあり、時には制止する必要もあるでしょう。しかし、問題行動ではない場合は静観することも必要になります。行動すべてを異常として制止してしまえば、認知症の方の「行動したい」という意欲を削いでしまうことになりかねません。
- 5共にあること
-
「共にあること」とは、認知症の方が社会に生きるひとりの人間として、尊重されていることが重要だという考えです。例えば、認知症の方が自分の状態、行動したことを、目の前で他人事のように話された場合、患者本人は「自分が輪に入っていない」と見てしまうことがあります。また、自分が普通の扱いをされていないと感じることから不安、不穏に繋がってしまう場合があるのです。
認知症の方の「良い状態」、「良くない状態」とは
認知症の方には、健康状態や精神状態が「良い状態」のときに見られる言動と、「良くない状態」のときに見られる言動があり、患者の状態を把握する、大まかな目安となります。
良い状態
認知症の方の状態が良いときに見られるものは、以下の通りです。
- ゆったりとしており穏やか
- 周囲に対して思いやりがある
- 喜びや自己の感情表現ができる
- 人になにかをしてあげようとする
- 愛情のある言動がある
- 自尊心のある生活を送っている
- ユーモアのある言動がある
良くない状態
認知症の方の状態が良くないときに見られるものは、以下の通りになります。
- 怒りを示す
- 不安や恐怖が表れている
- 退屈を表現している
- 不快感を示す
- 緊張している
- 動揺する、落ち着きがない
- 何に関しても無関心で無感動
- 部屋に引き籠る
- 無抵抗
良くない状態へ向かわせる状況に注意
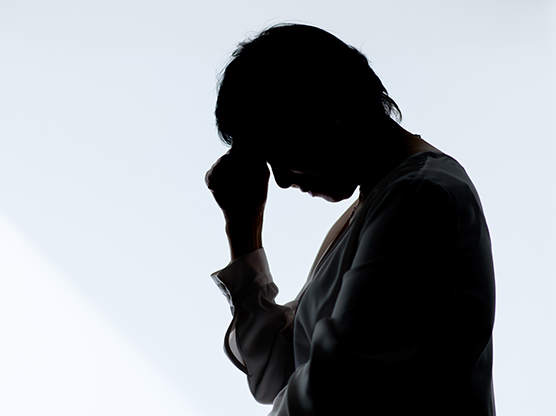
認知症の方における良くない状態は、体調や精神状態、過ごしている環境によって引き起こされる場合があるのです。
特に気を付けなければならないのは、介護者の対応及び言動。介護者のストレスと態度は相手にも伝わりやすく、ときに我慢できず強い言葉や強引な対応をしてしまうと、認知症の方を良くない状態へと向かわせてしまいます。常に丁寧に対応することが、認知症の方の良い状態を維持するコツです。
認知症ケアマッピングとは
「認知症ケアマッピング」とは、認知症の方ひとり一人に合ったケアを提供するために用いられる評価ツールのことであり、パーソン・センタード・ケアに基づいた評価方法。認知症の方の行動を長時間観察し、各行動を良い状態と良くない状態に判別することで、その方にとってどのような環境が適しているのかを、正確に評価することができます。個々に必要なケア、接し方が分かりやすくなるため、認知症の方の捉えづらい感情、行動の原因を把握するのに役立つのです。
まとめ
パーソン・センタード・ケアは、認知症の方に寄り添った、ケアを提供するための考え方。理解力、表現力の低下した認知症患者への対応は難しいものですが、その行動と言動には各々の感情や性格、環境に対する反応などがかかわってきます。可能な限り、その人らしい生活が送れるようにするため、介護者はパーソン・センタード・ケアを理解しておく必要があるのです。


