脊髄小脳変性症(SCD)とは?症状や原因、治る確率を解説
「脊髄小脳変性症」(せきずいしょうのうへんせいしょう)は、神経変性疾患のひとつです。SCDとも呼ばれ、主に脊髄や小脳の神経細胞が変性、喪失することにより、様々な症状が引き起こされます。脊髄小脳変性症(SCD)にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因や症状、進行速度は様々です。なお、脊髄小脳変性症(SCD)は、高齢者に多い疾患として知られています。脊髄小脳変性症(SCD)の症状、原因、治療方法などについて解説します。
脊髄小脳変性症(SCD)の症状

脊髄小脳変性症(SCD)は、「腫瘍」、「血管障害」、「多発性硬化症」といった炎症性疾患など、いくつかの異なる疾患を含みますが、これらの疾患はすべて「運動協調の問題」が特徴です。
運動協調の問題とは、身体の動きに対する整合性が失われ、一連の動作がスムーズに実行できなくなること。例えば、歩行時にふらついてしまうことなどが挙げられます。歩行は単に足を進めるだけではありません。
体のバランスを取る、適切な姿勢を保つなど、複数の動作が組み合わさって可能となっているのです。このような動作の連係が崩れると、歩行時に安定感が失われることになり、転倒につながります。また、文字を正確に書けない、シャツのボタンが留められないなどの症状も、運動協調の問題として出現。
病状が進行すると、自分ひとりで生活することが難しくなり、寝たきりの状態になったり、食事を摂取したりすることが困難になる場合もあり、介護が必要となることも少なくありません。
疾患の種類によっては、「パーキンソン病」のような手の震え、筋肉の硬直の他にも、腱反射(筋肉の反射運動)に異常が出たり、手足が動かしにくく固まったようになったりします。さらに、立ちくらみ、便秘、汗の分泌異常といった自律神経の問題、認知障害、睡眠時の呼吸停止といった症状が伴うこともあるのです。
脊髄小脳変性症(SCD)の原因
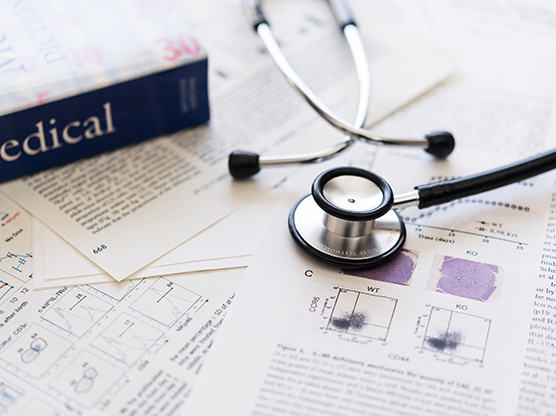
脊髄小脳変性症(SCD)の原因は解明されておらず、常に研究がされている状況です。脊髄小脳変性症(SCD)は、「遺伝性脊髄小脳変性症」と「孤発性脊髄小脳変性症」の2つに分類されます。
遺伝性脊髄小脳変性症は、脊髄小脳変性症(SCD)の約29%を占めており、「優性遺伝」において引き起こされる割合が高い傾向です。これに対し、孤発性脊髄小脳変性症は、脊髄小脳変性症(SCD)の約67%を占めており、「多系統萎縮症」とも呼ばれています。
孤発性脊髄小脳変性症は、遺伝によって発症するものではないため、血縁者に発症した人がいても、自分が発症する可能性は低め。なお、多系統萎縮症では、「グリア」と呼ばれる通常では見られない物質が確認されますが、なぜ見られるのか、また直接の原因とは確定されていません。
脊髄小脳変性症(SCD)の検査方法

脊髄小脳変性症(SCD)は、運動失調が主症状である神経変性疾患。
特定の要因が明確でないものを指すため、正確な診断には、神経変性疾患の中で、具体的にどの疾患であるかを特定することが重要です。具体的な病名を特定するために、様々な検査が行われます。
過去における病歴の聴取
脊髄小脳変性症(SCD)において、最も顕著な症状は「小脳失調」(小脳の機能が障害された状態のこと)です。しかし、小脳失調は脊髄小脳変性症(SCD)だけでなく、他の疾患でも現れることがあります。
正確な診断のためには、病歴の取りまとめが不可欠。例として、過去に「高血圧」、「脳梗塞」を経験していた場合、それらが小脳、脳幹に影響を及ぼし、小脳関連の症状を引き起こす可能性もあります。そうした背景を持つ人は、小脳の症状を示す他の病気を持つリスクが高め。
さらに、遺伝的な要因も関与する場合もあります。家族内で脊髄小脳変性症(SCD)の診断を受けた者がいるかどうかの情報は、遺伝的な背景を特定する上で非常に有用です。
神経症状の診察
脊髄小脳変性症(SCD)は、神経変性に関連した疾患のため、神経学的診断が重要です。神経学的診察では、患者の反射や自然な身体反応を確認。また、制御できない身体の動き、感覚を詳しく調査することで、神経に関連する症状や障害の有無を判断します。
脊髄小脳変性症(SCD)の患者では、小脳失調、パーキンソン症状、麻痺、感覚の低下など、特定の症状が現れやすいため、症状の確認、評価が神経学的診察の中心です。
脊髄小脳変性症(SCD)の治療

脊髄小脳変性症(SCD)に関連する研究は、現在も進行中であり、完全な治療法はまだ存在しません。
ただし、治療の選択肢が一切ないわけではなく、患者の具体的な症状や病状の進行度に応じて、症状を緩和するための対症療法が適用されます。ここでは、脊髄小脳変性症(SCD)が確認された場合の主な治療手段を紹介しましょう。
薬物療法
脊髄小脳変性症(SCD)の根本的な治療法として、患者に起こる症状の緩和、抑制に薬物が使用されることも。
例えば、「セレジスト」という薬は、脊髄小脳変性症(SCD)に伴う「運動障害」の治療に効果があります。定期的な服用により、運動機能の向上が期待されるとともに、病状の進行を遅らせることも可能です。
さらに、脊髄小脳変性症(SCD)によるパーキンソン病の症状が現れた際には、「抗パーキンソン病薬」の使用で、症状を緩和することができる場合もあります。
また、「排尿障害」、「低血圧」といった自律神経の症状、小脳失調による吐き気、めまいに対しては、それぞれの症状に合わせた薬が処方されることで、症状の軽減が期待。これにより、患者の「生活の質」の向上、症状の緩和が図られることとなります。
リハビリテーション
脊髄小脳変性症(SCD)におけるリハビリテーションの主な焦点は、運動能力の維持と現存する能力を最大限に活用すること。
小脳の損傷によって生じるバランスの不安定さ、歩く際の不安定さなど、各患者が抱える小脳失調特有の症状に合わせて、リハビリテーションが実施されます。
また、リハビリテーションの効果は終了後も持続することが重要です。特に、小脳失調の症状だけを持つ患者に対して、集中的なリハビリテーションは症状の悪化を遅らせる効果があるとの報告も。
病状が進行しても、まだ維持されている運動機能を最大限に利用し、その機能を保つためのリハビリテーションを行うことは、脊髄小脳変性症(SCD)を遅らせる上で、非常に効果的です。
脊髄小脳変性症(SCD)が治る確率と寿命について

孤発性脊髄小脳変性症の場合、平均的に症状が始まってから約5年で、患者が車いすを必要とするようになり、8年後にはほとんどの動きが制限され、寝たきりの状態になることが明らかに。病気の経過は約9年とされています。
一方、他の脊髄小脳変性症(SCD)では、症状の進行が孤発性脊髄小脳変性症よりも緩やか。このため、患者は5年、10年、さらには20年以上という長期にわたってこの病気と共に生活することを覚悟しなければなりません。
また、緩やかであっても、症状は進行し、最終的には完全に動けなくなる可能性があるため、早めの段階から適切な医療機関や行政と連携し、将来的な介護サポートの準備を進めることが大切です。
脊髄小脳変性症(SCD)で経済的な支援を受けられる制度
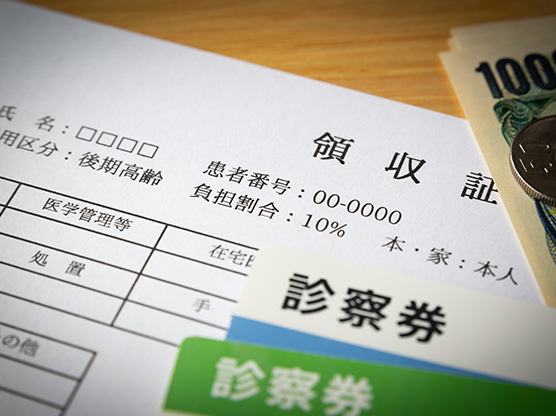
脊髄小脳変性症(SCD)の診断や治療に伴う経済的な負担、介護の必要性は、患者または家族にとって大きな負担となります。
しかし、公的な支援を利用することで、これらの負担を少しでも緩和することが可能です。脊髄小脳変性症(SCD)患者は、様々な助成や支援制度を受けることができます。
- 1介護保険制度
-
脊髄小脳変性症(SCD)は、介護のニーズが特に高まる疾病として、介護保険の「特定疾病」に指定されています。通常、介護保険サービスは65歳以上の高齢者が主な対象ですが、特定疾病に該当する場合は、例外的に利用が可能。
脊髄小脳変性症(SCD)の患者は、症状の進行によって日常生活に多大な支障をきたすことがあるため、このような制度が設けられています。
具体的には、40~65歳未満の脊髄小脳変性症(SCD)の患者も、必要な手続きを行うことで介護保険サービスを受けることができるのです。
介護保険制度を利用するには、まず医師の診断を受け、その後、適切な申請手続きを行うことが必要。申請手続きや利用可能なサービスについては、地域の社会福祉協議会、市区町村の福祉課などで詳しい情報やアドバイスを受けることができます。
- 2難病法に基づく特定医療費助成制度
-
脊髄小脳変性症(SCD)は「指定難病」に認定されており、難病法に基づく「特定医療費助成制度」を活用することで、治療費の一部が助成。受給者証にある自己負担上限月額を限度として医療費を自己負担することになります。
- 3障害年金
-
脊髄小脳変性症(SCD)の症状によって日常生活に支障をきたす場合、身体障害者手帳を取得することが可能。肢体不自由に該当し、市区町村に申請することで審査が行われます。
肢体不自由の障害等級に該当すると、身体障害者手帳の交付が受けられるのです。身体障害者手帳を持つことで、税金の控除、公共料金の割引など様々な特典を受けることができる他、等級によっては、医療費における自己負担分の助成なども受けることができます。
まとめ
本記事では、脊髄小脳変性症(SCD)の症状、原因について詳しく解説しました。脊髄小脳変性症(SCD)の原因は、いまだに解明されておらず、完全な治療法がありません。しかし、薬物療法やリハビリテーションを行うことで、進行を遅らせることができます。なお、脊髄小脳変性症(SCD)は指定難病に認定されており、介護保険の特定疾病にも認定されているため、支援制度がいくつかあります。治療や介護に伴う負担を減らすため、制度の利用も検討しましょう。


